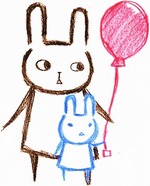2021年10月01日
第2回「2021不登校生のための進路相談会」を開催しました。
9月19日第2回「2021不登校生のための進路相談会」を開催しました。
コロナ禍の緊急事態宣言の中、定員を制限し12組15名の会場参加者と4名のZoom参加者がありました。
静岡県の高校受験状況が変わってきています。
今年度は県立高校の定員割れが起きていて、高校実質無償化による私立高校への人気が増加しています。私立通信制高校は増加しています。
不登校生の受け入れ校には、毎年入試や受け入れ状況等について聞き取りを行っていますが、私立高校、私立通信制高校は、少子化の中で、どう特色を出していくか、そのために方針をどうしていくか、年単位で変わってきています。
このような状況の中で、ますます相談会開催の意義を感じ、これからも子どもに合った進路選択をどのようにすればいいのか、情報提供を行い、親と子どもに寄り添いながら一緒に考えていきます。
今回の体験談は、今年4月からフリースクールのスタッフとして働いている、不登校経験者の今井さんです。質問者は、子ども育ちレスキューネットのメンバーでもあり、今井さんが働くフリースクール空の代表でもある西村です。
西村:今井さんは、最近まで愛知県県民で浜松に引っ越してきた。昼間の定時制を卒業し、芸術大学で音楽を学んで、特別支援学校で3年間音楽の先生をしていたのを辞めて、フリースクールに来てくれた。
小学校と中学校で、2回不登校になったと聞いている。いつ、どんなきっかけだった?
今井:きっかけは、忘れてしまったけど、その時はもちろん苦しかったし、たぶん、先生が怖かったとか友だちとなんかあったとか、たぶん毎日そのことを考えていた。学校は、絶対行きたくない、なんでみんな行かせようとするんだと考えていたと思う。
まず、小3で行かなくなって、小4の先生がすごく良い先生で、保健室登校とかお母さんがついてきても大丈夫ですよと言ってくれたので、毎日うちだけ授業参観みたいだった。小5、小6と通えるようになって、でも継続は難しくて、行ったり行かなかったり。中学校に入学して、夏休み明けに行けなくなった。
自分のことをまとめると、自分は完璧主義だった。友だちが困ってたら優しくしてあげなきゃいけない、先生のいうことは、ちゃんと聞かなければいけない、お母さんがああ言っているからがんばらなきゃいけないとか思っている間に疲れて、中学の時は体調が悪くなって行かなくなった。
西村:体調が悪くなったというのは、病的なことがあった?
今井:最初は、食べたものをもどす感じから始まって、学校を休んでから摂食障害で拒食症、過食症を繰り返し、そのあと幻聴がすごくて「死ね」と「殺せ」とかが聞こえて、「トイレットペーパーをここで切れ」みたいのも聞こえて、指定とかの幻聴が聞こえてストレスだった。不眠とかもあった。
西村:定時制に進もうと思ったときは、症状はある程度消えてた?
今井:幻聴は、たまにあったけど、生活には支障なくなっていた。拒食、過食はあった。
西村:その頃、両親とか周りから言われて嬉しかったことや嫌だったことは?
今井:両親に言われた嫌だったのは、1年くらい引きこもって、車に乗るのもやっとだった頃に「歌が上手になりたい」と思って調べたら、家の近くに音楽スクールがあるのがわかって、両親に言ったら「歌手になるわけでもないのに」と言われて、最初は通わせてもらえなくて、それがすごくショックで嫌だった。両親にとってはそうだったかも知れないけど、私は歌手になりたかったのではなくて、歌が上手くなりたかったのに、せっかくやりたいことがみつかったのに、なんでと思っていた。
今日は、これだけは声を大きくして言わないといけない思った。
「本人と親の幸せは違う、なにかやりたいとお子さんが言ったら、すごく勇気を振り絞っていったかもしれない。私がそうだったから、応援してもらいたい。親も応援できないことがあるかもしれないが、ダメって言われても子どもはどこまでできるか交渉して頑張って、親には応援してほしい」と思う。
西村:それで、音楽スクールは行けずじまい?
今井:そのあと、たぶんお母さんが、こういう進路相談会とかカウンセリングみたいのも行ってたから、娘のことを相談したと思う。急に「行っていいよ」と言いだして、コロッと意見変える、そういうこともイラっとしてた。
お母さんも悩んでたから、それで通わせてもらえて、送り迎えもしてくれて行けたことで、そこから開けた。
西村:今井さんにとっては、音楽が心の支えであり、外へ出るきっかけにもなったと思う。両親の努力もあった。定時制高校に通うことは勇気がいたと思うけど、高校生活はどんな感じだった?
今井:高校生活は、めちゃ楽しかった。でも、最初は普通の学校生活ってどんなのかなと、1回やってみようと思った。自分のメンタルが弱いことがわかっていたので「友だちは、絶対つくらないようにしよう。喧嘩したら、学校に行けなくなる。絶対、卒業する」と決意して行った。でも、結果的には、めちゃくちゃ友だちができて楽しく過ごした。文化祭は、楽しかった。
西村:文化祭は、歌いました?
今井:はい。
西村:そのあと、教員免許を取ろうと思ったのは?
今村:中学校時代に通ったボーカルスクールのマネージャーが、結構ちゃらんぽらんで自由な人で、私はその人のことが好きだった。ちゃらんぽらんに見えるのに教員免許を持っていた。ちゃらんぽらんでもかっこいい、私も教員免許ほしいと思って、免許を取れるのが芸術大学だった。
西村:特別支援学校で、3年間働いたのはどうだった?
今村:めちゃくちゃ楽しかった。特別支援学校で働くぞ!みたいな意気込みはなかったけど、たまたま1年間の臨時教員を募集していた。1年ならできるんじゃない?と思った。ずっとだと、辞めたくなると思った。
1年の任期で入ったけど、「来年同じクラスにしてあげる。生徒の成長をみたいでしょ」と教頭先生に引き留められて、また「向いてるから頑張りなさい。卒業をみたいでしょ」と言われて、3年間務めた。
特別支援学校は大好きだったけど、そのクラスの中に不登校の子がいて、副担任だったけど、学校サイドにいると気持ちがわかるから「学校にきて」と言いたくないし、でもきてくれないと話もできず、何もできなかったので辞めた。
西村:3月の終わりごろに、フリースクール空のブログをみて、どうしても空にいきたいと連絡をもらった。なぜ、安定した生活を辞めたのかと思ったけど、不登校の子に関わりたいという気持ちがあった。いまは、メインのスタッフとして働いている。
いま、日々不登校の子たちと接していて、何を考え何を願ったりする?
今井:まず思うのは、「今日もきてくれてありがとう。うれしいよ」ということ。自分のことだめだという子やこれができないとか、人と比べてしまう子が多いけど、自分もそうだった。だめだとかいう気持ちはわかるけど、過ごしても、1日は同じだから・・。
〇と丸がちょっとかけたCみたいな丸を書くと、丸の欠けたCに注目するけど、でも今日も朝起きれて、ちょっと気が向いて勉強ができたりするとか、生きているだけで良いと思う。足りないとか足りてないとか、視界を狭めていくよりは「今日これできた」「おいしいもの食べた」とか、そういう感じで過ごしてほしいなと思う。
人とのことが気になって比べてしまう子がいるけど、私はお寿司が大好きなのでお寿司で例えると、西村さんがサーモンで、他のスタッフがしゃりで、私が醤油みたいな、それぞれ得意なことが違い、良い場所が違う。醤油のバリエーションは少ないけど、ちょっとでもあるのとないのとは違う。そんな感じの私でいたい。上手く言えないけど、「みんな持ち味違うし、それぞれ良いところも違う」と伝えたかった。
西村:オールラウンド、全部できるまったく必要はないし、発達の得意なところが突出して何か不得意だとか、凸凹が大きい子ほど学校に行きづらい。
学校に通うのは人生の早い時期だけ、残りの人生のほうがずっと長い。仕事を始めてから、結婚してから、子育てしてから、あと人生の方が、ずっと長くてその中から学ぶことが多い。
今井さんのように、不登校だったけど大学にいって教員免許を取って先生になったという話は、サクセスストーリーのように聞こえるけど、まだまだ傷ついたり苦手なものを日々克服したりしている。
まだ、10歳そこそこしか生きていない子どもができないとはたくさんあるのは当たり前。いまうちに自分はこういうことが苦手なんだなと、自分で自分を知る時期が不登校かなと思う。
今日参加されているご両親、不安を抱えている方は多いと思うのですが、大丈夫ということを伝えて終わります。
次回の相談会は、10月17日(日)ワークピア磐田で開催となります。Zoom参加も受け付けます。

コロナ禍の緊急事態宣言の中、定員を制限し12組15名の会場参加者と4名のZoom参加者がありました。
静岡県の高校受験状況が変わってきています。
今年度は県立高校の定員割れが起きていて、高校実質無償化による私立高校への人気が増加しています。私立通信制高校は増加しています。
不登校生の受け入れ校には、毎年入試や受け入れ状況等について聞き取りを行っていますが、私立高校、私立通信制高校は、少子化の中で、どう特色を出していくか、そのために方針をどうしていくか、年単位で変わってきています。
このような状況の中で、ますます相談会開催の意義を感じ、これからも子どもに合った進路選択をどのようにすればいいのか、情報提供を行い、親と子どもに寄り添いながら一緒に考えていきます。
今回の体験談は、今年4月からフリースクールのスタッフとして働いている、不登校経験者の今井さんです。質問者は、子ども育ちレスキューネットのメンバーでもあり、今井さんが働くフリースクール空の代表でもある西村です。
西村:今井さんは、最近まで愛知県県民で浜松に引っ越してきた。昼間の定時制を卒業し、芸術大学で音楽を学んで、特別支援学校で3年間音楽の先生をしていたのを辞めて、フリースクールに来てくれた。
小学校と中学校で、2回不登校になったと聞いている。いつ、どんなきっかけだった?
今井:きっかけは、忘れてしまったけど、その時はもちろん苦しかったし、たぶん、先生が怖かったとか友だちとなんかあったとか、たぶん毎日そのことを考えていた。学校は、絶対行きたくない、なんでみんな行かせようとするんだと考えていたと思う。
まず、小3で行かなくなって、小4の先生がすごく良い先生で、保健室登校とかお母さんがついてきても大丈夫ですよと言ってくれたので、毎日うちだけ授業参観みたいだった。小5、小6と通えるようになって、でも継続は難しくて、行ったり行かなかったり。中学校に入学して、夏休み明けに行けなくなった。
自分のことをまとめると、自分は完璧主義だった。友だちが困ってたら優しくしてあげなきゃいけない、先生のいうことは、ちゃんと聞かなければいけない、お母さんがああ言っているからがんばらなきゃいけないとか思っている間に疲れて、中学の時は体調が悪くなって行かなくなった。
西村:体調が悪くなったというのは、病的なことがあった?
今井:最初は、食べたものをもどす感じから始まって、学校を休んでから摂食障害で拒食症、過食症を繰り返し、そのあと幻聴がすごくて「死ね」と「殺せ」とかが聞こえて、「トイレットペーパーをここで切れ」みたいのも聞こえて、指定とかの幻聴が聞こえてストレスだった。不眠とかもあった。
西村:定時制に進もうと思ったときは、症状はある程度消えてた?
今井:幻聴は、たまにあったけど、生活には支障なくなっていた。拒食、過食はあった。
西村:その頃、両親とか周りから言われて嬉しかったことや嫌だったことは?
今井:両親に言われた嫌だったのは、1年くらい引きこもって、車に乗るのもやっとだった頃に「歌が上手になりたい」と思って調べたら、家の近くに音楽スクールがあるのがわかって、両親に言ったら「歌手になるわけでもないのに」と言われて、最初は通わせてもらえなくて、それがすごくショックで嫌だった。両親にとってはそうだったかも知れないけど、私は歌手になりたかったのではなくて、歌が上手くなりたかったのに、せっかくやりたいことがみつかったのに、なんでと思っていた。
今日は、これだけは声を大きくして言わないといけない思った。
「本人と親の幸せは違う、なにかやりたいとお子さんが言ったら、すごく勇気を振り絞っていったかもしれない。私がそうだったから、応援してもらいたい。親も応援できないことがあるかもしれないが、ダメって言われても子どもはどこまでできるか交渉して頑張って、親には応援してほしい」と思う。
西村:それで、音楽スクールは行けずじまい?
今井:そのあと、たぶんお母さんが、こういう進路相談会とかカウンセリングみたいのも行ってたから、娘のことを相談したと思う。急に「行っていいよ」と言いだして、コロッと意見変える、そういうこともイラっとしてた。
お母さんも悩んでたから、それで通わせてもらえて、送り迎えもしてくれて行けたことで、そこから開けた。
西村:今井さんにとっては、音楽が心の支えであり、外へ出るきっかけにもなったと思う。両親の努力もあった。定時制高校に通うことは勇気がいたと思うけど、高校生活はどんな感じだった?
今井:高校生活は、めちゃ楽しかった。でも、最初は普通の学校生活ってどんなのかなと、1回やってみようと思った。自分のメンタルが弱いことがわかっていたので「友だちは、絶対つくらないようにしよう。喧嘩したら、学校に行けなくなる。絶対、卒業する」と決意して行った。でも、結果的には、めちゃくちゃ友だちができて楽しく過ごした。文化祭は、楽しかった。
西村:文化祭は、歌いました?
今井:はい。
西村:そのあと、教員免許を取ろうと思ったのは?
今村:中学校時代に通ったボーカルスクールのマネージャーが、結構ちゃらんぽらんで自由な人で、私はその人のことが好きだった。ちゃらんぽらんに見えるのに教員免許を持っていた。ちゃらんぽらんでもかっこいい、私も教員免許ほしいと思って、免許を取れるのが芸術大学だった。
西村:特別支援学校で、3年間働いたのはどうだった?
今村:めちゃくちゃ楽しかった。特別支援学校で働くぞ!みたいな意気込みはなかったけど、たまたま1年間の臨時教員を募集していた。1年ならできるんじゃない?と思った。ずっとだと、辞めたくなると思った。
1年の任期で入ったけど、「来年同じクラスにしてあげる。生徒の成長をみたいでしょ」と教頭先生に引き留められて、また「向いてるから頑張りなさい。卒業をみたいでしょ」と言われて、3年間務めた。
特別支援学校は大好きだったけど、そのクラスの中に不登校の子がいて、副担任だったけど、学校サイドにいると気持ちがわかるから「学校にきて」と言いたくないし、でもきてくれないと話もできず、何もできなかったので辞めた。
西村:3月の終わりごろに、フリースクール空のブログをみて、どうしても空にいきたいと連絡をもらった。なぜ、安定した生活を辞めたのかと思ったけど、不登校の子に関わりたいという気持ちがあった。いまは、メインのスタッフとして働いている。
いま、日々不登校の子たちと接していて、何を考え何を願ったりする?
今井:まず思うのは、「今日もきてくれてありがとう。うれしいよ」ということ。自分のことだめだという子やこれができないとか、人と比べてしまう子が多いけど、自分もそうだった。だめだとかいう気持ちはわかるけど、過ごしても、1日は同じだから・・。
〇と丸がちょっとかけたCみたいな丸を書くと、丸の欠けたCに注目するけど、でも今日も朝起きれて、ちょっと気が向いて勉強ができたりするとか、生きているだけで良いと思う。足りないとか足りてないとか、視界を狭めていくよりは「今日これできた」「おいしいもの食べた」とか、そういう感じで過ごしてほしいなと思う。
人とのことが気になって比べてしまう子がいるけど、私はお寿司が大好きなのでお寿司で例えると、西村さんがサーモンで、他のスタッフがしゃりで、私が醤油みたいな、それぞれ得意なことが違い、良い場所が違う。醤油のバリエーションは少ないけど、ちょっとでもあるのとないのとは違う。そんな感じの私でいたい。上手く言えないけど、「みんな持ち味違うし、それぞれ良いところも違う」と伝えたかった。
西村:オールラウンド、全部できるまったく必要はないし、発達の得意なところが突出して何か不得意だとか、凸凹が大きい子ほど学校に行きづらい。
学校に通うのは人生の早い時期だけ、残りの人生のほうがずっと長い。仕事を始めてから、結婚してから、子育てしてから、あと人生の方が、ずっと長くてその中から学ぶことが多い。
今井さんのように、不登校だったけど大学にいって教員免許を取って先生になったという話は、サクセスストーリーのように聞こえるけど、まだまだ傷ついたり苦手なものを日々克服したりしている。
まだ、10歳そこそこしか生きていない子どもができないとはたくさんあるのは当たり前。いまうちに自分はこういうことが苦手なんだなと、自分で自分を知る時期が不登校かなと思う。
今日参加されているご両親、不安を抱えている方は多いと思うのですが、大丈夫ということを伝えて終わります。
次回の相談会は、10月17日(日)ワークピア磐田で開催となります。Zoom参加も受け付けます。

2021年09月12日
9月19日の「2021不登校生のための進路相談会」についてのお知らせ
9月19日の「2021不登校生のための進路相談会」についてのお知らせです。
コロナウイルス感染による緊急事態宣言が9月30日まで延長されたことから、会場参加者の申し込みを締め切ります。Zoom参加者の申し込みは、受付します。Zoomを利用したことがないという方は、お問い合わせください。

コロナウイルス感染による緊急事態宣言が9月30日まで延長されたことから、会場参加者の申し込みを締め切ります。Zoom参加者の申し込みは、受付します。Zoomを利用したことがないという方は、お問い合わせください。

2021年07月11日
第一回「2021 不登校生のための進路相談会」を開催しました
7月4日、第1回「2021不登校生のための進路相談会」を開催しました。
12組19名の参加者(うちZoom参加2名、子ども1人)がありました。
初めてのZoomでの開催はトラブルなく行うことができ、「参考になりました」というご意見をいただくことができました。
高校からの進路指導担当の先生、子どもの居場所、フリースクールの代表やこれからフリースクールを開設する方の参加がありました。
今回の体験談は、小4から不登校になり、小6から通ったフリースクルーに通い、通信制高校を卒業して、フリースクールのスタッフとして働いている伊藤朋美さん。
当日は、静岡新聞の取材にも対応してくださったので、今回は実名での体験談を掲載します。
質問者は、当団体代表(フリースクールドリームフィールド代表)です。
伊藤:小4から不登校になり、小6から通ったドリームフィールドに通い、中学校には一日も登校したことはない。静岡中央高校に3年間通い卒業して、ドリームフィールドのスタッフとして働き、いまもフリースクールに通っている子どもたちのサポートをしている。
大山:最初来たのが、小学校6年生、そのときのいきさつは?
伊藤:幼稚園の頃から、集団行動が苦手で、幼稚園の先生が母親に「萌美ちゃんは、いつでも一人で遊んでいるんです」という子だった。自分は、それが楽で自覚がなかった。小学校に入学すると女子の派閥の中で、上手くやっていく技術身につけなければならくて、陰口をいうのに賛同しなければならなくて、陰口を言わないと自分が対象になる。それに賛同するの自分が嫌だし、友人関係にすごく疲れていた。でも、自分が疲れていることには、小学校低学年の頃は気づいていなくて「なんで仲間はずれの対象になるんだろう」翌日学校に行くと「なんで無視されるんだろう」という疑問をいだき、学校にいきたくないなということを繰り返しながら低学年を過ごし、順調に学校に通っていたわけではなかった。
小学校4年生の時にクラス替えがあり、そのときに「終わった。この中でやっていけるわっけはない」と思った。その時は、学校にいけなくなる理由が、自分の中で友達関係が上手くいかないということを自覚していなかった。始業式が近づくに連れて体調が悪いことが増えて、理由は分析できていなかったので、「なんで学校に行きたくないのか」、親も「なんでいかないんだろう」、クラスの子もなんで学校にこなくなったんだろう」、近所の人も「なんで学校にいかなくなったんだろう」という印象で、すごく静かにストレスをためていて、学校に通えなくなった。結果的には、通わなくてよっかたのではないかと自分では、ずっと思っている。
小学校4年生で学校に行かなくなり、そこから人と会うのが怖くなった。外に出たら、買い物に行っても病院に行っても同級生に会うので、1年間はひきこもっていた。5年性からは友達に会っていたけど「学校に行けてた方がいいのかな、でもいきたくないし」とモヤモヤを感じていた。
6年生のときに親がドリームフィールドができるのを知って、親は通えることを期待していたわけではないけど、自分の中で何かここならと思って「行ってみる!」となって、いまがある。
大山:不登校になって、家の人の反応はどうだったの?
伊藤:私の家は、7歳上の姉が不登校になっている。姉は、大変な思いをしていて、親も祖父母もどう対応していいかわからなかった。姉が精神的に、どんどん悪くなって、姉のおっかげで、私が不登校になっても受け入れられた。母もすごく私が行かないことで悩んでいたみたい。ある時、「学校に行ってない」と言ってしまえばいいんだと、開き直ったら楽になったと言っていた。
大山:お姉ちゃんと対照的だったのは、お姉ちゃんは追い込まれていた。親は悪意を持ってではなく、本人のためを思っていたつもりだけど追い込まれた。もみちんの場合は、そんなに圧がかからず、親が開き直ってくれて、自分らしさを持つことができた。
親が本当に闘うのは、「学校に行かなきゃダメ、学校に行かせなきゃダメ、学校を出ていないとダメ」という既成概念、固定概念だが難しい。
フリースクールにきはじめの頃は、こうでなければいけないというのはあったの?
伊藤:誰かに悪口を言われなくて良いという世界があるとは知らなくて。ドリームフィールドに通い始めて、だんだん自分らしくいても悪く言われたり、仲間外れにされることがないんだと思った。
大山:学校だけではなく、社会の中でも窮屈な集団もあるし、自分らしく生きれる場所もあるし、自分らしく生きられる場所を見つけることが大事かなと思う。
ドリームフィールドにきて、一番の支えになったのはベースかな?
伊藤:そうですね。ドリームフィールドは、私が入ったころからバンド活動をしていて、その影響を受けた。
きっかけは、「サルサガムテープ」という障がいのあるないという関係なくかっこいいバンドで、女性がエレキベースを弾いていた。私の中では、女性はピアノをやる、歌を歌うイメージがあって、そのバンドをみたときに、そのイメージが覆されて、女性のベーシストがかっこよくて、バンドがエネルギッシュで、私もやってみると始めた。ここまで続けると思わなかったけど、いまも弾いている。
大山:ベーシストは、かおりさん。ブルーハーツの梶原さんも入っているバンドで、梶原さんは月一でフリースクールに講師にきてくれている。
伊藤:ベースを始めたことで、すごく自分に自信がついた。自分のことを認められることが増えて、学校に行ってたら楽器を始めることはなかった。12歳の終わりから始めたけど、学校に行ってなくても、新しい趣味ができて、学校に行ってない方が良いんじゃないと思った。ベースに助けられた。
大山:さらっとベースをやってると言ってるけど、もみちんのロックなグルーヴがあって、いろんなグループとやっているけど、本当に気持ちがいい。
スクールオブロックというイベントに参加して、スクエアというバンドの人がみていて、ヤマハの人から連絡が来て、「是非、東京にでてきてやりませんか?」と誘われたけど、サラッと断ったよね。
伊藤:あまりにも冒険する気持ちがないので、東京ってわからないし、普通に弾いていても楽しいし、満足していた。
大山:自分なりに自分の生き方を選んで、自分で判断するというのはすごい。
舞い上がって、プロに呼ばれたと東京に行ってこようとあるけど、保障してくれるわけではない。来たら来たで、どこまで面倒見てくれるかわからない。
サラッと断って、他のベーシストとしたら、何で断るのとなるけど、自分で判断できちんとできたのはすごい。
その頃から、学童(児童デイサービス)に関わってもらって、いまは常勤のスタッフとなっている。
そこまで、いろいろ迷いもあったと思うけど。学童の子と中学生以上の子と関わることは違うけど、その辺りはどう?
伊藤:みんな不登校を経験しているのは同じだけど、それぞれ理由も抱えているものも、こだだわりも違うし、自分がこうだったというのが必ずしもあっているわけでない。いまでもそうだけど、悩んでいる子に本当にアドバイスや接し方ができているかなと、ずっと思いながらやっている。
大山:自分たちの仕事は、日々悩むことは大事で、常に関わりながら悩んでやらなくては。
なぜなら、みんなそれぞれ違う個性をもっているから。
静岡城北通信制高校に行っていたころの話を聞かせて。
伊藤:自分より、上の人が通っていたし、困ったときに一緒に通える人がいるという心強さがあった。私自身、学校が変わっても学校は合わないと思っていたけど、高卒の資格は取りたいと思っていた。静岡中央高校は、無理に友達を作ったり、クラスの中でみんなでやりましょうというのがなくて、自分のペースで学びたい気持ちを優先した。人間関係に無理に取り繕っていく場所を選ぶよりは、ドリームフィールド通いながら、静岡中央高校で勉強したいと選んだ。
大山:入ってみて、どうだった?もみちんの場合は、ペースよくやっていたようだけど?
伊藤:でも、行くの嫌だった。順調に行ってたかというとそうではなかった。勉強自体は嫌ではなかったけど、新居高校へのスクーリングやテストに行くとき、浜松駅から乗り換えるときに「いまなら帰れる」と思って、嫌々いいながら通っていた。
ある日母に、「そんなに嫌なら行くのやめても良いよ」と言われたら、「やっぱいくわ」となった。やめる選択肢があるとわかったのが良かったのかな。それからは、コツコツ単位を取るように行こうと思って3年間行きました。
大山:無理して行かなくてもいいという選択肢があることによって、救われることがある。
伊藤:1回は行ったら、ちゃんと通わないというプレッシャー、高校に限らず、何でも続けなくてはいけないのかなと思う。逃げるのも一個の選択があると、自分に合わないならやめてみるのもありかと思ったところで、もう少し行ってみるかと通っていた。
3年で卒業したから頑張ったねじゃなくて、早く嫌なことを終わせたかった。
自分のペースで5年、6年通えるのもすごいなと思うので、早くければいい遅いのはゆっくすぎるとは思わない。
大山:いまは、専任スタッフとしてやっていると、いろんな特徴のある子がいる。
もみちんはコツコツやれる人、突発的な対応もできるようになってきている。
参加者の子どもさんも、いまの状態だと社会に出れるんだろうかと不安があるかもしれないけど、その子にふさわしい場所とかその子の特徴を生かせる場所がいけば、社会の中で活動できる。ストレスが強い場所だと、その子の個性や特徴が出やすい。もみちんもストレスが強いと、不安が強くなる。
子どもさんが特徴的で困っているということは、ストレスかかっているかもしれない。学校に行かなくてもいいという選択肢がなくて、周りが行かなくもいいと言ってもこだわるかもしれないストレスかかかっているかなとみてあげるといいかなと思う。
もみちんの経験値も上がって、スクールカウンセラーばりに話も聞けるしアドバイスもできる。
これからの抱負、こうしていきたいということは?
伊藤:自分の持っているイメージで、子どもを決めつけない。決めつけると自分をせばめることにもなる。自分の印象で、できるできないの枠に納めない。人はすごく変わると思っているので。
大山:やらせてみようと指示的なものでなく。
伊藤:強要するものでない。私のベースもそうだけど、印象的にはやりそうではなかったけど、きっかけがあればいい方向でやることになると思う。
大山:自分ももみちんがベースを始めると思わなかった。でも、きっかけがあって始めた。人間は変わっていく、子どもは無限の可能性があると思っている。
次回の相談会は、9月19日(日)13:30~アイミティ浜松です。

12組19名の参加者(うちZoom参加2名、子ども1人)がありました。
初めてのZoomでの開催はトラブルなく行うことができ、「参考になりました」というご意見をいただくことができました。
高校からの進路指導担当の先生、子どもの居場所、フリースクールの代表やこれからフリースクールを開設する方の参加がありました。
今回の体験談は、小4から不登校になり、小6から通ったフリースクルーに通い、通信制高校を卒業して、フリースクールのスタッフとして働いている伊藤朋美さん。
当日は、静岡新聞の取材にも対応してくださったので、今回は実名での体験談を掲載します。
質問者は、当団体代表(フリースクールドリームフィールド代表)です。
伊藤:小4から不登校になり、小6から通ったドリームフィールドに通い、中学校には一日も登校したことはない。静岡中央高校に3年間通い卒業して、ドリームフィールドのスタッフとして働き、いまもフリースクールに通っている子どもたちのサポートをしている。
大山:最初来たのが、小学校6年生、そのときのいきさつは?
伊藤:幼稚園の頃から、集団行動が苦手で、幼稚園の先生が母親に「萌美ちゃんは、いつでも一人で遊んでいるんです」という子だった。自分は、それが楽で自覚がなかった。小学校に入学すると女子の派閥の中で、上手くやっていく技術身につけなければならくて、陰口をいうのに賛同しなければならなくて、陰口を言わないと自分が対象になる。それに賛同するの自分が嫌だし、友人関係にすごく疲れていた。でも、自分が疲れていることには、小学校低学年の頃は気づいていなくて「なんで仲間はずれの対象になるんだろう」翌日学校に行くと「なんで無視されるんだろう」という疑問をいだき、学校にいきたくないなということを繰り返しながら低学年を過ごし、順調に学校に通っていたわけではなかった。
小学校4年生の時にクラス替えがあり、そのときに「終わった。この中でやっていけるわっけはない」と思った。その時は、学校にいけなくなる理由が、自分の中で友達関係が上手くいかないということを自覚していなかった。始業式が近づくに連れて体調が悪いことが増えて、理由は分析できていなかったので、「なんで学校に行きたくないのか」、親も「なんでいかないんだろう」、クラスの子もなんで学校にこなくなったんだろう」、近所の人も「なんで学校にいかなくなったんだろう」という印象で、すごく静かにストレスをためていて、学校に通えなくなった。結果的には、通わなくてよっかたのではないかと自分では、ずっと思っている。
小学校4年生で学校に行かなくなり、そこから人と会うのが怖くなった。外に出たら、買い物に行っても病院に行っても同級生に会うので、1年間はひきこもっていた。5年性からは友達に会っていたけど「学校に行けてた方がいいのかな、でもいきたくないし」とモヤモヤを感じていた。
6年生のときに親がドリームフィールドができるのを知って、親は通えることを期待していたわけではないけど、自分の中で何かここならと思って「行ってみる!」となって、いまがある。
大山:不登校になって、家の人の反応はどうだったの?
伊藤:私の家は、7歳上の姉が不登校になっている。姉は、大変な思いをしていて、親も祖父母もどう対応していいかわからなかった。姉が精神的に、どんどん悪くなって、姉のおっかげで、私が不登校になっても受け入れられた。母もすごく私が行かないことで悩んでいたみたい。ある時、「学校に行ってない」と言ってしまえばいいんだと、開き直ったら楽になったと言っていた。
大山:お姉ちゃんと対照的だったのは、お姉ちゃんは追い込まれていた。親は悪意を持ってではなく、本人のためを思っていたつもりだけど追い込まれた。もみちんの場合は、そんなに圧がかからず、親が開き直ってくれて、自分らしさを持つことができた。
親が本当に闘うのは、「学校に行かなきゃダメ、学校に行かせなきゃダメ、学校を出ていないとダメ」という既成概念、固定概念だが難しい。
フリースクールにきはじめの頃は、こうでなければいけないというのはあったの?
伊藤:誰かに悪口を言われなくて良いという世界があるとは知らなくて。ドリームフィールドに通い始めて、だんだん自分らしくいても悪く言われたり、仲間外れにされることがないんだと思った。
大山:学校だけではなく、社会の中でも窮屈な集団もあるし、自分らしく生きれる場所もあるし、自分らしく生きられる場所を見つけることが大事かなと思う。
ドリームフィールドにきて、一番の支えになったのはベースかな?
伊藤:そうですね。ドリームフィールドは、私が入ったころからバンド活動をしていて、その影響を受けた。
きっかけは、「サルサガムテープ」という障がいのあるないという関係なくかっこいいバンドで、女性がエレキベースを弾いていた。私の中では、女性はピアノをやる、歌を歌うイメージがあって、そのバンドをみたときに、そのイメージが覆されて、女性のベーシストがかっこよくて、バンドがエネルギッシュで、私もやってみると始めた。ここまで続けると思わなかったけど、いまも弾いている。
大山:ベーシストは、かおりさん。ブルーハーツの梶原さんも入っているバンドで、梶原さんは月一でフリースクールに講師にきてくれている。
伊藤:ベースを始めたことで、すごく自分に自信がついた。自分のことを認められることが増えて、学校に行ってたら楽器を始めることはなかった。12歳の終わりから始めたけど、学校に行ってなくても、新しい趣味ができて、学校に行ってない方が良いんじゃないと思った。ベースに助けられた。
大山:さらっとベースをやってると言ってるけど、もみちんのロックなグルーヴがあって、いろんなグループとやっているけど、本当に気持ちがいい。
スクールオブロックというイベントに参加して、スクエアというバンドの人がみていて、ヤマハの人から連絡が来て、「是非、東京にでてきてやりませんか?」と誘われたけど、サラッと断ったよね。
伊藤:あまりにも冒険する気持ちがないので、東京ってわからないし、普通に弾いていても楽しいし、満足していた。
大山:自分なりに自分の生き方を選んで、自分で判断するというのはすごい。
舞い上がって、プロに呼ばれたと東京に行ってこようとあるけど、保障してくれるわけではない。来たら来たで、どこまで面倒見てくれるかわからない。
サラッと断って、他のベーシストとしたら、何で断るのとなるけど、自分で判断できちんとできたのはすごい。
その頃から、学童(児童デイサービス)に関わってもらって、いまは常勤のスタッフとなっている。
そこまで、いろいろ迷いもあったと思うけど。学童の子と中学生以上の子と関わることは違うけど、その辺りはどう?
伊藤:みんな不登校を経験しているのは同じだけど、それぞれ理由も抱えているものも、こだだわりも違うし、自分がこうだったというのが必ずしもあっているわけでない。いまでもそうだけど、悩んでいる子に本当にアドバイスや接し方ができているかなと、ずっと思いながらやっている。
大山:自分たちの仕事は、日々悩むことは大事で、常に関わりながら悩んでやらなくては。
なぜなら、みんなそれぞれ違う個性をもっているから。
静岡城北通信制高校に行っていたころの話を聞かせて。
伊藤:自分より、上の人が通っていたし、困ったときに一緒に通える人がいるという心強さがあった。私自身、学校が変わっても学校は合わないと思っていたけど、高卒の資格は取りたいと思っていた。静岡中央高校は、無理に友達を作ったり、クラスの中でみんなでやりましょうというのがなくて、自分のペースで学びたい気持ちを優先した。人間関係に無理に取り繕っていく場所を選ぶよりは、ドリームフィールド通いながら、静岡中央高校で勉強したいと選んだ。
大山:入ってみて、どうだった?もみちんの場合は、ペースよくやっていたようだけど?
伊藤:でも、行くの嫌だった。順調に行ってたかというとそうではなかった。勉強自体は嫌ではなかったけど、新居高校へのスクーリングやテストに行くとき、浜松駅から乗り換えるときに「いまなら帰れる」と思って、嫌々いいながら通っていた。
ある日母に、「そんなに嫌なら行くのやめても良いよ」と言われたら、「やっぱいくわ」となった。やめる選択肢があるとわかったのが良かったのかな。それからは、コツコツ単位を取るように行こうと思って3年間行きました。
大山:無理して行かなくてもいいという選択肢があることによって、救われることがある。
伊藤:1回は行ったら、ちゃんと通わないというプレッシャー、高校に限らず、何でも続けなくてはいけないのかなと思う。逃げるのも一個の選択があると、自分に合わないならやめてみるのもありかと思ったところで、もう少し行ってみるかと通っていた。
3年で卒業したから頑張ったねじゃなくて、早く嫌なことを終わせたかった。
自分のペースで5年、6年通えるのもすごいなと思うので、早くければいい遅いのはゆっくすぎるとは思わない。
大山:いまは、専任スタッフとしてやっていると、いろんな特徴のある子がいる。
もみちんはコツコツやれる人、突発的な対応もできるようになってきている。
参加者の子どもさんも、いまの状態だと社会に出れるんだろうかと不安があるかもしれないけど、その子にふさわしい場所とかその子の特徴を生かせる場所がいけば、社会の中で活動できる。ストレスが強い場所だと、その子の個性や特徴が出やすい。もみちんもストレスが強いと、不安が強くなる。
子どもさんが特徴的で困っているということは、ストレスかかっているかもしれない。学校に行かなくてもいいという選択肢がなくて、周りが行かなくもいいと言ってもこだわるかもしれないストレスかかかっているかなとみてあげるといいかなと思う。
もみちんの経験値も上がって、スクールカウンセラーばりに話も聞けるしアドバイスもできる。
これからの抱負、こうしていきたいということは?
伊藤:自分の持っているイメージで、子どもを決めつけない。決めつけると自分をせばめることにもなる。自分の印象で、できるできないの枠に納めない。人はすごく変わると思っているので。
大山:やらせてみようと指示的なものでなく。
伊藤:強要するものでない。私のベースもそうだけど、印象的にはやりそうではなかったけど、きっかけがあればいい方向でやることになると思う。
大山:自分ももみちんがベースを始めると思わなかった。でも、きっかけがあって始めた。人間は変わっていく、子どもは無限の可能性があると思っている。
次回の相談会は、9月19日(日)13:30~アイミティ浜松です。

2021年06月02日
「2021 不登校生のための進路相談会」を開催します
今年度も、「2021不登校生のための進路相談会」を、4回開催します。
新型コロナウイルスの感染予防対策を行い、開催します。
また、赤い羽根共同募金の新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン「第3回 withコロナ草の根応援助成」の助成金を活用して、Zoom参加も受け付けします。
感染拡大、緊急事態宣言等がなされた場合は、中止になることがあるかもしれませんが、その際は個別相談等の受付を行います。
「子ども不登校だけど、高校に行けるのだろうか」「このままひきこもりになってしまうのではないか」「発達障害の子どもは、どうしたら社会的な自立ができるのか」、悩む保護者の皆さんに、「子ども育ちレスキューネット」は10年以上寄り添ってきました。
子どもたちを支援するネットワークである本団体では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などの情報提供、個別相談の場をつくってきました。昨年度からは、「社会的自立」に向けた地域のサポート情報もお伝えしています。
中学校で不登校を経験し、その後進学、就職した子どもや保護者の体験談も聞くこともできます。 どうぞ、お気軽にご参加ください。
〇内容
13:15~受付
13:30~15:00
・高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明、公立、私立高校の入試、入学後の受け入れ支援体制、義務教育卒業後の自立に向けた支援体制等の情報提供
・不登校を経験しその後進学、就職した子どもや保護者の体験談
・「社会的自立」に向けた地域サポート情報提供
15:00~16:00
不登校生に関する進路及びなんでも悩み個別相談
〇開催日と会場
7月4日(日)9月19日(日)
アイミティ浜松 浜松市中区船越町11-11 会議室3 TEL053-465-5065
10月17日(日)
ワークピア磐田 磐田市国府台57-5 第3会議室 TEL0538-36-8381
11月14日(日)
浜松市市民協働センター 浜松市中区中央1-13-13 TEL053-547-2616
〇希望者には、学習支援を行います(要個別相談)
〇参加費等
参加費無料、予約申し込みをお願いします。
定員:各会場20名(Zoom参加は、制限なし)
参加予約方法:e-mail viancafirst@xvg.biglobe.ne.jpまたは090-3936-5840(事務局服部)
②参加者氏名②参加日③会場又はZoomを選択④連絡先 をお伝えください。
〇対象者
不登校生(中学・高校等)、高校中退者、引きこもりがちの若者とその保護者の皆さん、教育関係者、不登校支援に関心のある方
〇主催 子ども育ちレスキューネット
(西部地区の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
https://childrescuenet.hamazo.tv/
〇後援
浜松市・浜松市教育委員会・磐田市・磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社(予定)
赤い羽根共同募金「withコロナ 草の根助成応援」事業
〇新型コロナウイルス対策について
・参加者の人数を把握するために、参加申し込みをしてください。
当日の参加は、定員に達している場合はお断りさせていただくことがあります。
・体調のすぐれない方の参加は、ご遠慮ください。マスクの着用を、お願いします。
・会場では、健康チェックシート、アルコール消毒・換気等の感染対策防止を行いますので、ご協力をお願いします。
・感染拡大などによる状況に応じて、中止になる場合がありますので、Facebook・ブログで確認をお願いします。中止になった場合は、後日個別相談等の受付を行う予定です。
〇お問い合わせ・当日連絡先
090-3936-5840子ども育ちレスキューネット服部

新型コロナウイルスの感染予防対策を行い、開催します。
また、赤い羽根共同募金の新型コロナ感染下の福祉活動応援全国キャンペーン「第3回 withコロナ草の根応援助成」の助成金を活用して、Zoom参加も受け付けします。
感染拡大、緊急事態宣言等がなされた場合は、中止になることがあるかもしれませんが、その際は個別相談等の受付を行います。
「子ども不登校だけど、高校に行けるのだろうか」「このままひきこもりになってしまうのではないか」「発達障害の子どもは、どうしたら社会的な自立ができるのか」、悩む保護者の皆さんに、「子ども育ちレスキューネット」は10年以上寄り添ってきました。
子どもたちを支援するネットワークである本団体では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などの情報提供、個別相談の場をつくってきました。昨年度からは、「社会的自立」に向けた地域のサポート情報もお伝えしています。
中学校で不登校を経験し、その後進学、就職した子どもや保護者の体験談も聞くこともできます。 どうぞ、お気軽にご参加ください。
〇内容
13:15~受付
13:30~15:00
・高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明、公立、私立高校の入試、入学後の受け入れ支援体制、義務教育卒業後の自立に向けた支援体制等の情報提供
・不登校を経験しその後進学、就職した子どもや保護者の体験談
・「社会的自立」に向けた地域サポート情報提供
15:00~16:00
不登校生に関する進路及びなんでも悩み個別相談
〇開催日と会場
7月4日(日)9月19日(日)
アイミティ浜松 浜松市中区船越町11-11 会議室3 TEL053-465-5065
10月17日(日)
ワークピア磐田 磐田市国府台57-5 第3会議室 TEL0538-36-8381
11月14日(日)
浜松市市民協働センター 浜松市中区中央1-13-13 TEL053-547-2616
〇希望者には、学習支援を行います(要個別相談)
〇参加費等
参加費無料、予約申し込みをお願いします。
定員:各会場20名(Zoom参加は、制限なし)
参加予約方法:e-mail viancafirst@xvg.biglobe.ne.jpまたは090-3936-5840(事務局服部)
②参加者氏名②参加日③会場又はZoomを選択④連絡先 をお伝えください。
〇対象者
不登校生(中学・高校等)、高校中退者、引きこもりがちの若者とその保護者の皆さん、教育関係者、不登校支援に関心のある方
〇主催 子ども育ちレスキューネット
(西部地区の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
https://childrescuenet.hamazo.tv/
〇後援
浜松市・浜松市教育委員会・磐田市・磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社(予定)
赤い羽根共同募金「withコロナ 草の根助成応援」事業
〇新型コロナウイルス対策について
・参加者の人数を把握するために、参加申し込みをしてください。
当日の参加は、定員に達している場合はお断りさせていただくことがあります。
・体調のすぐれない方の参加は、ご遠慮ください。マスクの着用を、お願いします。
・会場では、健康チェックシート、アルコール消毒・換気等の感染対策防止を行いますので、ご協力をお願いします。
・感染拡大などによる状況に応じて、中止になる場合がありますので、Facebook・ブログで確認をお願いします。中止になった場合は、後日個別相談等の受付を行う予定です。
〇お問い合わせ・当日連絡先
090-3936-5840子ども育ちレスキューネット服部

2020年12月08日
第4回「2020 不登校生のための進路相談会」を開催しました。
11月29日、第4回「2020 不登校生のための進路相談会」を開催しました。
今年度の相談会は、新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中、参加者の皆さんのご協力があり、無事開催できました。
4回の参加者は63名(子ども5人)、今年度は中2の相談の参加者を中3を上回りました。また、小学生の相談は、年々増えて、発達障がいの診断を受けている子どもさんの進学を心配しての参加となっています。
新型コロナウイルス感染による休校の影響による不登校やいきしぶりの相談がありました。
進路先を「私立通信制高校を考えている」という相談が増えて、体験談を話してくれた生徒さんを囲んで話したり、学校や支援先の資料を熱心にみていかれます。
今回の体験談は、兄、妹で大平台高校定時制に4月から通っているNさん親子3人です。
昨年の相談会に参加したNさん親子は、大平台高校定時制に通っている子の体験談を聞いて、楽しそうだと思って気持ちが動き、4月から、兄のRさんは大平台高校定時制に編入、妹のYさんも大平台高校定時制に入学しました。お母さんのサポート体験も話していただきました。
Q.高校生活は、どう?
Rさん:とても、充実しています。朝は7時半くらいに家を出発して、8時45分と10時45分からの授業がある。単位制なので、日によって授業時間が変わる。編入したので、始まる時間も終わる時間も早い。英語と数学が好きで、科目担当の先生が特にわかりやすく教えてくれる。
※Rさんは、私立通信制で、30単位とっている。大平台高校定時制では、10時45分に始まるⅡ部に編入して、8時45分に始まるⅠ部の授業も取っている。去年の高卒認定試験で4科目取っているので、大平台高校定時制では単位を取らなくてよいので、その分単位を取らないので通うのは楽になる。来年度に卒業予定。
Q大平台定時制に行こうと思ったのは?
Yさん:相談会で体験談を聞いたこと、自分がどのくらい学校にいけば、単位が取れるとわかった。陸上をやっていたので、部活があったこと。陸上部は全日制と一緒で、練習日を自分で決めることができる。毎日に通っても、苦にならない。3年卒業で、2部の4時間授業で、週に2回6時間授業でもストレスなく通っている。中学校は、2年の後半から通っていなかったけど、高校はほとんど皆勤賞で通っている。
Q.先生との距離は、近い?
Yさん:めちゃ近い。一時期は、お昼を一緒に食べていた。部活の先生とも雑談しにいく。
前期と後期の授業が違うけど、前期に取った科目でも進路のこととかわからないことを担任以外でも教えてくれる。先生ともしゃべりやすい、先生怖いっていうのは全くない。
Q,Rくんは、大平台入学前からバイトしてたけど?
Rさん:昨年12月末から、スーパーでバイトして、編入後は土日祝日基本7時から12時の仕事になって、9月から肉をトレーに入れる作業をしている。今日は、バイトを1時間切り上げてきた。
Yさん:8月から、ハンバーガー屋でハイトを始めた。大学生や年上の人が仕事を教えてくれる人がたくさんいて続けていられる。私も土日祝日を主に、3~4時間でストレスにならない。平日に部活もやっているので、支障にならない。
Q.二人をサポートしてきたお母さんに、いままでと現在のこと話してもらえますか?
母:二人とも個性的過ぎて。兄は、人と話すのが苦手でコミュニケーション取らなくてもいいタイプ、妹はスポ魂みたく中学校でも部活やっていて、部活でいろいろあってフリースクールに行くようになって、兄も私立通信と合わなくてフリースクールに入った。
義務教育だから通わせなくてはいけないと思っていた。子ども達も思っていたが、フリースクールに通うようになって、「頑張らなくても良いんだよ、自分のできることをやっていけば良いんだよ。選択肢は、その中から選べば良いんだよ」というところを教えていただいて、肩の荷がおりた。
やっと私立通信制高校に入って、月8万の月謝を払いながらも学校に通えずにいる、部活を行きたいのに行けなくて家でもやもやして、ナイターで走っている子を見ていると心が痛んだ。フリースクールに通って、身辺自立もできるようになり、歩いて学校にいくの苦だったのが、結構な距離あるフリースクールにまでバスの乗り継いで、コロナで学校休校中の時期は自転車で通った。
規則正しい生活だったり、学習支援していただいて、いまに繋がる。兄の高卒認定試験のことも、手続きから教えてもらった。妹は学校から「公立高校の試験だから、ちゃんと5教科勉強しないと」と言われて、塾も継続して通っていたけど、学習支援もしてもらった。学校の先生の言ったことを真に受けて、ずっと熟に通っていたけど通わなくてよかったかなと思う。そんなに点数のことを気にしないで、いままでのことより、これから自分がどうしたいか、どういう職業につきたいかと描いていれば、たくさんチャンスがある学校だと思う。
妹が入学したとき「イグジットがたくさんいる、金髪やピンクの髪の毛がいて、すごいジャングルみたい」と言っているときがあった。手帳を持っている子もいるし、外国籍の子もいる、先生方が寛大です。兄は、コミュニケーションをあまりとらなくても、バイトしていることを知っていたり、「90日働くと教科書代タダだよ」「こういう進路先があるよ」とか、妹には「陸上やりたかったらくれば、好きにして」と、選択肢をいっぱい与えてくれるけど「自分たちでやりたいようにやっていけばいいんだよ、焦らなくていいんだよ」と言ってもらえるのは親としては安心できる。
去年は、どよーんとした家のなかで、学校から連絡が来ると「どうなっているの」というとドアを塞ぐ娘と高卒認定の試験でピリピリしている兄だったりとあったけど、いまは「そんなこともあったね」と笑って話せるようになったのは、いまが充実しているのかなと思う。
高校に入ってからは、弁当を作ることしができないけど、子ども達からはいままで聞いたことがなかった学校の情報をきくことができる。
Q.Rさんの高校の選択肢は、大平台高校がなかった?
母:兄は、手帳を持っていて、小学校から発達級できていた。中学に入学するとき、高校受験をしたいので中3のときは、発達級でなく普通級で卒業という話だった。先生の異動で引き次ができていなくて、進路相談は通信制一択だった。こんなたくさん情報があることも、大平台定時制のこともしらなかった。定時制は働きながら通うイメージではなくて、いまは発達級に通う子どもでもやりたいことがあれば受け入れないわけでなないという感じ。通信制は、発達級からいく子が多いのかな。娘の普通級の子どもに先生方が熱心に進路指導を行うなかで、発達級の情報が少ないと感じた。職業訓練校か大平台にいくか考えて、大平台したが、情報は欲しいのが正直なところ。
Q.編入試験は3教科、入学試験は5教科、集団面談と個別面接、受験はどうでした?
Yさん:まったく勉強をしなかった、点数はどうだったかわからいけど、面接重視だと思う。
グループ面談は質問は3つくらい、個人面接はぐいぐい聞かれるので正直に答えればいい受かると思う。質問は「なんで中学校いけなくなったか」「得意科目」「尊敬する人」で、勉強に関することではないので考えずに素直に答えればいいと思う。
Rさん:個別面接にきかれたことは覚えてない。数学と英語は自信があった。
来年度の相談会の予定は、ブログ、Facebookでお知らせします。
今年度の相談会は、新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中、参加者の皆さんのご協力があり、無事開催できました。
4回の参加者は63名(子ども5人)、今年度は中2の相談の参加者を中3を上回りました。また、小学生の相談は、年々増えて、発達障がいの診断を受けている子どもさんの進学を心配しての参加となっています。
新型コロナウイルス感染による休校の影響による不登校やいきしぶりの相談がありました。
進路先を「私立通信制高校を考えている」という相談が増えて、体験談を話してくれた生徒さんを囲んで話したり、学校や支援先の資料を熱心にみていかれます。
今回の体験談は、兄、妹で大平台高校定時制に4月から通っているNさん親子3人です。
昨年の相談会に参加したNさん親子は、大平台高校定時制に通っている子の体験談を聞いて、楽しそうだと思って気持ちが動き、4月から、兄のRさんは大平台高校定時制に編入、妹のYさんも大平台高校定時制に入学しました。お母さんのサポート体験も話していただきました。
Q.高校生活は、どう?
Rさん:とても、充実しています。朝は7時半くらいに家を出発して、8時45分と10時45分からの授業がある。単位制なので、日によって授業時間が変わる。編入したので、始まる時間も終わる時間も早い。英語と数学が好きで、科目担当の先生が特にわかりやすく教えてくれる。
※Rさんは、私立通信制で、30単位とっている。大平台高校定時制では、10時45分に始まるⅡ部に編入して、8時45分に始まるⅠ部の授業も取っている。去年の高卒認定試験で4科目取っているので、大平台高校定時制では単位を取らなくてよいので、その分単位を取らないので通うのは楽になる。来年度に卒業予定。
Q大平台定時制に行こうと思ったのは?
Yさん:相談会で体験談を聞いたこと、自分がどのくらい学校にいけば、単位が取れるとわかった。陸上をやっていたので、部活があったこと。陸上部は全日制と一緒で、練習日を自分で決めることができる。毎日に通っても、苦にならない。3年卒業で、2部の4時間授業で、週に2回6時間授業でもストレスなく通っている。中学校は、2年の後半から通っていなかったけど、高校はほとんど皆勤賞で通っている。
Q.先生との距離は、近い?
Yさん:めちゃ近い。一時期は、お昼を一緒に食べていた。部活の先生とも雑談しにいく。
前期と後期の授業が違うけど、前期に取った科目でも進路のこととかわからないことを担任以外でも教えてくれる。先生ともしゃべりやすい、先生怖いっていうのは全くない。
Q,Rくんは、大平台入学前からバイトしてたけど?
Rさん:昨年12月末から、スーパーでバイトして、編入後は土日祝日基本7時から12時の仕事になって、9月から肉をトレーに入れる作業をしている。今日は、バイトを1時間切り上げてきた。
Yさん:8月から、ハンバーガー屋でハイトを始めた。大学生や年上の人が仕事を教えてくれる人がたくさんいて続けていられる。私も土日祝日を主に、3~4時間でストレスにならない。平日に部活もやっているので、支障にならない。
Q.二人をサポートしてきたお母さんに、いままでと現在のこと話してもらえますか?
母:二人とも個性的過ぎて。兄は、人と話すのが苦手でコミュニケーション取らなくてもいいタイプ、妹はスポ魂みたく中学校でも部活やっていて、部活でいろいろあってフリースクールに行くようになって、兄も私立通信と合わなくてフリースクールに入った。
義務教育だから通わせなくてはいけないと思っていた。子ども達も思っていたが、フリースクールに通うようになって、「頑張らなくても良いんだよ、自分のできることをやっていけば良いんだよ。選択肢は、その中から選べば良いんだよ」というところを教えていただいて、肩の荷がおりた。
やっと私立通信制高校に入って、月8万の月謝を払いながらも学校に通えずにいる、部活を行きたいのに行けなくて家でもやもやして、ナイターで走っている子を見ていると心が痛んだ。フリースクールに通って、身辺自立もできるようになり、歩いて学校にいくの苦だったのが、結構な距離あるフリースクールにまでバスの乗り継いで、コロナで学校休校中の時期は自転車で通った。
規則正しい生活だったり、学習支援していただいて、いまに繋がる。兄の高卒認定試験のことも、手続きから教えてもらった。妹は学校から「公立高校の試験だから、ちゃんと5教科勉強しないと」と言われて、塾も継続して通っていたけど、学習支援もしてもらった。学校の先生の言ったことを真に受けて、ずっと熟に通っていたけど通わなくてよかったかなと思う。そんなに点数のことを気にしないで、いままでのことより、これから自分がどうしたいか、どういう職業につきたいかと描いていれば、たくさんチャンスがある学校だと思う。
妹が入学したとき「イグジットがたくさんいる、金髪やピンクの髪の毛がいて、すごいジャングルみたい」と言っているときがあった。手帳を持っている子もいるし、外国籍の子もいる、先生方が寛大です。兄は、コミュニケーションをあまりとらなくても、バイトしていることを知っていたり、「90日働くと教科書代タダだよ」「こういう進路先があるよ」とか、妹には「陸上やりたかったらくれば、好きにして」と、選択肢をいっぱい与えてくれるけど「自分たちでやりたいようにやっていけばいいんだよ、焦らなくていいんだよ」と言ってもらえるのは親としては安心できる。
去年は、どよーんとした家のなかで、学校から連絡が来ると「どうなっているの」というとドアを塞ぐ娘と高卒認定の試験でピリピリしている兄だったりとあったけど、いまは「そんなこともあったね」と笑って話せるようになったのは、いまが充実しているのかなと思う。
高校に入ってからは、弁当を作ることしができないけど、子ども達からはいままで聞いたことがなかった学校の情報をきくことができる。
Q.Rさんの高校の選択肢は、大平台高校がなかった?
母:兄は、手帳を持っていて、小学校から発達級できていた。中学に入学するとき、高校受験をしたいので中3のときは、発達級でなく普通級で卒業という話だった。先生の異動で引き次ができていなくて、進路相談は通信制一択だった。こんなたくさん情報があることも、大平台定時制のこともしらなかった。定時制は働きながら通うイメージではなくて、いまは発達級に通う子どもでもやりたいことがあれば受け入れないわけでなないという感じ。通信制は、発達級からいく子が多いのかな。娘の普通級の子どもに先生方が熱心に進路指導を行うなかで、発達級の情報が少ないと感じた。職業訓練校か大平台にいくか考えて、大平台したが、情報は欲しいのが正直なところ。
Q.編入試験は3教科、入学試験は5教科、集団面談と個別面接、受験はどうでした?
Yさん:まったく勉強をしなかった、点数はどうだったかわからいけど、面接重視だと思う。
グループ面談は質問は3つくらい、個人面接はぐいぐい聞かれるので正直に答えればいい受かると思う。質問は「なんで中学校いけなくなったか」「得意科目」「尊敬する人」で、勉強に関することではないので考えずに素直に答えればいいと思う。
Rさん:個別面接にきかれたことは覚えてない。数学と英語は自信があった。
来年度の相談会の予定は、ブログ、Facebookでお知らせします。
2020年10月28日
第3回「2020 不登校生のための進路相談会」を、開催しました。
10月25日、第3回「2020 不登校生のための進路相談会」を、開催しました。
年1回の磐田市での開催に、13組21名(子ども2人)の参加者があり、今回は、中学3年生の参加者は少なく、中学2、3年生の参加者が多く、事前に高校の情報がほしいと参加したようです。
今回も、浜名高校定時制の中村先生から、定時制のお話をしていただきました。
〇定時制ってどんなところ?
新居高校定時制の中村先生のお話
・働きながら学校に通っている生徒というイメージがあるが、正社員で働いている生徒はいない。不登校だった生徒1/3、外国人や発達障がいがあると思われる生徒が1/3ずつkらい。
・定時制は、4年制だが、3年で卒業することもできる。3年で卒業したい生徒は、学校で応援する。1年生のテストで、選抜する。
・定時制は、単位を落とすと留年がある。中央高校通信制で、単位を取ることができれば4年で卒業できることもある。5年生がいることがある。
・入試は、作文、面接。作文は、5つのテーマから選んでその場で書く。大平台高校、浜松工業は、5科目になる。面接は、1次は集団で、2次は個別。1日で終わる。
・定員は、1学年40名定員。卒業まで、一割くらいは中退している。進路がきまらずに卒業する生徒は、3割くらい。
今回の験談は、中3からフリースクールに通い、現在中央高校通信制2年生のY君。
Q、小学校からの不登校だった?原因は、いじめだった?
A.そう。今考えたとき、今の自分と比べるとやる気とかがなかった、勉強がいやだったからいかないという感じだったのかなと、今は思う。
Q.今振り返るとそうかもしれないけど、その頃は混乱状態だった?
A.そう、思う。
Q中学校は、私立の中高一貫の入ったけど、中2で行かなくなった、そのときは?
A.そのときの学年主任の先生が、あまり良くなかった。生徒間、先生間のいじめがすごくあった。
先生が辞めたり、自分もいじめにあっていて、行きたくなくなった。
Q地元の中学に行きたくなくて、私立に行ったけどいじめがあったということ?
A.そういう感じ。ほほ、一学期のみ行った。。
Qそのあと、家にいた感じ?
A.学校には行かなかったけど、趣味の鉄道を乗りに行くこともあったので、家からは出ていた。
Q.天竜病院に入院して、天竜特別支援学校にいったのは、何年生のとき?
A.中2の夏くらいから1月まで、退院して戻ってきた。天竜特別支援学校には、ほぼ1日.いった日もあった。先生が、すごく親身になって接してくれた。先生って、こんなに優しいのなら行けるかもと思った。
Q.退院すると在籍校に戻るわけだけど、在籍校には行けなかった?
A.中2の3月までは行けていた。そこまでは天竜病院から、こうしてほしいお願いされいたことがあったけど、中3にそれをなくされた感じになったので、苦痛になった。
Q.中3の夏ごろに、スリースクールにきて「高校どうしよう」となったとき、中高一貫の学校に戻る気はなく、大平台定時制か中央高校通信制か考えた?
A.天竜特別支援学校も考えたが、距離が遠くてやめた。最終的は、2つになった。
中央高校通信制だと、自分の時間がすごい取れる。いままで小中学校は趣味もあるし、学校に行かなくてはいけないと自分の時間がなくて、大平台だと同じだと考えた。
自分の趣味も学校も両立できるのは、中央高校に決めた。
Q.中央高校に入って、去年は単位も全部取れて、高卒認定試験で地理と国語総合を受けた。そんなに、勉強しなくても受かった?
A.そこまで本気でやったとは思っていない。過去問題集を少しやった感じ。再来週は、数学Ⅰと現代社会を受ける。(高卒認定試験で取れた単位は、中央高校通信制の単位となる)
Q.最近、バイトも始めた?
A.高齢者の施設で、週2回掃除や配膳をやっている。中央高校の勉強、趣味と全部、同じくらいのペースでやっている。
Q.最近は、バイクもやっている?
A.最初1年目は、中央高校にも行く気が起きなくて。「移動手段を兼ねて、原付免許でも取ろうかな?」と母に相談したら、「免許とっただけでは怖いから、125ccを取ってきなさい」と言われた。中央高校の勉強を頑張ったせいか、教習もフルタイム行けて面鏡が取れて自分に自信がでてきた。バイクに乗っていて、自分の他人も守らなければならない、自分に自信がなければ怖くて運転できない、そこで自信がついて、2年目に入ってバイクで学校に通いながら、フルタイムで学校に通っても苦でなくなった。
Q.公共交通機関が苦手な子がいて、自転車で遠くまで可洋子もいる。バイクに乗るようになって、行動範囲が一機に広がった?
A. 鉄道は好きだったけど、学校にいくために電車でいくのは・・と思っていた。バイクに乗りたいから、学校にいくという原動力になって、休むことが少なくなった。
Q. 将来の夢は?
Aいまのところ、大井川鉄道のSLの機関士になること。
Q 前向きになれたのは、どうして?
A.いままでの経験してきたことが、全部影響になっているとは思う。
フリースクールに通って人に関わったこと、天竜特別支援学校の先生に関わったこと、
中1にドイツに行って「世界ってこんなに広いんだ」と思って、「やりたいこと仕事にしないと長続きしない、やりたいことをやるために頑張ろう」という感じになった。
Q,バイクに乗り始めたころ、いじめた子に見せにいきたいと言っていたが、いじめた子に言いたいことはある?
Aいじめの原因って相手にもあると思うけど、自分もゼロと思わない。自分もそこは謝って仲直りしたいと思う。
Q参加者の保護者と子どもに伝えたいことは?
A.ますは、子どもに。不登校で悩んでいるときに、無理に自分を外へ出すとか、学校に行くはやらなくていい。自分がやりたたい、あそこに行きたい、学校に行きたいとか、そういう気持ちがでてきたときにいくとると、すごい自分が変われるきっかけになると思う。
きっかけを作るのは自分だけだと自分だけだと大変なので、それは親に協力してもらうと未来が開けると思う。夢はあった方が、自分が頑張れる原動力になる。職業だけではなく、やりたいことでいい。
親には、自分は干渉されるのが嫌で「放っておいてくれ!」と感じが多かった。何かをやりたい、こうしたいとでできたときに、全力でサポートすることが、子どもにとって一番良いとことだと思う。
次回の相談会は、今年度最後になります。11月29日(日)13:30~「アイミティ浜松」になります。
個別相談は、いつでも受け付けます。

年1回の磐田市での開催に、13組21名(子ども2人)の参加者があり、今回は、中学3年生の参加者は少なく、中学2、3年生の参加者が多く、事前に高校の情報がほしいと参加したようです。
今回も、浜名高校定時制の中村先生から、定時制のお話をしていただきました。
〇定時制ってどんなところ?
新居高校定時制の中村先生のお話
・働きながら学校に通っている生徒というイメージがあるが、正社員で働いている生徒はいない。不登校だった生徒1/3、外国人や発達障がいがあると思われる生徒が1/3ずつkらい。
・定時制は、4年制だが、3年で卒業することもできる。3年で卒業したい生徒は、学校で応援する。1年生のテストで、選抜する。
・定時制は、単位を落とすと留年がある。中央高校通信制で、単位を取ることができれば4年で卒業できることもある。5年生がいることがある。
・入試は、作文、面接。作文は、5つのテーマから選んでその場で書く。大平台高校、浜松工業は、5科目になる。面接は、1次は集団で、2次は個別。1日で終わる。
・定員は、1学年40名定員。卒業まで、一割くらいは中退している。進路がきまらずに卒業する生徒は、3割くらい。
今回の験談は、中3からフリースクールに通い、現在中央高校通信制2年生のY君。
Q、小学校からの不登校だった?原因は、いじめだった?
A.そう。今考えたとき、今の自分と比べるとやる気とかがなかった、勉強がいやだったからいかないという感じだったのかなと、今は思う。
Q.今振り返るとそうかもしれないけど、その頃は混乱状態だった?
A.そう、思う。
Q中学校は、私立の中高一貫の入ったけど、中2で行かなくなった、そのときは?
A.そのときの学年主任の先生が、あまり良くなかった。生徒間、先生間のいじめがすごくあった。
先生が辞めたり、自分もいじめにあっていて、行きたくなくなった。
Q地元の中学に行きたくなくて、私立に行ったけどいじめがあったということ?
A.そういう感じ。ほほ、一学期のみ行った。。
Qそのあと、家にいた感じ?
A.学校には行かなかったけど、趣味の鉄道を乗りに行くこともあったので、家からは出ていた。
Q.天竜病院に入院して、天竜特別支援学校にいったのは、何年生のとき?
A.中2の夏くらいから1月まで、退院して戻ってきた。天竜特別支援学校には、ほぼ1日.いった日もあった。先生が、すごく親身になって接してくれた。先生って、こんなに優しいのなら行けるかもと思った。
Q.退院すると在籍校に戻るわけだけど、在籍校には行けなかった?
A.中2の3月までは行けていた。そこまでは天竜病院から、こうしてほしいお願いされいたことがあったけど、中3にそれをなくされた感じになったので、苦痛になった。
Q.中3の夏ごろに、スリースクールにきて「高校どうしよう」となったとき、中高一貫の学校に戻る気はなく、大平台定時制か中央高校通信制か考えた?
A.天竜特別支援学校も考えたが、距離が遠くてやめた。最終的は、2つになった。
中央高校通信制だと、自分の時間がすごい取れる。いままで小中学校は趣味もあるし、学校に行かなくてはいけないと自分の時間がなくて、大平台だと同じだと考えた。
自分の趣味も学校も両立できるのは、中央高校に決めた。
Q.中央高校に入って、去年は単位も全部取れて、高卒認定試験で地理と国語総合を受けた。そんなに、勉強しなくても受かった?
A.そこまで本気でやったとは思っていない。過去問題集を少しやった感じ。再来週は、数学Ⅰと現代社会を受ける。(高卒認定試験で取れた単位は、中央高校通信制の単位となる)
Q.最近、バイトも始めた?
A.高齢者の施設で、週2回掃除や配膳をやっている。中央高校の勉強、趣味と全部、同じくらいのペースでやっている。
Q.最近は、バイクもやっている?
A.最初1年目は、中央高校にも行く気が起きなくて。「移動手段を兼ねて、原付免許でも取ろうかな?」と母に相談したら、「免許とっただけでは怖いから、125ccを取ってきなさい」と言われた。中央高校の勉強を頑張ったせいか、教習もフルタイム行けて面鏡が取れて自分に自信がでてきた。バイクに乗っていて、自分の他人も守らなければならない、自分に自信がなければ怖くて運転できない、そこで自信がついて、2年目に入ってバイクで学校に通いながら、フルタイムで学校に通っても苦でなくなった。
Q.公共交通機関が苦手な子がいて、自転車で遠くまで可洋子もいる。バイクに乗るようになって、行動範囲が一機に広がった?
A. 鉄道は好きだったけど、学校にいくために電車でいくのは・・と思っていた。バイクに乗りたいから、学校にいくという原動力になって、休むことが少なくなった。
Q. 将来の夢は?
Aいまのところ、大井川鉄道のSLの機関士になること。
Q 前向きになれたのは、どうして?
A.いままでの経験してきたことが、全部影響になっているとは思う。
フリースクールに通って人に関わったこと、天竜特別支援学校の先生に関わったこと、
中1にドイツに行って「世界ってこんなに広いんだ」と思って、「やりたいこと仕事にしないと長続きしない、やりたいことをやるために頑張ろう」という感じになった。
Q,バイクに乗り始めたころ、いじめた子に見せにいきたいと言っていたが、いじめた子に言いたいことはある?
Aいじめの原因って相手にもあると思うけど、自分もゼロと思わない。自分もそこは謝って仲直りしたいと思う。
Q参加者の保護者と子どもに伝えたいことは?
A.ますは、子どもに。不登校で悩んでいるときに、無理に自分を外へ出すとか、学校に行くはやらなくていい。自分がやりたたい、あそこに行きたい、学校に行きたいとか、そういう気持ちがでてきたときにいくとると、すごい自分が変われるきっかけになると思う。
きっかけを作るのは自分だけだと自分だけだと大変なので、それは親に協力してもらうと未来が開けると思う。夢はあった方が、自分が頑張れる原動力になる。職業だけではなく、やりたいことでいい。
親には、自分は干渉されるのが嫌で「放っておいてくれ!」と感じが多かった。何かをやりたい、こうしたいとでできたときに、全力でサポートすることが、子どもにとって一番良いとことだと思う。
次回の相談会は、今年度最後になります。11月29日(日)13:30~「アイミティ浜松」になります。
個別相談は、いつでも受け付けます。

2020年10月27日
講演会「自分らしく生きる、自立するためのきっかけをつくろう!」を、YouTubeで公開します。
10月11日の講演会「自分らしく生きる、自立するためのきっかけをつくろう!」を、YouTubeで公開します。
講演①「自分らしく生きよう」–子どもの特性を理解するために−
浜松市発達相談支援センタールピロ所長 内山敏さん
https://www.youtube.com/watch?v=VD7Ays0-SLM&feature=youtu.be
講演②「自立するためのきっかけをつくろう」−地域の支援に繋がろ–
https://www.youtube.com/watch?v=9C8B5HHy7AI&feature=youtu.be
パネルディスカッション
「子ども・若者、保護者の味方!地域支援を繋ぐために」
https://www.youtube.com/watch?v=CVoGal7gHS0&feature=youtu.be
の、三部制です。
是非、ご覧下さい。

講演①「自分らしく生きよう」–子どもの特性を理解するために−
浜松市発達相談支援センタールピロ所長 内山敏さん
https://www.youtube.com/watch?v=VD7Ays0-SLM&feature=youtu.be
講演②「自立するためのきっかけをつくろう」−地域の支援に繋がろ–
https://www.youtube.com/watch?v=9C8B5HHy7AI&feature=youtu.be
パネルディスカッション
「子ども・若者、保護者の味方!地域支援を繋ぐために」
https://www.youtube.com/watch?v=CVoGal7gHS0&feature=youtu.be
の、三部制です。
是非、ご覧下さい。

2020年10月18日
講演会「自分らしく生きる、自立するためのきっかけをつくろう!」を開催しました。
コロナ禍の中、また台風接近が心配されましたが、10月11日に38名の参加者(保護者、教員、支援機関職員、市議など)があり、講演会を開催することができました。
今回の講演の開催主旨は、昨年10月に文部科学省が通知した「不登校生生徒への支援の在り方」で、不登校児童生徒支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標とすることを目指すのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること」と明確化されたことにありました。
当会で開催している「不登校生のための進路相談会」(昨年まで「不登校生のための進学相談会」)においても、ほとんどの参加者は子どもの将来への不安、心配が尽きない状況から、「社会的自立」を目指すうえで必要とされている「対人関係」と「キャリア教育」についての講演会を開催することにしました。
講師の内山さん、池田さんからは、不登校であることや障がいの有無に関係なく、選択をする権利は「子ども本人」、本人も保護者も関わっている支援者もひとりで頑張らない、本人も家族も楽しく過ごすことと、共通したお話がありました。
これは、当会でも相談会でいつも伝えていることです。
簡単に、講演内容についてまとめますが、講演会については、後日YouTubeで配信予定です。配信が決まりましたらお知らせしますので。是非、ご覧になってください。
講演①「自分らしく生きよう」-子供の特性を理解していくためにー
浜松発達相談支援センタールピロ 所長 内山敏さん
・ルピロの相談は、乳幼時から大人まで、診断前の相談が92%、主訴や背景は様々。
学齢期前から成人まで、問題は積み重ねられて、複雑になってくる。
・子どもの発言に嫌な気持ちをしたら、冷静に怒らずそのこと伝える、パニックや大声を出したりしたら、言い聞かせるのでなく、別の場所で冷静な口調で話しかける、言葉でわからないときは、絵や図をみせたり、やってみせるとわかりやすい。
・パニックの誘因となるなんらかの感覚異常があると思われることは多い。生活のわずらわしさに対して対処することができる、克服させるものではない。
・発達障がいについて、ラベリングで終わるのは、対処ではない。対応については、個別性が強い。
・子どもは、周りの期待に気づいている、必ずしも本音を言わない、返事をしなくても謝れなくても言われたことはわかっているけど、大人は「わかっているか?」と返事を聞きたい。
・社会的自立の要件(障がいの有無に関わらず)
試行錯誤して自分で摘み取るが、「自分らしく生きること」につながるのでは?
1)身辺の自立 2)基本的なコミュニケーション 3)危険の認識と回避 4)金銭管理 5)生きがいを見つける 6)家族・友人と楽しむ
・自分らしさを生きるを構成するもの
1)支援は「与えられる恩恵」ではなく、「選択の権利」 2)支援は治療やリハビリや指導で完成させるものではなく、さらに怠けや弱さを克服させることでもなく、本人の「有効な選択肢」を増やすこと。平等に、大人が選びやすい情報の提供をする
浜松発達相談支援センタールピロ https://www.rupiro.com/
講演②「自立するためのきっかけをつくろう」-地域の支援に繋がろうー
NPO法人青少年就労支援支援ネットワーク静岡 事務局長 池田佳寿子さん
・働きたいけど働けない人びとに対して、市民ネットワークによる伴走型の就労支援を提供することを通じて、働く喜びを分かち合える、相互扶助の社会をつくることを目的としている。コロナ禍で、失業する人、仕事がなくなる人が増えている。誰にも起こること。
・IPS(Individual Placement and Support)就労支援プログラムの「クライアントの好みを重視する。サービスの提供は、プロバイダーの判断より、クライアントの好みと選択に基づいている」こと、本人の信頼を原則とする。
・「静岡方式」が、地域を大切にしている理由。「困っている人」ほど自ら働くことが困難で、相談窓口に赴くことが難しい。地域の民生委員や自治会の方など、地域のつながりを通して出会う。行政の制度や市場からこぼれる人々を。互助の原理で再組織化して生活しやすくする。隙間に陥る人々を、制度で埋めるのではなく、地域で支える。不可視化された困りことを中心に地域をつくる。
県内に16000人超のボランティア、西部地区は約530名がいる。地域若者サポートステーション事業、学習支援・生活支援事業、引きこもり支援事業等。
・何をもって「自立」と言うのか。社会的養護を受けた方の答えは、「情報が取れる」「選択肢.がある」「喜怒哀楽が出せる」など、子どもの考えは大人の考えの自立の手前にある。
・私たちは人を支えない、支えを外してしまえば落ちてしまう。本人の人生はあくまで、本人のもの、本人の人生を送るものを「応援する」応援団。
・ウィークタイズ(弱い紐帯)の強み。ごちゃ混ぜは状況により、「支えるとき」「支えられるとき」、支える側・支える側でない、誰もが応援可能。
・好きなこと、好きなもの、好きなひと、「ストレングス」で、縁を増やし、運に出会うこと、運を縁に変えて、繋がろう。
・これからできること。 ◇みんなの原則 1)過去でなく、未来を見る、問題でなく強みをみる。 2)自分が変わる(他人を変えようとしない)・変わるために人から助けてもらう 3)小さな変化を起こす、変化に気づく、日常なことを大切にする。
◇応援する人ができること 1)焦らない、無理しない、無理をすると本人を責めたくなる。 2)話すこと、仲間を作る。
◇本人ができること 1)「自分ほめ」上手になる 2)嫌な経験も失敗も大切 3)自分に得な考えをする 4)自分にない考えや選択肢を手に入れる 5)身近な人から、どんどんはなしてみる 6)素直になる、騙され得意になる。
・母子面接での場面、母親はイライラしている、「自分が何とかしなくては」と思ってしまう。母親が楽しそうだと、本人も気づき話しかけてみようと思う。
・困ったときにこまらない、「大丈夫だよ」と言い合える地域に。
NPO法人青少年就労支援支援ネットワーク静岡 https://www.sssns.org/
〇パネルディスカッション「子ども・若者、保護者の味方!地域支援を繋ぐために」
会場からの質問「自立とは?どう生きていけば、暮らしていけばいいのか?幸せなのか?」への回答
内山:何が自立なのかは難しい。自立=幸せか?人が押し付けるものではない。対話しながら、子どもが身に着けていくもの。
多様性のある生き方について、議論が必要でなないか。学芸会など、主人公をやりたい人でだけではないのは?やりたい役、やりたいこと、幼児期から選択できることが大切。
池田:新卒で就職が当たり前、「みんな同じから個性へと言われても困る」と若者が声を出してくれた。選択ができること、一人でなく、頼れる人と繋がる。
<会場の参加者の皆様へひとことメッセージ>
内山:その人にとって大切なものは何か?自分がその人の人生に入るべきではなく、その人の人生の選択を支援すればいいと思っている。「子どもが働かなくて心配」と思っていても、何も動いていない人はいない。考えて準備をしている。
池田:出会えたことは、いいタイミングだったと思っている。考える時間、余裕がある人が、訪れている。本人、支援者が頑張ればいいのではなく、気持ちの共有、一緒に頑張ることが大切。
大山(子ども育ちレスキューネット代表)
周囲は自分で気づく、チャンス、きっかけをつくる。推測する、向き合う、対話をすることを大切にする。



今回の講演の開催主旨は、昨年10月に文部科学省が通知した「不登校生生徒への支援の在り方」で、不登校児童生徒支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標とすることを目指すのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があること」と明確化されたことにありました。
当会で開催している「不登校生のための進路相談会」(昨年まで「不登校生のための進学相談会」)においても、ほとんどの参加者は子どもの将来への不安、心配が尽きない状況から、「社会的自立」を目指すうえで必要とされている「対人関係」と「キャリア教育」についての講演会を開催することにしました。
講師の内山さん、池田さんからは、不登校であることや障がいの有無に関係なく、選択をする権利は「子ども本人」、本人も保護者も関わっている支援者もひとりで頑張らない、本人も家族も楽しく過ごすことと、共通したお話がありました。
これは、当会でも相談会でいつも伝えていることです。
簡単に、講演内容についてまとめますが、講演会については、後日YouTubeで配信予定です。配信が決まりましたらお知らせしますので。是非、ご覧になってください。
講演①「自分らしく生きよう」-子供の特性を理解していくためにー
浜松発達相談支援センタールピロ 所長 内山敏さん
・ルピロの相談は、乳幼時から大人まで、診断前の相談が92%、主訴や背景は様々。
学齢期前から成人まで、問題は積み重ねられて、複雑になってくる。
・子どもの発言に嫌な気持ちをしたら、冷静に怒らずそのこと伝える、パニックや大声を出したりしたら、言い聞かせるのでなく、別の場所で冷静な口調で話しかける、言葉でわからないときは、絵や図をみせたり、やってみせるとわかりやすい。
・パニックの誘因となるなんらかの感覚異常があると思われることは多い。生活のわずらわしさに対して対処することができる、克服させるものではない。
・発達障がいについて、ラベリングで終わるのは、対処ではない。対応については、個別性が強い。
・子どもは、周りの期待に気づいている、必ずしも本音を言わない、返事をしなくても謝れなくても言われたことはわかっているけど、大人は「わかっているか?」と返事を聞きたい。
・社会的自立の要件(障がいの有無に関わらず)
試行錯誤して自分で摘み取るが、「自分らしく生きること」につながるのでは?
1)身辺の自立 2)基本的なコミュニケーション 3)危険の認識と回避 4)金銭管理 5)生きがいを見つける 6)家族・友人と楽しむ
・自分らしさを生きるを構成するもの
1)支援は「与えられる恩恵」ではなく、「選択の権利」 2)支援は治療やリハビリや指導で完成させるものではなく、さらに怠けや弱さを克服させることでもなく、本人の「有効な選択肢」を増やすこと。平等に、大人が選びやすい情報の提供をする
浜松発達相談支援センタールピロ https://www.rupiro.com/
講演②「自立するためのきっかけをつくろう」-地域の支援に繋がろうー
NPO法人青少年就労支援支援ネットワーク静岡 事務局長 池田佳寿子さん
・働きたいけど働けない人びとに対して、市民ネットワークによる伴走型の就労支援を提供することを通じて、働く喜びを分かち合える、相互扶助の社会をつくることを目的としている。コロナ禍で、失業する人、仕事がなくなる人が増えている。誰にも起こること。
・IPS(Individual Placement and Support)就労支援プログラムの「クライアントの好みを重視する。サービスの提供は、プロバイダーの判断より、クライアントの好みと選択に基づいている」こと、本人の信頼を原則とする。
・「静岡方式」が、地域を大切にしている理由。「困っている人」ほど自ら働くことが困難で、相談窓口に赴くことが難しい。地域の民生委員や自治会の方など、地域のつながりを通して出会う。行政の制度や市場からこぼれる人々を。互助の原理で再組織化して生活しやすくする。隙間に陥る人々を、制度で埋めるのではなく、地域で支える。不可視化された困りことを中心に地域をつくる。
県内に16000人超のボランティア、西部地区は約530名がいる。地域若者サポートステーション事業、学習支援・生活支援事業、引きこもり支援事業等。
・何をもって「自立」と言うのか。社会的養護を受けた方の答えは、「情報が取れる」「選択肢.がある」「喜怒哀楽が出せる」など、子どもの考えは大人の考えの自立の手前にある。
・私たちは人を支えない、支えを外してしまえば落ちてしまう。本人の人生はあくまで、本人のもの、本人の人生を送るものを「応援する」応援団。
・ウィークタイズ(弱い紐帯)の強み。ごちゃ混ぜは状況により、「支えるとき」「支えられるとき」、支える側・支える側でない、誰もが応援可能。
・好きなこと、好きなもの、好きなひと、「ストレングス」で、縁を増やし、運に出会うこと、運を縁に変えて、繋がろう。
・これからできること。 ◇みんなの原則 1)過去でなく、未来を見る、問題でなく強みをみる。 2)自分が変わる(他人を変えようとしない)・変わるために人から助けてもらう 3)小さな変化を起こす、変化に気づく、日常なことを大切にする。
◇応援する人ができること 1)焦らない、無理しない、無理をすると本人を責めたくなる。 2)話すこと、仲間を作る。
◇本人ができること 1)「自分ほめ」上手になる 2)嫌な経験も失敗も大切 3)自分に得な考えをする 4)自分にない考えや選択肢を手に入れる 5)身近な人から、どんどんはなしてみる 6)素直になる、騙され得意になる。
・母子面接での場面、母親はイライラしている、「自分が何とかしなくては」と思ってしまう。母親が楽しそうだと、本人も気づき話しかけてみようと思う。
・困ったときにこまらない、「大丈夫だよ」と言い合える地域に。
NPO法人青少年就労支援支援ネットワーク静岡 https://www.sssns.org/
〇パネルディスカッション「子ども・若者、保護者の味方!地域支援を繋ぐために」
会場からの質問「自立とは?どう生きていけば、暮らしていけばいいのか?幸せなのか?」への回答
内山:何が自立なのかは難しい。自立=幸せか?人が押し付けるものではない。対話しながら、子どもが身に着けていくもの。
多様性のある生き方について、議論が必要でなないか。学芸会など、主人公をやりたい人でだけではないのは?やりたい役、やりたいこと、幼児期から選択できることが大切。
池田:新卒で就職が当たり前、「みんな同じから個性へと言われても困る」と若者が声を出してくれた。選択ができること、一人でなく、頼れる人と繋がる。
<会場の参加者の皆様へひとことメッセージ>
内山:その人にとって大切なものは何か?自分がその人の人生に入るべきではなく、その人の人生の選択を支援すればいいと思っている。「子どもが働かなくて心配」と思っていても、何も動いていない人はいない。考えて準備をしている。
池田:出会えたことは、いいタイミングだったと思っている。考える時間、余裕がある人が、訪れている。本人、支援者が頑張ればいいのではなく、気持ちの共有、一緒に頑張ることが大切。
大山(子ども育ちレスキューネット代表)
周囲は自分で気づく、チャンス、きっかけをつくる。推測する、向き合う、対話をすることを大切にする。



2020年07月30日
第2回「2020 不登校生のための進路相談会」を開催しました。
7月19日、第2回「2020 不登校生のための進路相談会」を開催しました。
16名の参加者があり、今回は、小学生、中2、高校生の不登校生の相談と幅広い参加者があり、磐田市、袋井市からの参加者がありました。
前回と同様に、 新型コロナウイルスの感染予防対策を行いながらの相談会の開催で、ネット配信も行いました。
体験談を話してくれたYくんへの質問や個別面談時間に話を聞いている参加者の方もいらして、親と子どもにとって不登校の情報が充分ではなく、相談会の開催の意義を感じています。
今回の体験談は、中1の6月から、不登校。中2からフリースクールに通い、大平台高校定時制を4年で卒業、大学を卒業し4月から社会人になったYさん。大学在学中も体験談を話してくれましたが、今回は社会人になってからの体験も話してくれました。
Q社会人になって、仕事はどう?
A.大変調子よく、やらせてもらっている。あんまりおもしろくなないけど、楽しくやっている(笑い)
Qどんな、仕事?
A.ウエーブエンジニアの仕事。入社して、3カ月はリモートで仕事、7月から出社して仕事をしている。
Q中1で不登校になったときの気持ちは?
A.中1の冬から、不登校。「過敏性胃腸症候群」でいつもお腹が痛くてお腹を押さえていた。体調的にも悪かったけど、いまよりずっと気持ち的には悪かった。
Qそんな中でも、高校進学のことは考えていた?
A.本当に行けたらいいなと考えていたか、怪しい。本当は、行きたくないと考えていたレベル。
Qフリースクールに来たのは、中2の夏だった?もともと明るい、元気が子だったので、いつも楽しく遊んでいたよね
A.はい、中2から通って、よく遊んだ!
Q.中央高校通信制の選択もあったけど、大平台高校を決めた、決め手は?
A.大平台高校の学校見学にいって、トイレがきれいだった事、個室が広い、自動点灯で、トイレがよくて選んだ。
Q.当時は、受験科目は3日科目だった?
A.いまは、5科目だけど、3科目のラスト2年の年だった。
メンバー西村より
大平台定時制の受験科目は、全日制と同じ5科目と面接がある。学科試験は、全日制と同じレベルでできないといけないことはなく、学科試験ができなくて受からないことはない。面接重視なので「中学校はいけなかったけど、高校では頑張りたい」と意欲を示すことができればたぶん大丈夫です。面接は、個人面接と集団面接がある。
出席日数も関係ない。学校見学も受け入れています。
Q.面接では、何を聞かれたことは覚えている?
A.就活の面接でも聞かれたことがない「自由とはなにか?」ということは、覚えている。
「人に迷惑をかけない、うちで好きなことをやるのが自由だと思います」と答えたと思う。教師2人か3人に生徒5人の集団面接で、一番最初に挙手して答えたのが良かったのかなと思う。
Q.高校に入って、夏休みの前くらいから張り切りすぎて体調が悪くなって学校に行けなくなったことがあったけど、その頃のときは?
A.大平台高校定時制は、1から3部に分かれていて、1部は8:40からで朝が強い人、2部は10:40分から、3部は夜、他部履修して3年で卒業を最初は目指していけど、疲れちゃって、お腹が痛くなって、フリースクールに戻った。フリースクールで、よく遊んで、翌年4月から復学して、1年生のときはほとんど行けなくて、2.3.年は自分のペースを掴み、4年通って卒業した。2年生に戻年って半年以上してから、コンビニでバイトもした。
Q.大学はAO入試?
A.プレゼンと簡単な筆記試験で入学した。。
Q.進路については、高校在学中に考えていた?
A.自分では、これをやりたいとは考えていなかった。高校は農業、介護、情報とか、いろんな授業があって、一番楽しいと受けていたのが情報の授業。大学に情報科があったので、受験した。。
Q.大平台高校は、授業もたくさん面白い科目があるけど、生徒も国際色豊かで、見た目派手な子も、ヤンキーな子もいるけど、いじめはないと聞いている。Y 君がヤンキーの子にプールで助けられた出来事があるよね。
A.毎年、話してますね(笑い)
ブールの授業で、準備運動をしていたのに足がつって、溺れたところを、ヤンキーの友達に助けてもらった良い思い出がある。
いじめは、みたことがない。
Q.大平台高校は、学食がおいしい?
A学食がおいしいところがお勧め。
また弁当だけ食べにいきたい。
Q 参加者へのアドバイスをお願いします
A.大学が一番楽しかったという話を知人から聞くけど、僕は大平台高校が一番たのしかった。まずは、見学だけでも行ってみてください。ご飯が本当においしいので、ご飯につられていくのもお勧めだと思います。
大平台高校は、勉強ができなくても行ける高校なので、分数できない子でも通っていました。お勧めの高校です。
Q いまのYくんをみて、不登校だったと思うことはないと思う。不登校で家にいたり、フリースクールで、遊んだ時期があったけど、必要だったと思う?
A中学、高校とさんざん遊んだ。大学では、真面目に授業を受けて、成績もまあまあ良くて、卒業式で送辞をやった。
楽しい時期があったから、頑張れた。
〇会場からの質問
Q不登校のとき、親はどんな対応をしていましたか?
A.フリースクール入る前までは、最初の頃は触れずに、フリースクールに入る頃は、こんなことあるけど、どう?と言ってきた。フリースクール入ってからは、働きかけはなかったけど、
高校入試のときは、結構圧力があった。家族とは、旅行に行ったり仲はいいです。
Q不登校の原因は?
A.真面目な性格で、部活が終わってから、塾に行くのが大変だった。体調が悪くなった。
次回の相談会は、10月25日(日)13:30~ 「ワークピア磐田」。11月29日(日)13:30~「アイミティ浜松、」になります。
個別相談は、いつでも受け付けます。
子ども育ちレスキューネットのこれからの予定
〇10月3日(土)13:30~15:30 浜北文化センター
静岡県合同相談会(ニート・ひきこもり・不登校等の子ども・若者を支援する相談機関・支援機関、就労支援団体、通信制・定時制高等学校、サポート校、長期欠席生徒選抜実施の県立高等学校等がブースを設置して無料で個別相談に応じる)に参加します。
https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080/soudannkai/goudousoudannkai.html
〇10月11日(日)13:00~16:30
「自分らしく生きる、自立するための、きっかけをつくろう!」講演会
相談会、講演会は、参加予約申し込み、マスク着用、手指のアルコール消毒、健康チャックアンケート等のご協力をお願いします。


16名の参加者があり、今回は、小学生、中2、高校生の不登校生の相談と幅広い参加者があり、磐田市、袋井市からの参加者がありました。
前回と同様に、 新型コロナウイルスの感染予防対策を行いながらの相談会の開催で、ネット配信も行いました。
体験談を話してくれたYくんへの質問や個別面談時間に話を聞いている参加者の方もいらして、親と子どもにとって不登校の情報が充分ではなく、相談会の開催の意義を感じています。
今回の体験談は、中1の6月から、不登校。中2からフリースクールに通い、大平台高校定時制を4年で卒業、大学を卒業し4月から社会人になったYさん。大学在学中も体験談を話してくれましたが、今回は社会人になってからの体験も話してくれました。
Q社会人になって、仕事はどう?
A.大変調子よく、やらせてもらっている。あんまりおもしろくなないけど、楽しくやっている(笑い)
Qどんな、仕事?
A.ウエーブエンジニアの仕事。入社して、3カ月はリモートで仕事、7月から出社して仕事をしている。
Q中1で不登校になったときの気持ちは?
A.中1の冬から、不登校。「過敏性胃腸症候群」でいつもお腹が痛くてお腹を押さえていた。体調的にも悪かったけど、いまよりずっと気持ち的には悪かった。
Qそんな中でも、高校進学のことは考えていた?
A.本当に行けたらいいなと考えていたか、怪しい。本当は、行きたくないと考えていたレベル。
Qフリースクールに来たのは、中2の夏だった?もともと明るい、元気が子だったので、いつも楽しく遊んでいたよね
A.はい、中2から通って、よく遊んだ!
Q.中央高校通信制の選択もあったけど、大平台高校を決めた、決め手は?
A.大平台高校の学校見学にいって、トイレがきれいだった事、個室が広い、自動点灯で、トイレがよくて選んだ。
Q.当時は、受験科目は3日科目だった?
A.いまは、5科目だけど、3科目のラスト2年の年だった。
メンバー西村より
大平台定時制の受験科目は、全日制と同じ5科目と面接がある。学科試験は、全日制と同じレベルでできないといけないことはなく、学科試験ができなくて受からないことはない。面接重視なので「中学校はいけなかったけど、高校では頑張りたい」と意欲を示すことができればたぶん大丈夫です。面接は、個人面接と集団面接がある。
出席日数も関係ない。学校見学も受け入れています。
Q.面接では、何を聞かれたことは覚えている?
A.就活の面接でも聞かれたことがない「自由とはなにか?」ということは、覚えている。
「人に迷惑をかけない、うちで好きなことをやるのが自由だと思います」と答えたと思う。教師2人か3人に生徒5人の集団面接で、一番最初に挙手して答えたのが良かったのかなと思う。
Q.高校に入って、夏休みの前くらいから張り切りすぎて体調が悪くなって学校に行けなくなったことがあったけど、その頃のときは?
A.大平台高校定時制は、1から3部に分かれていて、1部は8:40からで朝が強い人、2部は10:40分から、3部は夜、他部履修して3年で卒業を最初は目指していけど、疲れちゃって、お腹が痛くなって、フリースクールに戻った。フリースクールで、よく遊んで、翌年4月から復学して、1年生のときはほとんど行けなくて、2.3.年は自分のペースを掴み、4年通って卒業した。2年生に戻年って半年以上してから、コンビニでバイトもした。
Q.大学はAO入試?
A.プレゼンと簡単な筆記試験で入学した。。
Q.進路については、高校在学中に考えていた?
A.自分では、これをやりたいとは考えていなかった。高校は農業、介護、情報とか、いろんな授業があって、一番楽しいと受けていたのが情報の授業。大学に情報科があったので、受験した。。
Q.大平台高校は、授業もたくさん面白い科目があるけど、生徒も国際色豊かで、見た目派手な子も、ヤンキーな子もいるけど、いじめはないと聞いている。Y 君がヤンキーの子にプールで助けられた出来事があるよね。
A.毎年、話してますね(笑い)
ブールの授業で、準備運動をしていたのに足がつって、溺れたところを、ヤンキーの友達に助けてもらった良い思い出がある。
いじめは、みたことがない。
Q.大平台高校は、学食がおいしい?
A学食がおいしいところがお勧め。
また弁当だけ食べにいきたい。
Q 参加者へのアドバイスをお願いします
A.大学が一番楽しかったという話を知人から聞くけど、僕は大平台高校が一番たのしかった。まずは、見学だけでも行ってみてください。ご飯が本当においしいので、ご飯につられていくのもお勧めだと思います。
大平台高校は、勉強ができなくても行ける高校なので、分数できない子でも通っていました。お勧めの高校です。
Q いまのYくんをみて、不登校だったと思うことはないと思う。不登校で家にいたり、フリースクールで、遊んだ時期があったけど、必要だったと思う?
A中学、高校とさんざん遊んだ。大学では、真面目に授業を受けて、成績もまあまあ良くて、卒業式で送辞をやった。
楽しい時期があったから、頑張れた。
〇会場からの質問
Q不登校のとき、親はどんな対応をしていましたか?
A.フリースクール入る前までは、最初の頃は触れずに、フリースクールに入る頃は、こんなことあるけど、どう?と言ってきた。フリースクール入ってからは、働きかけはなかったけど、
高校入試のときは、結構圧力があった。家族とは、旅行に行ったり仲はいいです。
Q不登校の原因は?
A.真面目な性格で、部活が終わってから、塾に行くのが大変だった。体調が悪くなった。
次回の相談会は、10月25日(日)13:30~ 「ワークピア磐田」。11月29日(日)13:30~「アイミティ浜松、」になります。
個別相談は、いつでも受け付けます。
子ども育ちレスキューネットのこれからの予定
〇10月3日(土)13:30~15:30 浜北文化センター
静岡県合同相談会(ニート・ひきこもり・不登校等の子ども・若者を支援する相談機関・支援機関、就労支援団体、通信制・定時制高等学校、サポート校、長期欠席生徒選抜実施の県立高等学校等がブースを設置して無料で個別相談に応じる)に参加します。
https://www.pref.shizuoka.jp/kyouiku/kk-080/soudannkai/goudousoudannkai.html
〇10月11日(日)13:00~16:30
「自分らしく生きる、自立するための、きっかけをつくろう!」講演会
相談会、講演会は、参加予約申し込み、マスク着用、手指のアルコール消毒、健康チャックアンケート等のご協力をお願いします。


2020年07月05日
第1回「2020 不登校生のための進路相談会」を開催しました
6月28日、第1回「2020 不登校生のための進路相談会」を開催しました。
14名(うち子ども2名)の参加者がありました。今回は、中2、中3の不登校生が対象の参加者がほとんどでした。
新型コロナウイルスの感染拡大で「休校になったときは、みんな不登校状態で安心した気持ちだった。学校が再開したら、登校できるかな?と思っていたけど、やっぱり行けなかった」というお話や「学校再開後に学校に行けなくなった」というケースがありました。
中学3年生の不登校生の保護者と子どもにとっては、いつもより高校受験の不安は大きいと感じました。
新型コロナウイルスの感染予防対策を行いながらの相談会の開催で、ネット配信も行いました。
次回も、同様に参加予約、マスク着用、手指のアルコール消毒、健康チャックアンケート等のご協力をお願いします。
子ども育ちレスキューネットのフェイスブックのページから、相談会のネット配信の予定です。
今回の体験談は、中1から不登校になりフリースクールに通って、4月に大平台高校定時制に入学したⅯさんとお母さんです。
最初は、Ⅿさんの体験談です。
Q 中1のときに、不登校を自分で決めてフリースクールにきたけど、どんな気持ちできた?
A つらい思いをして、学校にいきたくなかったから。
Q 主な理由は、部活だったかな?
A 部活のことで、先生からバカにされたので、行きたくなかった。
Q つらい思いをして学校にいけなくなったのに。そのあと学校に行って先生の話を聞いたら、先生方はそんなつらいとは思っていなくて、びっくりしてた。
静岡中央通信制か大平台定時制か、高校進学の選択で考えていたけど、大平台定時制に決めた理由は?
A 自分のペースに合う学校にしたかったから。
Q 見学に行っていいなと思ったのと、フリースクールの卒業生で大平台定時制にいった生徒の話を聞いたことが良かった?
中学校の先生は、入試の5教科をやらないとダメだそ言ったけど、卒業生や大平台定時制の校長先生や教頭先生に話を聞いたら、5教科の試験より面接が大事だと聞きました。でも、勉強も頑張って面接の練習もしたけど、受験はどうでした?
A フリースクールで公文の勉強をして、自主勉強をしたり頑張って、面接も不安だったけど練習をして、大丈夫だと思って受けることができた。
Q 入学して、すぐにコロナで休業になってしまたけど、学校が休業して再開して一か月ですが、どのように通っている?
A 休まずに、勉強に取り組んでいます。
Q 部活に、入った?
A 入りたいと思った部活があったけど、トラウマがあってあんまり入りたくないと気持ちがある。
Q 10時から14時くらいまでのⅡ部ですね。3年で卒業もできるけど、Ⅿさんは3年の予定ですか?
A. 4年の予定です。マイペースで、ゆっくり行きます。
Q. 学校は、どんな感じ?
A.友達と悩み事を相談しあえたり、笑わしてくる人がいて、自分の心が安らかになって通いやすい。
Q. 授業の様子や先生方は、どう?
A. 先生は、自分のことや他の人のこともわかってくれる人が多い。授業は、自分のペースに合ったところなので、とても通いやすい。
Q. フリースクールに通ってからも、悪夢をみて泣いてしまうことがあったけど、高校に通ってどう?
A. 高校に入ってからは、その夢を見ることもなく、楽しい学校生活を送っている。
Q. 経験から、今日の参加者へのアドバイスはある?
A. あります。自分の人生は自分が決めることだから、他人の評価と比べないこと。自分は、人と比べてしまうことがあるので、孤独な気持ちになることがあった。
そのことを、フリースクールで相談して、人と比べなくなった。そのとき、大きな試練を乗り越えて、自分で決めてフリスクールに入って楽しく通っていると思った。
次は、お母さんの体験談です。
Q. Ⅿさんが、学校に通えなくなった時、どんな対応をした?
A. 先のことを考えてしまって、すごく不安だった。ずっと家にいたらどうしようと思って、眠れない日が続いた。
Q. フリースクールに通っても楽しいことばかりでなく、将来の不安もあったけど、どんな形で家族で支えた?、
A. フリースクールのこと、考えていることを、きちんと聞いてあげよう、共感しようと思った。
Q. 高校進学について、本人の意思を優先していたが、大平台定時制はどこが合っていると思った?
A. 本人が行けそうだと思ったところ。友達をたくさん作りたいと聞いていたので、毎日通学できそうと言っていたので、行ってみたらと思った。
Q. お母さんがPTA役員を引き受けてくれたと聞いた。学校の雰囲気とかⅯさんの様子は、どう?
A. まだよくわからないけど、話では個性的な子が多いけど、先生方も個性を認めている感じ。Ⅿも、、毎日落ち着いて学校に通っているので、雰囲気的には良いのかと思うけど、まだよくわからない。。
Q 今日の参加者の保護者の方に、親としての経験からのサポートについてありますか?
Aフリースクールが居場所になったので、いろいろ体験したことに感謝している。子どもなりに、いろいろ考えているので、あまり口を出さない方が良いのかと思う。まだ、Ⅿといろいろ話しながらいる。これからも、楽しいこともつらいこともあると思うので、一緒に乗り越えようと思っている。
次回の相談会は、7月19日(日)13:30~ アイミティ浜松です。
※中日新聞と静岡新聞の取材があり、新聞に掲載されました。

14名(うち子ども2名)の参加者がありました。今回は、中2、中3の不登校生が対象の参加者がほとんどでした。
新型コロナウイルスの感染拡大で「休校になったときは、みんな不登校状態で安心した気持ちだった。学校が再開したら、登校できるかな?と思っていたけど、やっぱり行けなかった」というお話や「学校再開後に学校に行けなくなった」というケースがありました。
中学3年生の不登校生の保護者と子どもにとっては、いつもより高校受験の不安は大きいと感じました。
新型コロナウイルスの感染予防対策を行いながらの相談会の開催で、ネット配信も行いました。
次回も、同様に参加予約、マスク着用、手指のアルコール消毒、健康チャックアンケート等のご協力をお願いします。
子ども育ちレスキューネットのフェイスブックのページから、相談会のネット配信の予定です。
今回の体験談は、中1から不登校になりフリースクールに通って、4月に大平台高校定時制に入学したⅯさんとお母さんです。
最初は、Ⅿさんの体験談です。
Q 中1のときに、不登校を自分で決めてフリースクールにきたけど、どんな気持ちできた?
A つらい思いをして、学校にいきたくなかったから。
Q 主な理由は、部活だったかな?
A 部活のことで、先生からバカにされたので、行きたくなかった。
Q つらい思いをして学校にいけなくなったのに。そのあと学校に行って先生の話を聞いたら、先生方はそんなつらいとは思っていなくて、びっくりしてた。
静岡中央通信制か大平台定時制か、高校進学の選択で考えていたけど、大平台定時制に決めた理由は?
A 自分のペースに合う学校にしたかったから。
Q 見学に行っていいなと思ったのと、フリースクールの卒業生で大平台定時制にいった生徒の話を聞いたことが良かった?
中学校の先生は、入試の5教科をやらないとダメだそ言ったけど、卒業生や大平台定時制の校長先生や教頭先生に話を聞いたら、5教科の試験より面接が大事だと聞きました。でも、勉強も頑張って面接の練習もしたけど、受験はどうでした?
A フリースクールで公文の勉強をして、自主勉強をしたり頑張って、面接も不安だったけど練習をして、大丈夫だと思って受けることができた。
Q 入学して、すぐにコロナで休業になってしまたけど、学校が休業して再開して一か月ですが、どのように通っている?
A 休まずに、勉強に取り組んでいます。
Q 部活に、入った?
A 入りたいと思った部活があったけど、トラウマがあってあんまり入りたくないと気持ちがある。
Q 10時から14時くらいまでのⅡ部ですね。3年で卒業もできるけど、Ⅿさんは3年の予定ですか?
A. 4年の予定です。マイペースで、ゆっくり行きます。
Q. 学校は、どんな感じ?
A.友達と悩み事を相談しあえたり、笑わしてくる人がいて、自分の心が安らかになって通いやすい。
Q. 授業の様子や先生方は、どう?
A. 先生は、自分のことや他の人のこともわかってくれる人が多い。授業は、自分のペースに合ったところなので、とても通いやすい。
Q. フリースクールに通ってからも、悪夢をみて泣いてしまうことがあったけど、高校に通ってどう?
A. 高校に入ってからは、その夢を見ることもなく、楽しい学校生活を送っている。
Q. 経験から、今日の参加者へのアドバイスはある?
A. あります。自分の人生は自分が決めることだから、他人の評価と比べないこと。自分は、人と比べてしまうことがあるので、孤独な気持ちになることがあった。
そのことを、フリースクールで相談して、人と比べなくなった。そのとき、大きな試練を乗り越えて、自分で決めてフリスクールに入って楽しく通っていると思った。
次は、お母さんの体験談です。
Q. Ⅿさんが、学校に通えなくなった時、どんな対応をした?
A. 先のことを考えてしまって、すごく不安だった。ずっと家にいたらどうしようと思って、眠れない日が続いた。
Q. フリースクールに通っても楽しいことばかりでなく、将来の不安もあったけど、どんな形で家族で支えた?、
A. フリースクールのこと、考えていることを、きちんと聞いてあげよう、共感しようと思った。
Q. 高校進学について、本人の意思を優先していたが、大平台定時制はどこが合っていると思った?
A. 本人が行けそうだと思ったところ。友達をたくさん作りたいと聞いていたので、毎日通学できそうと言っていたので、行ってみたらと思った。
Q. お母さんがPTA役員を引き受けてくれたと聞いた。学校の雰囲気とかⅯさんの様子は、どう?
A. まだよくわからないけど、話では個性的な子が多いけど、先生方も個性を認めている感じ。Ⅿも、、毎日落ち着いて学校に通っているので、雰囲気的には良いのかと思うけど、まだよくわからない。。
Q 今日の参加者の保護者の方に、親としての経験からのサポートについてありますか?
Aフリースクールが居場所になったので、いろいろ体験したことに感謝している。子どもなりに、いろいろ考えているので、あまり口を出さない方が良いのかと思う。まだ、Ⅿといろいろ話しながらいる。これからも、楽しいこともつらいこともあると思うので、一緒に乗り越えようと思っている。
次回の相談会は、7月19日(日)13:30~ アイミティ浜松です。
※中日新聞と静岡新聞の取材があり、新聞に掲載されました。

2020年05月20日
2020不登校生の進路相談会&不登校生の社会的自立にむけた講演会を開催します
今年度の活動のお知らせです。
「不登校生のための進学相談会」は、不登校生の社会的自立に向けた情報提供を行う「不登校生のための進路相談会」に代わります。
また、今年は「不登校生の社会的自立」についての講演会を開催します。
新型コロナウ「イルスの感染が心配なところですが、感染予防対策を取り、開催することになりました。
感染拡大など、再び緊急事態宣言等がなされた場合は、中止になることがあるかもしれませんが、その際は個別相談等の受付を行います。
①「2020不登校生のための進路相談会」
「子どもが学校に行けてないけれど、高校に行けるのだろうか」「このままひきこもりになってしまうのではないか」「発達障害の子どもは、どうしたら社会的な自立ができるのか」、悩む保護者の皆さんに、「子ども育ちレスキューネット」は10年以上寄り添ってきました。
子どもたちを支援するネットワークである本団体では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などの情報提供、個別相談の場をつくってきました。今年度は、これまでに加えて、「社会的自立」に向けた地域のサポート情報もお伝えしていきます。 中学校で不登校を経験し、その後進学、就職した子どもや保護者の体験談も聞くこともできます。 どうぞ、お気軽にご参加ください。
〇内容
13:15~受付
13:30~15:00
・高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明、公立、私立高校の入試、入学後の受け入れ支援体制、義務教育卒業後の自立に向けた支援体制等の情報提供
・不登校を経験しその後進学、就職した子どもや保護者の体験談
・「社会的自立」に向けた地域サポート情報提供
15:00~16:00
不登校生に関する進路及びなんでも悩み個別相談
〇開催日と会場
6月28日、7月19日、11月29日
アイミティ浜松 浜松市中区船越町11-11 大会議室 TEL053-465-5065
10月25日
ワークピア磐田 磐田市国府台57-5 第3会議室 TEL0538-36-8381
〇希望者には、学習支援を行います(要個別相談)
②講演会
自分らしく生きる、自立するためのきっかけをつくろう!
子どもが不登校やニート、ひきこもりになったとき、「将来自立できるのだろうか?」と、保護者の不安や心配は尽きません。 将来の「社会的自立」を目指すうえで、必要とされている「対人関係」と「キャリア教育」について、不登校やひきこもり支援に関わっている方たちのお話をお伺いします。学歴や職業にとらわれず、子どもたちが自分らしく生きていけるために、好きなことや得意なことを伸ばす選択ができるためには、信頼できる人との繋がることが大切です。この講演がそのきっかけづくりになるよう企画しました。ぜひ、ご参加ください。
〇開催日時と会場
10月11日(日)13:00~16:30
浜松市市民協働センター ギャラリー
浜松市中区中央1丁目13-3 TEL053-457-2616
〇講演内容
1)「自分らしく生きよう」ー子どもの特性を理解していくためにー
浜松発達相談支援センタールピロ所長 内山敏さん
2)「自立するために、きっかけをつくろう」ー地域の支援に繋がろうー
NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡 事務局長 池田佳寿子さん
3)パネルディスカッション コーディネーター 鈴木恵さん(子ども育ちレスキューネット・浜松市議)
「子ども・若者、保護者の味方!地域支援を繋ぐために」
内山敏さん
池田佳寿子さん
大山浩司さん
(子ども育ちレスキューネット代表・NPO法人ドリームフィールド代表)
〇参加費等
参加費無料、なるべく予約申し込みをお願いします。定員50名
参加予約方法:e-mail child-rescue@memoad.jpまたは090-3936-5840(事務局服部)
②参加者氏名②連絡先③所属団体等 をお伝えください。
<相談会・講演会共通事項>
〇対象者
不登校生(中学・高校等)、高校中退者、引きこもりがちの若者とその保護者の皆さん、教育関係者、不登校支援に関心のある方
〇主催 子ども育ちレスキューネット
(西部地区の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
https://childrescuenet.hamazo.tv/
〇後援
浜松市・浜松市教育委員会・磐田市・磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社(予定)
・キリン福祉財団 助成金事業
〇新型コロナウイルス対策について
・参加者の人数を把握するために、参加申し込みをしてください。
当日の参加は、定員に達している場合はお断りさせていただくことがあります。
・体調のすぐれない方の参加は、ご遠慮ください。マスクの着用を、お願いします。
・会場では、健康チェック、アルコール消毒・換気等の感染対策防止を行いますので、ご協力をお願いします。
・感染拡大などによる状況に応じて、中止になる場合がありますので、Facebook・ブログで確認をお願いします。中止になった場合は、後日個別相談等の受付を行う予定です。
〇お問い合わせ・当日連絡先
090-3936-5840子ども育ちレスキューネット服部


「不登校生のための進学相談会」は、不登校生の社会的自立に向けた情報提供を行う「不登校生のための進路相談会」に代わります。
また、今年は「不登校生の社会的自立」についての講演会を開催します。
新型コロナウ「イルスの感染が心配なところですが、感染予防対策を取り、開催することになりました。
感染拡大など、再び緊急事態宣言等がなされた場合は、中止になることがあるかもしれませんが、その際は個別相談等の受付を行います。
①「2020不登校生のための進路相談会」
「子どもが学校に行けてないけれど、高校に行けるのだろうか」「このままひきこもりになってしまうのではないか」「発達障害の子どもは、どうしたら社会的な自立ができるのか」、悩む保護者の皆さんに、「子ども育ちレスキューネット」は10年以上寄り添ってきました。
子どもたちを支援するネットワークである本団体では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などの情報提供、個別相談の場をつくってきました。今年度は、これまでに加えて、「社会的自立」に向けた地域のサポート情報もお伝えしていきます。 中学校で不登校を経験し、その後進学、就職した子どもや保護者の体験談も聞くこともできます。 どうぞ、お気軽にご参加ください。
〇内容
13:15~受付
13:30~15:00
・高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明、公立、私立高校の入試、入学後の受け入れ支援体制、義務教育卒業後の自立に向けた支援体制等の情報提供
・不登校を経験しその後進学、就職した子どもや保護者の体験談
・「社会的自立」に向けた地域サポート情報提供
15:00~16:00
不登校生に関する進路及びなんでも悩み個別相談
〇開催日と会場
6月28日、7月19日、11月29日
アイミティ浜松 浜松市中区船越町11-11 大会議室 TEL053-465-5065
10月25日
ワークピア磐田 磐田市国府台57-5 第3会議室 TEL0538-36-8381
〇希望者には、学習支援を行います(要個別相談)
②講演会
自分らしく生きる、自立するためのきっかけをつくろう!
子どもが不登校やニート、ひきこもりになったとき、「将来自立できるのだろうか?」と、保護者の不安や心配は尽きません。 将来の「社会的自立」を目指すうえで、必要とされている「対人関係」と「キャリア教育」について、不登校やひきこもり支援に関わっている方たちのお話をお伺いします。学歴や職業にとらわれず、子どもたちが自分らしく生きていけるために、好きなことや得意なことを伸ばす選択ができるためには、信頼できる人との繋がることが大切です。この講演がそのきっかけづくりになるよう企画しました。ぜひ、ご参加ください。
〇開催日時と会場
10月11日(日)13:00~16:30
浜松市市民協働センター ギャラリー
浜松市中区中央1丁目13-3 TEL053-457-2616
〇講演内容
1)「自分らしく生きよう」ー子どもの特性を理解していくためにー
浜松発達相談支援センタールピロ所長 内山敏さん
2)「自立するために、きっかけをつくろう」ー地域の支援に繋がろうー
NPO法人青少年就労支援ネットワーク静岡 事務局長 池田佳寿子さん
3)パネルディスカッション コーディネーター 鈴木恵さん(子ども育ちレスキューネット・浜松市議)
「子ども・若者、保護者の味方!地域支援を繋ぐために」
内山敏さん
池田佳寿子さん
大山浩司さん
(子ども育ちレスキューネット代表・NPO法人ドリームフィールド代表)
〇参加費等
参加費無料、なるべく予約申し込みをお願いします。定員50名
参加予約方法:e-mail child-rescue@memoad.jpまたは090-3936-5840(事務局服部)
②参加者氏名②連絡先③所属団体等 をお伝えください。
<相談会・講演会共通事項>
〇対象者
不登校生(中学・高校等)、高校中退者、引きこもりがちの若者とその保護者の皆さん、教育関係者、不登校支援に関心のある方
〇主催 子ども育ちレスキューネット
(西部地区の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
https://childrescuenet.hamazo.tv/
〇後援
浜松市・浜松市教育委員会・磐田市・磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社(予定)
・キリン福祉財団 助成金事業
〇新型コロナウイルス対策について
・参加者の人数を把握するために、参加申し込みをしてください。
当日の参加は、定員に達している場合はお断りさせていただくことがあります。
・体調のすぐれない方の参加は、ご遠慮ください。マスクの着用を、お願いします。
・会場では、健康チェック、アルコール消毒・換気等の感染対策防止を行いますので、ご協力をお願いします。
・感染拡大などによる状況に応じて、中止になる場合がありますので、Facebook・ブログで確認をお願いします。中止になった場合は、後日個別相談等の受付を行う予定です。
〇お問い合わせ・当日連絡先
090-3936-5840子ども育ちレスキューネット服部


2020年03月22日
キリン福祉財団の助成金が決定しました!
子ども育ちレスキューネットの発足から、13年目になりました。
3月に入ってから、いままでの12年間の活動を振り返り、来年度4月からの事業内容について話し合いをしました。
その話し合いに合わせたかのように、申請していました「公益財団法人 キリン福祉財団」から「キリン・地域のちから応援事業」の助成金決定の連絡をいただきました。
今年の助成金授与式は、新コロナウイルスの影響を受け中止となってしまいましたが、通知書と一緒に「子ども育ちレスキューネットの活動が高く評価され情勢金が決定しました」と記載されている贈呈書が同封されていました。

振り返りから、来年度は、「不登校生のための進学相談会」を、「不登校生のための進路相談会」として、不登校生の「社会的自立」を伝える内容にしていくことになりました。
今まで通り、高校進学についての情報提供はしていきますが、進学や就職という形に捕らわれがちな保護者の不安を、「子どもが自立する」ために進路を考える内容にしていきます。高校不登校や中退後の選択肢や相談先について、相談会で渡している手引書に掲載していきます。
個別相談の他に、参加者同士のしゃべり場を設けようと考えています。
相談会開催は、進路指導が早く始まっているという情報から、初回開催を6月として例年通り年4回を予定します。
相談会の他に、「発達障がいと進路」「社会的自立」のついて、講演会を9月に開催する予定です。
相談会と講演会の開催については、決まり次第お知らせしていきます。
3月に入ってから、いままでの12年間の活動を振り返り、来年度4月からの事業内容について話し合いをしました。
その話し合いに合わせたかのように、申請していました「公益財団法人 キリン福祉財団」から「キリン・地域のちから応援事業」の助成金決定の連絡をいただきました。
今年の助成金授与式は、新コロナウイルスの影響を受け中止となってしまいましたが、通知書と一緒に「子ども育ちレスキューネットの活動が高く評価され情勢金が決定しました」と記載されている贈呈書が同封されていました。

振り返りから、来年度は、「不登校生のための進学相談会」を、「不登校生のための進路相談会」として、不登校生の「社会的自立」を伝える内容にしていくことになりました。
今まで通り、高校進学についての情報提供はしていきますが、進学や就職という形に捕らわれがちな保護者の不安を、「子どもが自立する」ために進路を考える内容にしていきます。高校不登校や中退後の選択肢や相談先について、相談会で渡している手引書に掲載していきます。
個別相談の他に、参加者同士のしゃべり場を設けようと考えています。
相談会開催は、進路指導が早く始まっているという情報から、初回開催を6月として例年通り年4回を予定します。
相談会の他に、「発達障がいと進路」「社会的自立」のついて、講演会を9月に開催する予定です。
相談会と講演会の開催については、決まり次第お知らせしていきます。
2019年11月18日
「2019 不登校生のための進学相談会」が終わりました。
11月10日に開催しました「2019不登校生のための進学相談会」をもって、今年度の相談会が終了しました。
ここ数年は100名近かった参加者が、今年度の参加者は、41組57人(子ども6人)でしたが、学校関係者(教員、スクールカウンセラー)の参加や付き添いがあったり、不登校支援に関わる方の参加、青少年の支援に関わる機関から紹介で参加した方がありました。今年も新居高校定時制の先生が、参加してくださいました。
個別面談の時間には、以前には見られなかった様子の変化が、よく見られるようになりました。以前には、個別相談を希望されない参加者の方はすぐに帰ってしまい、個別相談が始まるとどうしても重苦しい空間になってしまっていましたが、数年前間から体験を話してくれた生徒さんが数名の参加者の方に囲まれて話をして時々笑い声が聞こえたり、定時制の先生に話しかけたり、個別相談を希望しない参加者の方と立ち話をしたり、相談が始まったりという光景が、よく見られるようになりました。相談の内容は、複雑なケースが増えていますが、参加者の方が積極的に情報を得ようという思いが伝わってきます。
参加者は、毎年、中学3年生の相談が一番多いのは変わりませんが、前もって情報を知りたいという中学1,2年生の相談、高校生の不登校相談がありました。今年度は障がいや不登校があると高校に進学するのは難しいと言われたという就学前や小学生の子どもさんが高校進学ができるかどうかという相談もありました。
支援を繋げようとするところでは、情報提供があって相談会に参加される方もいれば、まだまだ情報を持ち合わせていないところでは、不用意な発言があるのは残念でなりません。
昨年も参加していますという方や2回目に子ども一緒に参加される方などもありました。
相談会は、来年度も7月から開催の予定です。開催日時が決まり次第、ブログに更新します。
今回も新居高校定時制の中村先生に、定時制についてお話していただきました。
〇定時制ってどんなところ?
・定時制は、働いている生徒、やんちゃな生徒がいるイメージがあると思うが、正社員で働 いている生徒はいない。アルバイトをしている生徒は半分くらい。不登校だった生徒、外国籍の生徒が多く、経済的に困窮している家庭もある。授業中に騒ぐ生徒はいない。
・定時制の始まりが17時、終わりが21時、女子や通学距離が遠いと帰り時間が遅いので敬遠される。1学年の定員は40名、今年度は入学者が7名と少なかった。1学年一クラスしかないので、クラス替えができないので、人間関係によっては苦しくなるかも。
中退者は10%位いる。
・入試は、作文、面接のみ。成績は重要視されないので、調査票がオール1でも大丈夫。
入学してから、頑張ろうというアピールが大切。定員割れでも、面接で判断して不合格のなることがある。
・テストで点数が取れないと、補習や課題をだしてフォローする。進級するには、出席日数が2/3超えることが必要。
・制服はないが、式典時は正装をする。中学の制服でもOK。
・毎週、掛川市の地域若者サポートステーションの就労支援、相談を行っている。地域の企業や周囲の社会との協力がある。
在学中はアルバイト、卒業後は正社員へとサポートしている。昨年度は、帰国した一人を除いて、全員が就職したがアルバイトもいる。進学できない理由は、経済的なこともある。働いて進学し、その後に正社員を目指す生徒もいる。
・月に2回水曜日の放課後に、定時制カフェを開催。企業やボランティアの人との学校以外の人との触れ合いがあり、話をしたり、人に繋げている。いまは、ボードゲームを一緒に楽しんでいる。
・秋期の2次募集は、大平台定時制のみ。転入・編入は、遠方なら受けることもある。通学できなくなったら、3月まで在籍し、再入学か転入(学科試験あり)という方法がある。
今回の体験談は、中1から、不登校になって、フリースクールに通い、大平台高校定時制進学、現在2年生のKくんです。中学の時は、自分の気持ちを話すのは苦手だったそうですが、今回相談会で話すことを快諾してくれました。
Q:不登校になった時、どんなことを考えていたことはありましたか?
A:中学の時は、学校のことを考えたくなかった。未来のことは一切考えていなくて、いまどうしようと考えていた。
Q:今、高校に進学して話してもいいかなという感じかな?
A:正直、中学のことは口にしたくない。
Q:毎日、フリースクールに通って、ハンモックで熱心に漫画を読んでいたけど、良い感じで過ごしていた。高校進学の時、フリースクールに残って静岡中央高校通信制に通うという進路もあったけど、大平台定時制に進学したのはなぜ?
K:家が、自転車で15分と結構近かった。毎日通う、規則的な生活ができるので選んだ。規則がないと自堕落な生活を送ってしまいそうだったので、通学が向いていると思った。
Q:定時制の中で、大平台を選んだ理由は?
K:大学みたいな感じの雰囲気。授業の取り方も。ここだったら、自由な感じで通えそうと思ったので、ここにしよう決めた。。
Q:2年間ほぼ皆勤で、飲食店でバイトもしている聞いたけど?
K:去年の8月からなので1年以上続けてる。バイトしている方が多い。部活とバイトを両立している子もいる。
Q:Kくんは、何部に通っている?
K:Ⅰ部です。大平台は、朝は最初ホームルールから始まらなくて、いきなり授業から始まる。1時限目の授業が始まる8:45まで、授業の教室まで行って、4時限目が終わるのが12:30、そのあとホームルームと掃除をして、そのあと授業がない日は帰る。。
Ⅱ部は10:45から授業が始まって、2時間授業、ホームルーム、掃除、昼休みがあって、そのあと授業が2時間、終わるのは15:25分。。Ⅲ部は、夜間で17:00から。
Q;3年で卒業する他部履修を取っているいるけど、どんな感じ?
K;Ⅰ部のあと、5、6時間目の授業を取って、問題なければ卒業できます。
3年で卒業する子が多い。
基本的には、自分の履修科目は、ほとんど自分で考えることはないけど、3年で卒業する場合は、5,6時間目に取れる授業を考えて入れていく。授業する教室へ、時間までに生徒が勝手に移動する感じ。
Q:1年は必修科目が多いけど、2年以降は。選択科目が増えていくので、ホームルーの仲間ともバラバラだったりする?
K:2年までは、必修科目があり、3年は体育が1時限目にあるくらい、3年卒業の人はバラバラな感じ。授業によっては、2~3人の少人数のところもある。入学時のアンケートで、数学の苦手な人は基礎からやってくれたり、授業で公式とかやってくれるのでやりやすかった。
Q:先生方は、どう?
K:専門性が高い方が多い。生徒と気さくに話している先生もいる。
Q:全日制は制服を着用していて、定時制は私服なので見分けはつくし、職員室も保健室も別々だね?
K:校舎が別々なので、全日制と定時制の生徒がそう合うことはないし、購買で会うくらい。購買の前にあるテーブル席に、全日制優先席と定時制優先席があったりしている。。
購買は充実して美味しい。近くのスーパーで、お弁当を買ってくる人をみたことがない。
Q:冷暖房がないので、夏暑くて冬寒い?
K:校舎の向きもあって、特別教室はエアコンがついているけど、普通の教室は暑くて寒いのが難点かな。
Q:普通の高校にない授業がある。何か取っていた?
K:2年で生物とか3年で電子商取引を取った。1年の時は必修科目で「はなみどり」という授業で、いちごや大根を育てた。
Q:大平台に入って良かった?
K:結構楽しい。自分のクラスだけでなくて、授業とがごちゃになってやるので、他のクラスの人も知っているし、思ったより人の繋がりが多いけど、その分楽しかった。見た目派手な感じの人もいる。授業をさぼる人は、そのうち学校をやめていく。仲良くなれる人もいるので、大丈夫と思う。不登校だった生徒、外国籍の生徒もいる。いじめは聞いたことない。
Q:大学進学を目指しているということけど、学校で進学指導はある?
K:先生に相談すれば、わからないとところは教えてくれるけど、基本的は自分で塾などにいく。。
Q:参加者にアドバイスはありますか?
K:大平台定時制は基本的に留年はなく、単位を落としてもそのまま次の年次で取っている。単位を落とす理由は、欠席が1/3あると単位を落とすので休まないことが大事。試験は、面接が重視なので勉強ができなくても大丈夫だと思う。
Q:面接で聞かれたことは覚えている?
K:中学校時代、どんな感じだったか。作文に自己PRを書くと良い。
大平台高校と静岡中央高校通信制の学校説明会に日程が決まりました。
詳しくは、下記ホームページアドレスでご確認ください。
〇大平台高校定時制
http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsuohiradai-h/home.nsf/SearchHeaderView/%E5%85%A5%E8%A9%A6%E6%83%85%E5%A0%B1?OpenDocument&Category=%E5%85%A5%E8%A9%A6%E6%83%85%E5%A0%B1
〇静岡中高校通信制
入試情報の学校案内の一番最後のページに掲載。西部地区の方は。西部キャンパスがお近くです。
http://shizuokachuo-h.sakura.ne.jp/top/入試情報/?action=common_download_main&upload_id=847
ここ数年は100名近かった参加者が、今年度の参加者は、41組57人(子ども6人)でしたが、学校関係者(教員、スクールカウンセラー)の参加や付き添いがあったり、不登校支援に関わる方の参加、青少年の支援に関わる機関から紹介で参加した方がありました。今年も新居高校定時制の先生が、参加してくださいました。
個別面談の時間には、以前には見られなかった様子の変化が、よく見られるようになりました。以前には、個別相談を希望されない参加者の方はすぐに帰ってしまい、個別相談が始まるとどうしても重苦しい空間になってしまっていましたが、数年前間から体験を話してくれた生徒さんが数名の参加者の方に囲まれて話をして時々笑い声が聞こえたり、定時制の先生に話しかけたり、個別相談を希望しない参加者の方と立ち話をしたり、相談が始まったりという光景が、よく見られるようになりました。相談の内容は、複雑なケースが増えていますが、参加者の方が積極的に情報を得ようという思いが伝わってきます。
参加者は、毎年、中学3年生の相談が一番多いのは変わりませんが、前もって情報を知りたいという中学1,2年生の相談、高校生の不登校相談がありました。今年度は障がいや不登校があると高校に進学するのは難しいと言われたという就学前や小学生の子どもさんが高校進学ができるかどうかという相談もありました。
支援を繋げようとするところでは、情報提供があって相談会に参加される方もいれば、まだまだ情報を持ち合わせていないところでは、不用意な発言があるのは残念でなりません。
昨年も参加していますという方や2回目に子ども一緒に参加される方などもありました。
相談会は、来年度も7月から開催の予定です。開催日時が決まり次第、ブログに更新します。
今回も新居高校定時制の中村先生に、定時制についてお話していただきました。
〇定時制ってどんなところ?
・定時制は、働いている生徒、やんちゃな生徒がいるイメージがあると思うが、正社員で働 いている生徒はいない。アルバイトをしている生徒は半分くらい。不登校だった生徒、外国籍の生徒が多く、経済的に困窮している家庭もある。授業中に騒ぐ生徒はいない。
・定時制の始まりが17時、終わりが21時、女子や通学距離が遠いと帰り時間が遅いので敬遠される。1学年の定員は40名、今年度は入学者が7名と少なかった。1学年一クラスしかないので、クラス替えができないので、人間関係によっては苦しくなるかも。
中退者は10%位いる。
・入試は、作文、面接のみ。成績は重要視されないので、調査票がオール1でも大丈夫。
入学してから、頑張ろうというアピールが大切。定員割れでも、面接で判断して不合格のなることがある。
・テストで点数が取れないと、補習や課題をだしてフォローする。進級するには、出席日数が2/3超えることが必要。
・制服はないが、式典時は正装をする。中学の制服でもOK。
・毎週、掛川市の地域若者サポートステーションの就労支援、相談を行っている。地域の企業や周囲の社会との協力がある。
在学中はアルバイト、卒業後は正社員へとサポートしている。昨年度は、帰国した一人を除いて、全員が就職したがアルバイトもいる。進学できない理由は、経済的なこともある。働いて進学し、その後に正社員を目指す生徒もいる。
・月に2回水曜日の放課後に、定時制カフェを開催。企業やボランティアの人との学校以外の人との触れ合いがあり、話をしたり、人に繋げている。いまは、ボードゲームを一緒に楽しんでいる。
・秋期の2次募集は、大平台定時制のみ。転入・編入は、遠方なら受けることもある。通学できなくなったら、3月まで在籍し、再入学か転入(学科試験あり)という方法がある。
今回の体験談は、中1から、不登校になって、フリースクールに通い、大平台高校定時制進学、現在2年生のKくんです。中学の時は、自分の気持ちを話すのは苦手だったそうですが、今回相談会で話すことを快諾してくれました。
Q:不登校になった時、どんなことを考えていたことはありましたか?
A:中学の時は、学校のことを考えたくなかった。未来のことは一切考えていなくて、いまどうしようと考えていた。
Q:今、高校に進学して話してもいいかなという感じかな?
A:正直、中学のことは口にしたくない。
Q:毎日、フリースクールに通って、ハンモックで熱心に漫画を読んでいたけど、良い感じで過ごしていた。高校進学の時、フリースクールに残って静岡中央高校通信制に通うという進路もあったけど、大平台定時制に進学したのはなぜ?
K:家が、自転車で15分と結構近かった。毎日通う、規則的な生活ができるので選んだ。規則がないと自堕落な生活を送ってしまいそうだったので、通学が向いていると思った。
Q:定時制の中で、大平台を選んだ理由は?
K:大学みたいな感じの雰囲気。授業の取り方も。ここだったら、自由な感じで通えそうと思ったので、ここにしよう決めた。。
Q:2年間ほぼ皆勤で、飲食店でバイトもしている聞いたけど?
K:去年の8月からなので1年以上続けてる。バイトしている方が多い。部活とバイトを両立している子もいる。
Q:Kくんは、何部に通っている?
K:Ⅰ部です。大平台は、朝は最初ホームルールから始まらなくて、いきなり授業から始まる。1時限目の授業が始まる8:45まで、授業の教室まで行って、4時限目が終わるのが12:30、そのあとホームルームと掃除をして、そのあと授業がない日は帰る。。
Ⅱ部は10:45から授業が始まって、2時間授業、ホームルーム、掃除、昼休みがあって、そのあと授業が2時間、終わるのは15:25分。。Ⅲ部は、夜間で17:00から。
Q;3年で卒業する他部履修を取っているいるけど、どんな感じ?
K;Ⅰ部のあと、5、6時間目の授業を取って、問題なければ卒業できます。
3年で卒業する子が多い。
基本的には、自分の履修科目は、ほとんど自分で考えることはないけど、3年で卒業する場合は、5,6時間目に取れる授業を考えて入れていく。授業する教室へ、時間までに生徒が勝手に移動する感じ。
Q:1年は必修科目が多いけど、2年以降は。選択科目が増えていくので、ホームルーの仲間ともバラバラだったりする?
K:2年までは、必修科目があり、3年は体育が1時限目にあるくらい、3年卒業の人はバラバラな感じ。授業によっては、2~3人の少人数のところもある。入学時のアンケートで、数学の苦手な人は基礎からやってくれたり、授業で公式とかやってくれるのでやりやすかった。
Q:先生方は、どう?
K:専門性が高い方が多い。生徒と気さくに話している先生もいる。
Q:全日制は制服を着用していて、定時制は私服なので見分けはつくし、職員室も保健室も別々だね?
K:校舎が別々なので、全日制と定時制の生徒がそう合うことはないし、購買で会うくらい。購買の前にあるテーブル席に、全日制優先席と定時制優先席があったりしている。。
購買は充実して美味しい。近くのスーパーで、お弁当を買ってくる人をみたことがない。
Q:冷暖房がないので、夏暑くて冬寒い?
K:校舎の向きもあって、特別教室はエアコンがついているけど、普通の教室は暑くて寒いのが難点かな。
Q:普通の高校にない授業がある。何か取っていた?
K:2年で生物とか3年で電子商取引を取った。1年の時は必修科目で「はなみどり」という授業で、いちごや大根を育てた。
Q:大平台に入って良かった?
K:結構楽しい。自分のクラスだけでなくて、授業とがごちゃになってやるので、他のクラスの人も知っているし、思ったより人の繋がりが多いけど、その分楽しかった。見た目派手な感じの人もいる。授業をさぼる人は、そのうち学校をやめていく。仲良くなれる人もいるので、大丈夫と思う。不登校だった生徒、外国籍の生徒もいる。いじめは聞いたことない。
Q:大学進学を目指しているということけど、学校で進学指導はある?
K:先生に相談すれば、わからないとところは教えてくれるけど、基本的は自分で塾などにいく。。
Q:参加者にアドバイスはありますか?
K:大平台定時制は基本的に留年はなく、単位を落としてもそのまま次の年次で取っている。単位を落とす理由は、欠席が1/3あると単位を落とすので休まないことが大事。試験は、面接が重視なので勉強ができなくても大丈夫だと思う。
Q:面接で聞かれたことは覚えている?
K:中学校時代、どんな感じだったか。作文に自己PRを書くと良い。
大平台高校と静岡中央高校通信制の学校説明会に日程が決まりました。
詳しくは、下記ホームページアドレスでご確認ください。
〇大平台高校定時制
http://www.edu.pref.shizuoka.jp/hamamatsuohiradai-h/home.nsf/SearchHeaderView/%E5%85%A5%E8%A9%A6%E6%83%85%E5%A0%B1?OpenDocument&Category=%E5%85%A5%E8%A9%A6%E6%83%85%E5%A0%B1
〇静岡中高校通信制
入試情報の学校案内の一番最後のページに掲載。西部地区の方は。西部キャンパスがお近くです。
http://shizuokachuo-h.sakura.ne.jp/top/入試情報/?action=common_download_main&upload_id=847
Posted by hiro at
01:15
│Comments(0)
2019年11月04日
第4回「2019不登校生のための進学相談会」を開催します・
今年度最後になります。
第4回「不登校生のための進学相談会」を、11月10日13:30から浜松市のアイミティ浜松で開催します。
「相談会」では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などについての情報提供するとともに、個別の相談にも対応します。
また、実際に不登校を経験して進学した方、不登校生の保護者の話を聞くことができます。
不登校生の中学3年生には、進路選択について焦りや不安が募る時期になっていることと思います。
どうぞ、お気軽にご参加ください。
開催月により、会場が変わっていますので、お間違えのないように確認をお願いします。
*2009年から開催。10年間で、610名378組(小中高生98名)の方が、参加しています。
◇日時
7月 6日(土)
9月14日(土)
10月 6日(日)
11月10日 (日)
13:30~16:00
◇相談会の日程と内容
13:15~ 受付
13:30 ~15:00 高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明
定時制・通信制高校で学んでいる生徒、学んだ人、不登校生の保護者の体験談
15:00 ~16:00 不登校生に関する進路およびなんでも悩み相談(個別)
◇対象
不登校生(中学、高校等)、高校中退者、引きこもりがちな若者と
その保護者の皆さん、教育関係者、不登校生の支援に関心のある方
◇参加費 無料、予約不要(途中参加可能です)
希望者には、無料で学習支援を行います(要個別相談)
◇会場
7月
ワークピア磐田
磐田市見付2898-3 TEL0538-37-8381)
9月、10月、11月
アイミティ浜松
浜松市中区船越町11-11 TEL053-465-5065
◇主催 子ども育ちレスキューネット
(静岡県西部の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
http://childrescuenet.hamazo.tv/
◇後援
浜松市 浜松市教育委員会 磐田市 磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社
◇お問い合わせ・当日連絡先
TEL/090-3936-5840(子ども育ちレスキューネット 服部)

第4回「不登校生のための進学相談会」を、11月10日13:30から浜松市のアイミティ浜松で開催します。
「相談会」では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などについての情報提供するとともに、個別の相談にも対応します。
また、実際に不登校を経験して進学した方、不登校生の保護者の話を聞くことができます。
不登校生の中学3年生には、進路選択について焦りや不安が募る時期になっていることと思います。
どうぞ、お気軽にご参加ください。
開催月により、会場が変わっていますので、お間違えのないように確認をお願いします。
*2009年から開催。10年間で、610名378組(小中高生98名)の方が、参加しています。
◇日時
9月14日(土)
10月 6日(日)
11月10日 (日)
13:30~16:00
◇相談会の日程と内容
13:15~ 受付
13:30 ~15:00 高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明
定時制・通信制高校で学んでいる生徒、学んだ人、不登校生の保護者の体験談
15:00 ~16:00 不登校生に関する進路およびなんでも悩み相談(個別)
◇対象
不登校生(中学、高校等)、高校中退者、引きこもりがちな若者と
その保護者の皆さん、教育関係者、不登校生の支援に関心のある方
◇参加費 無料、予約不要(途中参加可能です)
希望者には、無料で学習支援を行います(要個別相談)
◇会場
ワークピア磐田
磐田市見付2898-3 TEL0538-37-8381)
9月、10月、11月
アイミティ浜松
浜松市中区船越町11-11 TEL053-465-5065
◇主催 子ども育ちレスキューネット
(静岡県西部の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
http://childrescuenet.hamazo.tv/
◇後援
浜松市 浜松市教育委員会 磐田市 磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社
◇お問い合わせ・当日連絡先
TEL/090-3936-5840(子ども育ちレスキューネット 服部)

2019年10月09日
第3回「2019不登校生のための進学相談会」が終わりました
10月6日、「2019 不登校生のための進学相談会」の3回目が終わりました。
小学生から、高校生まで子どもさんの保護者 、7組11名、子ども1人の参加がありました。
今回は、新居高校定時制の先生が参加が参加してくだり、定時制のお話をきくことができました。今年の新しい情報を求めて2回目の参加者という方もいました。
個別相談の希望される方は少なかったのですが、学校情報の資料を見たりしながら話したり、少し声掛けをすると話されたりする方もいました。以前から考えていましたが、あらたまった相談というスタイルではなく、お茶を飲みながら話をするだけの場があっても良いのかと思っています。
〇定時制ってどんなところ?
新居高校定時制の中村先生のお話
・学校の始まりが17時、終わりが21時、女子には帰り時間が遅いので敬遠される。女子生徒は、全体の1/3。
1日の授業は、4時間。新居高校では、卒業まで76単位以上が必要になる。
勉強は難しくない、中学校からの復習から始める。登校ができない、欠席が多いと進級できない。
・定員は、1学年40名定員。卒業まで、1/3は中退している。少人数対応ができる。1学年は2クラス、2年以降は1クラスになる。
・不登校生の割合は、1/3。外国籍の生徒が1/3、なんらかの支援が必要な生徒は1/4(療育手帳を持っている生徒もいる)。
全日制で不登校生を受け入れるところはあるが支援体制が整っていない。定時制は、少人数なので対応しやすい。
・入試は、作文と面接。作文は、原稿用紙2枚、2枚目にかかればいいかな。面接は、高校で頑張りたいという気持が伝わることが大事。
成績は、問われない。
今回の体験談は、いままで何度も体験談を話してくれているMさん、24歳。
中2から不登校で、大平台定時制高校へ進学、化粧品販売の正社員と働いている。現在、1歳の子どものお母さん、4月より育児休暇が終わり職場復帰した。
Q.不登校になった理由は?
A. 中2の時クラス替えがあって、中1から気になっていたが、教室がうるさくて・・教室の空間、学校が合わなかった。
2年前に、私自身が発達障がいと診断されて、感覚過敏があったかもしれない。
中2から、保健室登校だったり、行かなかったりが多かった。中3から、立志舘という不登校生を対象にした塾で勉強したり、部活だけ行ったりしていた。部活だけいくことには、周わりの目は気になったが、うるさく言われなかった。
母が理解があったので、学校にいかない選択ができた。
Q.大平台定時制は、どんな学校?
A.定時制は、ヤンキーとか派手な子が多いと思っていたら、おとなしい子もいた。一人ひとり個性的で自由があって、ヤンキーとか派手な子もいるけど、悪いイメージがない。定時制では、友だちとの出会いがあり、いまも付き合っている。外国籍の子もいる。20歳過ぎの人もいて、50歳近くで仕事しながら働いている人がいた。
先生は優しくて、良い先生が多い。
Q.大平台定時制は4年間だけど、3年でも卒業できる?
A.Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部とあって、私はⅠ部の午前中だったけどⅡ部の午後の授業をとって、3年で卒業した。午後の授業は、クッキングとか自分の興味あるものをとった。花と緑という科目は、スイカやれんこんをビニールハウスで育てた。その他に、ポルトガル語、中国語、ダンスなどの授業があった。1,2年生の時は、頑張って授業にでて、3年生は少なめにして、私はバイトを頑張った。
Q.校則はある?
A.ない。ピアスOK。制服がないので、毎日服を考えるのが大変かな?ハロウィンの仮装できた子がいたが、教室を傷つけなけれなればOKと言われた。
Q.大人になって、発達障がいの診断を受けたきっかけは?
A.私はADHDと診断されたが、働くようになって少し前の記憶を記憶するのが苦手で、レジを打っているときに、お客さんと話しながらやると間違えたり、カードを渡すのを忘れることがあった。診断を受けようと思ったのは、作業に支障がでたから。ADHDの特徴と思い診断を受けた。中学の時に受診していたら、落ち込んでいてバイトもできなかったと思う。診断されていたら、できることが少なかったかも。病院選びは、大切。
Q.子どもが不登校になったら?
A.学校に行かせなくてもいいと思う。学校に通うのは、人生の中のほんのちょっとの間で、社会人の方が長い。社会人に必要なことを身に着けるなら、バイトでもいい。私立通信制高校を卒業した人が、職場の店長をしている。
Q参加者に伝えたいことは?
A.子どもを育てていて、不登校、発達障がいになったらと思うとつらい部分はある。でも、、私のようになってほしいと思うところもある。
親に、苦労かけたと思う。
学校がすべてではない。親が、焦らずにいてほしいと思う。
次回の相談会は、11月10日(日)13:30~会場は浜松市のアイミティ浜松です。

小学生から、高校生まで子どもさんの保護者 、7組11名、子ども1人の参加がありました。
今回は、新居高校定時制の先生が参加が参加してくだり、定時制のお話をきくことができました。今年の新しい情報を求めて2回目の参加者という方もいました。
個別相談の希望される方は少なかったのですが、学校情報の資料を見たりしながら話したり、少し声掛けをすると話されたりする方もいました。以前から考えていましたが、あらたまった相談というスタイルではなく、お茶を飲みながら話をするだけの場があっても良いのかと思っています。
〇定時制ってどんなところ?
新居高校定時制の中村先生のお話
・学校の始まりが17時、終わりが21時、女子には帰り時間が遅いので敬遠される。女子生徒は、全体の1/3。
1日の授業は、4時間。新居高校では、卒業まで76単位以上が必要になる。
勉強は難しくない、中学校からの復習から始める。登校ができない、欠席が多いと進級できない。
・定員は、1学年40名定員。卒業まで、1/3は中退している。少人数対応ができる。1学年は2クラス、2年以降は1クラスになる。
・不登校生の割合は、1/3。外国籍の生徒が1/3、なんらかの支援が必要な生徒は1/4(療育手帳を持っている生徒もいる)。
全日制で不登校生を受け入れるところはあるが支援体制が整っていない。定時制は、少人数なので対応しやすい。
・入試は、作文と面接。作文は、原稿用紙2枚、2枚目にかかればいいかな。面接は、高校で頑張りたいという気持が伝わることが大事。
成績は、問われない。
今回の体験談は、いままで何度も体験談を話してくれているMさん、24歳。
中2から不登校で、大平台定時制高校へ進学、化粧品販売の正社員と働いている。現在、1歳の子どものお母さん、4月より育児休暇が終わり職場復帰した。
Q.不登校になった理由は?
A. 中2の時クラス替えがあって、中1から気になっていたが、教室がうるさくて・・教室の空間、学校が合わなかった。
2年前に、私自身が発達障がいと診断されて、感覚過敏があったかもしれない。
中2から、保健室登校だったり、行かなかったりが多かった。中3から、立志舘という不登校生を対象にした塾で勉強したり、部活だけ行ったりしていた。部活だけいくことには、周わりの目は気になったが、うるさく言われなかった。
母が理解があったので、学校にいかない選択ができた。
Q.大平台定時制は、どんな学校?
A.定時制は、ヤンキーとか派手な子が多いと思っていたら、おとなしい子もいた。一人ひとり個性的で自由があって、ヤンキーとか派手な子もいるけど、悪いイメージがない。定時制では、友だちとの出会いがあり、いまも付き合っている。外国籍の子もいる。20歳過ぎの人もいて、50歳近くで仕事しながら働いている人がいた。
先生は優しくて、良い先生が多い。
Q.大平台定時制は4年間だけど、3年でも卒業できる?
A.Ⅰ部、Ⅱ部、Ⅲ部とあって、私はⅠ部の午前中だったけどⅡ部の午後の授業をとって、3年で卒業した。午後の授業は、クッキングとか自分の興味あるものをとった。花と緑という科目は、スイカやれんこんをビニールハウスで育てた。その他に、ポルトガル語、中国語、ダンスなどの授業があった。1,2年生の時は、頑張って授業にでて、3年生は少なめにして、私はバイトを頑張った。
Q.校則はある?
A.ない。ピアスOK。制服がないので、毎日服を考えるのが大変かな?ハロウィンの仮装できた子がいたが、教室を傷つけなけれなればOKと言われた。
Q.大人になって、発達障がいの診断を受けたきっかけは?
A.私はADHDと診断されたが、働くようになって少し前の記憶を記憶するのが苦手で、レジを打っているときに、お客さんと話しながらやると間違えたり、カードを渡すのを忘れることがあった。診断を受けようと思ったのは、作業に支障がでたから。ADHDの特徴と思い診断を受けた。中学の時に受診していたら、落ち込んでいてバイトもできなかったと思う。診断されていたら、できることが少なかったかも。病院選びは、大切。
Q.子どもが不登校になったら?
A.学校に行かせなくてもいいと思う。学校に通うのは、人生の中のほんのちょっとの間で、社会人の方が長い。社会人に必要なことを身に着けるなら、バイトでもいい。私立通信制高校を卒業した人が、職場の店長をしている。
Q参加者に伝えたいことは?
A.子どもを育てていて、不登校、発達障がいになったらと思うとつらい部分はある。でも、、私のようになってほしいと思うところもある。
親に、苦労かけたと思う。
学校がすべてではない。親が、焦らずにいてほしいと思う。
次回の相談会は、11月10日(日)13:30~会場は浜松市のアイミティ浜松です。

2019年09月19日
第2回「2019 不登校生のための進学相談会」が終わりました。
9月14日、「2019 不登校生のための進学相談会」の2回目が終わりました。
16組19名、子ども2人の参加がありました。
今回は、参加者に付き添ってくださった学校関係者の方の参加がありました。小学校入学前から高校進学は難しいと言われて悩まれて参加された方がありましたが、やはり中学3年生の参加が多数でした。2回目の参加という方もありました。
学校情報の提供は、参考になりましたという声を聞くことができ、個別相談の時間に、希望される参加者には体験談を話してくれたYくんに質問したり、話を聞く機会を設けましたが、とても好評でした。
今回の体験談は、中1の6月から、不登校。中3からフリースクールに通い、大平台高校定時制を4年で卒業、現在静岡理工科大学4年生のYさん。前回に続き、体験を話してくれました。
Q中1で不登校になった理由は?
A.体調的な問題もあったけど、やはり精神的な問題「どうしても、学校に行きたくない」という気持ちが強かった。どっちが先かは、自分でもわからない。どちらかというと、体調が悪くなって、学校に行きたくないと思ったのかな。
Q.大平台高校を決めた、決め手は?
A.静岡中央高校を先に見学して、大平台高校の学校見学にいった。大平台高校は、本当に校舎がきれいだった。こんなきれいな学校に通えるのかと思った。腹痛があってトイレに通うことが多かったので、トイレがきれいだった事、個室が広い、自動点灯で、トイレがよくて選んだ。
Q.当時は、受験科目は3日科目だった?
A.いまは、5科目だけど、3科目のラスト2年の年だった。
メンバー西村
大平台定時制の受験科目は、全日制と同じ5科目と面接がある。学科試験は、全日制と同じレベルでできないといけないことはなく、学力は重要視されない。面接重視と教頭先生がおしゃっていた。「中学校はいけなかったけど、高校では頑張りたい」と意欲を示すことができればたぶん大丈夫です。
Q.面接では、何を聞かれた?
A.8年前のことなので、よく覚えていないけど、ひとつ覚えているのは人生で一番意地悪な質問だと思っている「自由とはなにか?」という質問でした。それっぽい答えはしたと思うけど、覚えていない。あとは、趣味とか通常面接で聞かれる質問だったと思う。
メンバー西村
学校は、子ども達の緊張するのはわかっているので、自分の気持ちを一生懸命伝えるのが大事だと思う。
Q.高校に入って、バトミントン部の部活にも入って、大平台高校は楽しいよと話していたけれど、夏休みの前くらいから体調が悪くなって学校に行けなくなったんだよね。
A.自分が、朝が弱いことがわかった。
メンバー西村
大平台高校定時制は、1から3部に分かれていて、1部は8:40からで朝が強い人、2部は10:40分から、3部は夜。他部履修して3年で卒業を最初は目指していたが、Yさんは疲れちゃった。フリースクールに戻って、また4月から大平台高校に戻った。
4月から復学して、4年間で卒業した。2年生に戻って半年以上してから、コンビニでバイトもした。
Q.大学はAO入試で入って、大学は何を学んでいる?
A.9月にAO入試を受て入学した。情報学科で、プロミングだったり、経営とかマーケティング。情報をどう扱うかという勉強をしている。
Q.Yさんにとって、中学校不登校だったことは、プラスになっているのかマイナスになっている?
A.絶対、プラスになっている。不登校の時に遊んでなければ、こんなに大学で勉強しなかったと思う。大学に入って、やる気が出て、遊びって大事だと思う。
Q.大平台高校は、どんな学校生活だった?
A.制服がないので、学校にいくというより、友達に会いに行くという感じだった。本当に楽しかった。
学食がおいしいところがお勧め。前回からの新情報があって、他の学校の情報を聞いて比較すると、売店が充実していることがわかった。
Q.大学4年生で就職が決まり、どんな仕事をするの?
A.ウエーブサイトを作って、運営する仕事。
Q.ストレス弱いところがあると思うけど、仕事がきついと思ったら、自分でなんとか休むということができるかな?不登校経験があると、頑張りすぎないで休むことができると思うけど、これからもいろいろとあっても、なんとかやっていける?
A.いま研修に行ってるけど、上司に自分の弱いところをよく知っていると言われた。
Q不登校の時、苦しかったと思うけど、いま苦しい思いをしている不登校生に伝えたいことは?
A.自分の好きなことを見つける。ゲームとかでも、自分の集中できることを見つけてあげるとか。夢中になって一緒に遊べる友達とか、仲間とのつながりがが大事かな。
次回の相談会は、10月6日(日)13:30~会場は浜松市のアイミティ浜松です。
※中日新聞の取材を受け、掲載されました。

16組19名、子ども2人の参加がありました。
今回は、参加者に付き添ってくださった学校関係者の方の参加がありました。小学校入学前から高校進学は難しいと言われて悩まれて参加された方がありましたが、やはり中学3年生の参加が多数でした。2回目の参加という方もありました。
学校情報の提供は、参考になりましたという声を聞くことができ、個別相談の時間に、希望される参加者には体験談を話してくれたYくんに質問したり、話を聞く機会を設けましたが、とても好評でした。
今回の体験談は、中1の6月から、不登校。中3からフリースクールに通い、大平台高校定時制を4年で卒業、現在静岡理工科大学4年生のYさん。前回に続き、体験を話してくれました。
Q中1で不登校になった理由は?
A.体調的な問題もあったけど、やはり精神的な問題「どうしても、学校に行きたくない」という気持ちが強かった。どっちが先かは、自分でもわからない。どちらかというと、体調が悪くなって、学校に行きたくないと思ったのかな。
Q.大平台高校を決めた、決め手は?
A.静岡中央高校を先に見学して、大平台高校の学校見学にいった。大平台高校は、本当に校舎がきれいだった。こんなきれいな学校に通えるのかと思った。腹痛があってトイレに通うことが多かったので、トイレがきれいだった事、個室が広い、自動点灯で、トイレがよくて選んだ。
Q.当時は、受験科目は3日科目だった?
A.いまは、5科目だけど、3科目のラスト2年の年だった。
メンバー西村
大平台定時制の受験科目は、全日制と同じ5科目と面接がある。学科試験は、全日制と同じレベルでできないといけないことはなく、学力は重要視されない。面接重視と教頭先生がおしゃっていた。「中学校はいけなかったけど、高校では頑張りたい」と意欲を示すことができればたぶん大丈夫です。
Q.面接では、何を聞かれた?
A.8年前のことなので、よく覚えていないけど、ひとつ覚えているのは人生で一番意地悪な質問だと思っている「自由とはなにか?」という質問でした。それっぽい答えはしたと思うけど、覚えていない。あとは、趣味とか通常面接で聞かれる質問だったと思う。
メンバー西村
学校は、子ども達の緊張するのはわかっているので、自分の気持ちを一生懸命伝えるのが大事だと思う。
Q.高校に入って、バトミントン部の部活にも入って、大平台高校は楽しいよと話していたけれど、夏休みの前くらいから体調が悪くなって学校に行けなくなったんだよね。
A.自分が、朝が弱いことがわかった。
メンバー西村
大平台高校定時制は、1から3部に分かれていて、1部は8:40からで朝が強い人、2部は10:40分から、3部は夜。他部履修して3年で卒業を最初は目指していたが、Yさんは疲れちゃった。フリースクールに戻って、また4月から大平台高校に戻った。
4月から復学して、4年間で卒業した。2年生に戻って半年以上してから、コンビニでバイトもした。
Q.大学はAO入試で入って、大学は何を学んでいる?
A.9月にAO入試を受て入学した。情報学科で、プロミングだったり、経営とかマーケティング。情報をどう扱うかという勉強をしている。
Q.Yさんにとって、中学校不登校だったことは、プラスになっているのかマイナスになっている?
A.絶対、プラスになっている。不登校の時に遊んでなければ、こんなに大学で勉強しなかったと思う。大学に入って、やる気が出て、遊びって大事だと思う。
Q.大平台高校は、どんな学校生活だった?
A.制服がないので、学校にいくというより、友達に会いに行くという感じだった。本当に楽しかった。
学食がおいしいところがお勧め。前回からの新情報があって、他の学校の情報を聞いて比較すると、売店が充実していることがわかった。
Q.大学4年生で就職が決まり、どんな仕事をするの?
A.ウエーブサイトを作って、運営する仕事。
Q.ストレス弱いところがあると思うけど、仕事がきついと思ったら、自分でなんとか休むということができるかな?不登校経験があると、頑張りすぎないで休むことができると思うけど、これからもいろいろとあっても、なんとかやっていける?
A.いま研修に行ってるけど、上司に自分の弱いところをよく知っていると言われた。
Q不登校の時、苦しかったと思うけど、いま苦しい思いをしている不登校生に伝えたいことは?
A.自分の好きなことを見つける。ゲームとかでも、自分の集中できることを見つけてあげるとか。夢中になって一緒に遊べる友達とか、仲間とのつながりがが大事かな。
次回の相談会は、10月6日(日)13:30~会場は浜松市のアイミティ浜松です。
※中日新聞の取材を受け、掲載されました。

2019年09月08日
第2回「2019不登校生のための進学相談会」を開催します・
第2回「不登校生のための進学相談会」を、9月14日13:30から浜松市のアイミティ浜松で開催します。
「相談会」では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などについての情報提供するとともに、個別の相談にも対応します。
また、実際に不登校を経験して進学した方、不登校生の保護者の話を聞くことができます。
どうぞ、お気軽にご参加ください。
開催月により、会場が変わりますので、お間違えのないように確認をお願いします。
*2009年から開催。10年間で、610名378組(小中高生98名)の方が、参加しています。
◇日時
7月 6日(土)
9月14日(土)
10月 6日(日)
11月10日 (日)
13:30~16:00
◇相談会の日程と内容
13:15~ 受付
13:30 ~15:00 高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明
定時制・通信制高校で学んでいる生徒、学んだ人、不登校生の保護者の体験談
15:00 ~16:00 不登校生に関する進路およびなんでも悩み相談(個別)
◇対象
不登校生(中学、高校等)、高校中退者、引きこもりがちな若者と
その保護者の皆さん、教育関係者、不登校生の支援に関心のある方
◇参加費 無料、予約不要(途中参加可能です)
希望者には、無料で学習支援を行います(要個別相談)
◇会場
7月
ワークピア磐田
磐田市見付2898-3 TEL0538-37-8381
9月、10月、11月
アイミティ浜松
浜松市中区船越町11-11 TEL053-465-5065
◇主催 子ども育ちレスキューネット
(静岡県西部の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
http://childrescuenet.hamazo.tv/
◇後援
浜松市 浜松市教育委員会 磐田市 磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社
◇お問い合わせ・当日連絡先
TEL/090-3936-5840(子ども育ちレスキューネット 服部)

「相談会」では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などについての情報提供するとともに、個別の相談にも対応します。
また、実際に不登校を経験して進学した方、不登校生の保護者の話を聞くことができます。
どうぞ、お気軽にご参加ください。
開催月により、会場が変わりますので、お間違えのないように確認をお願いします。
*2009年から開催。10年間で、610名378組(小中高生98名)の方が、参加しています。
◇日時
10月 6日(日)
11月10日 (日)
13:30~16:00
◇相談会の日程と内容
13:15~ 受付
13:30 ~15:00 高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明
定時制・通信制高校で学んでいる生徒、学んだ人、不登校生の保護者の体験談
15:00 ~16:00 不登校生に関する進路およびなんでも悩み相談(個別)
◇対象
不登校生(中学、高校等)、高校中退者、引きこもりがちな若者と
その保護者の皆さん、教育関係者、不登校生の支援に関心のある方
◇参加費 無料、予約不要(途中参加可能です)
希望者には、無料で学習支援を行います(要個別相談)
◇会場
7月
ワークピア磐田
磐田市見付2898-3 TEL0538-37-8381
9月、10月、11月
アイミティ浜松
浜松市中区船越町11-11 TEL053-465-5065
◇主催 子ども育ちレスキューネット
(静岡県西部の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
http://childrescuenet.hamazo.tv/
◇後援
浜松市 浜松市教育委員会 磐田市 磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社
◇お問い合わせ・当日連絡先
TEL/090-3936-5840(子ども育ちレスキューネット 服部)

2019年07月15日
「2019 不登校生のための進学相談会」の1回目が終わりました
7月6日、「2019 不登校生のための進学相談会」の1回目が終わりました。
7組14名、子ども1人の参加がありました。
今回も、 関心を持って参加された学校関係者、磐田市役所の職員の参加があり、新居高校定時制先生には、学校の状況をお聞きし、個別相談などに対応していただきました。
中学2年生から、高校1年生の不登校生の相談がありました。
学校情報を知りたいというなかには、学校から「ここの学校しか入れない」と一方的に渡された学校情報を確認したいと参加され、学校が選択できることがわかり安心したという方がいました。
〇定時制って、どんなところ?
新居高校定時制の先生に、お話を伺いました。
・今年の入学生は、40名定員に対して、7名。
定員に満たなくても、試験で入学したいという意思が伝わらなかった子ども、外国籍で面接で日本語でほとんど答えられなった子どもは、不合格になった。総合的に評価するので、学力面は考慮するところはある。
・少人数で、アットホームな感じ。1クラス10~20人。生徒と教師の関係は近いが、合う合わないの相性はある。
・テストは何回でも受けることができるが、担任教師が6人なので、学習面のフォローは難しい面がある。落第はある。
・他校と比べて、進学する生徒が少ない。アルバイトから同じ職場で就職移行する生徒がいる。
トランスジェンダーの生徒がいて、手術を受けるまでは、卒業後もアルバイトで過ごしていた。
・月2回のペースで、放課後に、キャリアカウンセラー、支援団体や地域のボランティアが関わって、「定時制カフェ」を開催している。お菓子食べ、ジュース飲みながら雑談の中で悩みを拾う。先生以外の大人と繋がるきっかけとなっている。
大平台高校でも始まり、他校でも取り組んでいく予定がある。夜間定時制の教師の交流会を行う予定がある。
・全日制でも、環境の変化で通えて、再スタートをきれることもある。
・見学は、随時受付ています。生徒に、直接話を聞いてみるのがいいかも。
今回の体験談は、中1の6月から、不登校。中3からフリースクールに通い、大平台高校定時制に進学、現在静岡理工科大学4年生のYさん。
フリースクールにきたときは、過敏性腸症候群で、いつもお腹をが痛くて学校には行けないとと言っていたので、スクールでもトイレに籠ってしまうのではないかと思っていたけど、トイレに籠ることなく、面白い子だと思っていた。、フリースクールでは、よく遊んでいた。
Q.大平台高校とほかにも進学先を考えていた?
A.静岡中央高校を考えていた。大平台高校の学校見学にいったとき、トイレがきれいだった事、便座が温かい、自動点灯、トイレに並ばなくてもいいことが決め手になった。校舎も新しいのできれい。
Q.高校に入って、部活にも入って、大平台高校は楽しいよと話していたkれど、夏休みの前くらいから体調が悪くなって学校に行けなくなって、フリースクールに戻って、また4月から大平台高校に戻ったんだよね
A.そうですね。なにより、自分が朝に弱いとわかった。大平台高校定時制は、1から3部に分かれていて、1部は8:40からで朝が強い人、2部は10:40分から、3部は夜。自分は2部で、他部履修して3年で卒業を最初は目指していたが、飛ばしすぎた。
4月から復学して、4年間で卒業した。戻ってからは、無理しないで、コンビニでバイトもした。部活は、あんまり行かないようにした。
Q.大平台の良かったところは?
A.まず、学食がおいしいところが大きい。大学の購買で買う弁当とは、比べものにならない。
いまでも、また食べたい。おいしいものがあるから、学校に行っていこうというのもあった。やる気がでる。
Q.大学4年生で就職が決まり、どんな仕事をするの?
A.ウエーブサイトを作る仕事。大学に入って、一番楽しかった授業がウエーブサイトを作ることだったので、仕事にしたいと思っていた。受かって、嬉しかった。
Q.いちど、高校に行けなくなったことはあったけど、その後は順調にだったが、不登校になったときは、どんな気持ちだった?
A.行けなくていいのかな?って思った。行きたい気持ちはあったけど、朝どうしても行けなかった。やりたいことができない、もどかしさがあった。
Q.大平台高校に行けなくなっとき、お腹の痛いのが治りますようにと自転車で神社巡りをしていたこともあったけど、そういうときでも悲観的にならず、スクールで毎日麻雀やったり、よく遊んでいたよね。友達と雑談したり、楽しい時間は、子供達には大切な時間だと思った。
A.よく遊びました!!
Q.大学で、不登校だったことを話しても、信じてもらえないと思うけど?
A.信じられないとびっくりしていました。
Q.参加者に高校を選ぶアドバイスがあれば、お願いします
A.大平台高校の良いところを話すと、いろんなことができる。一般教科の他に、美術で石を削ったり、食品製造という授業でラーメンや中華まんを作ったり、幅広い授業が受けれるところが良い。大学は、A0入試で受けた。プロセンテーションの授業があって、プレゼンテーションが上手くいって受かったというところがある。自分のやりたいことがなかったとしても、どこかで役に立つ授業を受けることができるところが魅力と思う。
Q.校則は、ある?
A.ひとつだけ、床を傷つけるから、ハイヒールは禁止。メイクも服装も自由。
面白い人が多い。いろんなタイプの人がいる。プールでおぼれそうになって、ヤンキーの人が助けてくれた。今は、友達になった。
次回の相談会は、9月14日(土)13:30~会場は浜松市のアイミティ浜松です。
※静岡新聞の取材を受け、掲載されました。

7組14名、子ども1人の参加がありました。
今回も、 関心を持って参加された学校関係者、磐田市役所の職員の参加があり、新居高校定時制先生には、学校の状況をお聞きし、個別相談などに対応していただきました。
中学2年生から、高校1年生の不登校生の相談がありました。
学校情報を知りたいというなかには、学校から「ここの学校しか入れない」と一方的に渡された学校情報を確認したいと参加され、学校が選択できることがわかり安心したという方がいました。
〇定時制って、どんなところ?
新居高校定時制の先生に、お話を伺いました。
・今年の入学生は、40名定員に対して、7名。
定員に満たなくても、試験で入学したいという意思が伝わらなかった子ども、外国籍で面接で日本語でほとんど答えられなった子どもは、不合格になった。総合的に評価するので、学力面は考慮するところはある。
・少人数で、アットホームな感じ。1クラス10~20人。生徒と教師の関係は近いが、合う合わないの相性はある。
・テストは何回でも受けることができるが、担任教師が6人なので、学習面のフォローは難しい面がある。落第はある。
・他校と比べて、進学する生徒が少ない。アルバイトから同じ職場で就職移行する生徒がいる。
トランスジェンダーの生徒がいて、手術を受けるまでは、卒業後もアルバイトで過ごしていた。
・月2回のペースで、放課後に、キャリアカウンセラー、支援団体や地域のボランティアが関わって、「定時制カフェ」を開催している。お菓子食べ、ジュース飲みながら雑談の中で悩みを拾う。先生以外の大人と繋がるきっかけとなっている。
大平台高校でも始まり、他校でも取り組んでいく予定がある。夜間定時制の教師の交流会を行う予定がある。
・全日制でも、環境の変化で通えて、再スタートをきれることもある。
・見学は、随時受付ています。生徒に、直接話を聞いてみるのがいいかも。
今回の体験談は、中1の6月から、不登校。中3からフリースクールに通い、大平台高校定時制に進学、現在静岡理工科大学4年生のYさん。
フリースクールにきたときは、過敏性腸症候群で、いつもお腹をが痛くて学校には行けないとと言っていたので、スクールでもトイレに籠ってしまうのではないかと思っていたけど、トイレに籠ることなく、面白い子だと思っていた。、フリースクールでは、よく遊んでいた。
Q.大平台高校とほかにも進学先を考えていた?
A.静岡中央高校を考えていた。大平台高校の学校見学にいったとき、トイレがきれいだった事、便座が温かい、自動点灯、トイレに並ばなくてもいいことが決め手になった。校舎も新しいのできれい。
Q.高校に入って、部活にも入って、大平台高校は楽しいよと話していたkれど、夏休みの前くらいから体調が悪くなって学校に行けなくなって、フリースクールに戻って、また4月から大平台高校に戻ったんだよね
A.そうですね。なにより、自分が朝に弱いとわかった。大平台高校定時制は、1から3部に分かれていて、1部は8:40からで朝が強い人、2部は10:40分から、3部は夜。自分は2部で、他部履修して3年で卒業を最初は目指していたが、飛ばしすぎた。
4月から復学して、4年間で卒業した。戻ってからは、無理しないで、コンビニでバイトもした。部活は、あんまり行かないようにした。
Q.大平台の良かったところは?
A.まず、学食がおいしいところが大きい。大学の購買で買う弁当とは、比べものにならない。
いまでも、また食べたい。おいしいものがあるから、学校に行っていこうというのもあった。やる気がでる。
Q.大学4年生で就職が決まり、どんな仕事をするの?
A.ウエーブサイトを作る仕事。大学に入って、一番楽しかった授業がウエーブサイトを作ることだったので、仕事にしたいと思っていた。受かって、嬉しかった。
Q.いちど、高校に行けなくなったことはあったけど、その後は順調にだったが、不登校になったときは、どんな気持ちだった?
A.行けなくていいのかな?って思った。行きたい気持ちはあったけど、朝どうしても行けなかった。やりたいことができない、もどかしさがあった。
Q.大平台高校に行けなくなっとき、お腹の痛いのが治りますようにと自転車で神社巡りをしていたこともあったけど、そういうときでも悲観的にならず、スクールで毎日麻雀やったり、よく遊んでいたよね。友達と雑談したり、楽しい時間は、子供達には大切な時間だと思った。
A.よく遊びました!!
Q.大学で、不登校だったことを話しても、信じてもらえないと思うけど?
A.信じられないとびっくりしていました。
Q.参加者に高校を選ぶアドバイスがあれば、お願いします
A.大平台高校の良いところを話すと、いろんなことができる。一般教科の他に、美術で石を削ったり、食品製造という授業でラーメンや中華まんを作ったり、幅広い授業が受けれるところが良い。大学は、A0入試で受けた。プロセンテーションの授業があって、プレゼンテーションが上手くいって受かったというところがある。自分のやりたいことがなかったとしても、どこかで役に立つ授業を受けることができるところが魅力と思う。
Q.校則は、ある?
A.ひとつだけ、床を傷つけるから、ハイヒールは禁止。メイクも服装も自由。
面白い人が多い。いろんなタイプの人がいる。プールでおぼれそうになって、ヤンキーの人が助けてくれた。今は、友達になった。
次回の相談会は、9月14日(土)13:30~会場は浜松市のアイミティ浜松です。
※静岡新聞の取材を受け、掲載されました。

2019年06月24日
「2019不登校生のための進学相談会」を開催します
今年度の「不登校生のための進学相談会」の日時が決まりましたので、お知らせします。
「相談会」では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などについての情報提供するとともに、個別の相談にも対応します。
また、実際に不登校を経験して進学した方の話を聞く時間も設けます。今年も、保護者の話を聞くことができます。
どうぞ、お気軽にご参加ください。
開催月により、会場が変わりますので、お間違えのないように確認をお願いします。
*2009年から開催。10年間で、610名378組(小中高生98名)の方が、参加しています。
◇日時
7月 6日(土)
9月14日(土)
10月 6日(日)
11月10日 (日)
13:30~16:00
◇相談会の日程と内容
13:15~ 受付
13:30 ~15:00 高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明
定時制・通信制高校で学んでいる生徒、学んだ人、不登校生の保護者の体験談
15:00 ~16:00 不登校生に関する進路およびなんでも悩み相談(個別)
◇対象
不登校生(中学、高校等)、高校中退者、引きこもりがちな若者と
その保護者の皆さん、教育関係者、不登校生の支援に関心のある方
◇参加費 無料、予約不要(途中参加可能です)
希望者には、無料で学習支援を行います(要個別相談)
◇会場
7月
ワークピア磐田
磐田市見付2898-3 TEL0538-37-8381
9月、10月、11月
アイミティ浜松
浜松市中区船越町11-11 TEL053-465-5065
◇主催 子ども育ちレスキューネット
(静岡県西部の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
http://childrescuenet.hamazo.tv/
◇後援
浜松市 浜松市教育委員会 磐田市 磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社
◇お問い合わせ・当日連絡先
TEL/090-3936-5840(子ども育ちレスキューネット 服部)

「相談会」では、不登校であっても進学可能な高校、高卒認定試験(高等学校卒業程度認定試験)などについての情報提供するとともに、個別の相談にも対応します。
また、実際に不登校を経験して進学した方の話を聞く時間も設けます。今年も、保護者の話を聞くことができます。
どうぞ、お気軽にご参加ください。
開催月により、会場が変わりますので、お間違えのないように確認をお願いします。
*2009年から開催。10年間で、610名378組(小中高生98名)の方が、参加しています。
◇日時
7月 6日(土)
9月14日(土)
10月 6日(日)
11月10日 (日)
13:30~16:00
◇相談会の日程と内容
13:15~ 受付
13:30 ~15:00 高等学校、高等学校卒業資格認定試験に関する説明
定時制・通信制高校で学んでいる生徒、学んだ人、不登校生の保護者の体験談
15:00 ~16:00 不登校生に関する進路およびなんでも悩み相談(個別)
◇対象
不登校生(中学、高校等)、高校中退者、引きこもりがちな若者と
その保護者の皆さん、教育関係者、不登校生の支援に関心のある方
◇参加費 無料、予約不要(途中参加可能です)
希望者には、無料で学習支援を行います(要個別相談)
◇会場
7月
ワークピア磐田
磐田市見付2898-3 TEL0538-37-8381
9月、10月、11月
アイミティ浜松
浜松市中区船越町11-11 TEL053-465-5065
◇主催 子ども育ちレスキューネット
(静岡県西部の子ども関係NPO団体やカウンセラーからなる団体)
http://childrescuenet.hamazo.tv/
◇後援
浜松市 浜松市教育委員会 磐田市 磐田市教育委員会
静岡新聞社・静岡放送 中日新聞東海本社
◇お問い合わせ・当日連絡先
TEL/090-3936-5840(子ども育ちレスキューネット 服部)

2018年12月08日
「2018不登校生のための進学相談会」が終わりました
11月17日に開催しました「2018不登校生のための進学相談会」をもって、今年度の相談会が終了しました。
今年度の参加者は、60組86人(子ども12人)でした。
毎年、中学3年生の相談が一番多いのは変わりませんが、前もって情報を知りたいという中学1,2年生の相談が同じくらいになりました。高校生の不登校は留年か退学になりそう、転校が良いのかという相談、中退後の進路の相談も1割ありました。
毎年参加していますという方や2回目、3回目という方、2回目に子どもと参加される方などもありました。
学校関係者や支援に関わる方の参加もあり、不登校生を受け入れている学校情報について、お話をしていただきました。(第3回目の報告記事に掲載)学校現場のリアルな話は、私達にもとても参考になりました。
相談会を開催してから、今年で10年目となります。10年前はほとんどの方が、家族だけで不安や問題を抱えていて、誰にも相談できないという状況でした。
現在は、ほとんどの方が、学校のカウンセラーや支援室、適応指導教室、医療機関、発達支援センター、フリースクールなどに関わりを持ち、なんらかの支援を受けています。
保護者の方も多くの情報を持てるようになりましたが、親と子どもの不安や心配、苦しさや辛い状況は、いまも変わずあります。
発達障がいや精神疾患、家庭状況、社会環境など、以前からあった問題や課題がみえるようになり、複雑に絡み合うケースも少なくなく、問題の解決には、困難が伴うことから「相談者に寄り添いながら、ともに考える」子ども育ちレスキューネットの活動の必要性を感じています。
そのような中で、「保護者と子どもが、進路を決定するためには、子どもの状態に合った必要な情報を得ることが大事」ということを伝えるために、相談会を開催しています。
相談会は、来年度も開催の予定です。開催日時が決まり次第、ブログに更新します。
今回の体験談は、同じフリースクールに通う、来年3月に静岡中央高校通信制(以下、中央高校)を卒業予定のNくん(22歳)とMくん(18歳)。Mくんは、中1から不登校。Nくんは、小4から不登校。当会のメンバーの西村と質問形式で行いました。
西村:中央高校に進学した理由は?
N:中学生の時は、適応指導教室に通っていた。母に、夜間定時制を勧められて入学したが、
不登校だったので、通えるわけがなかったので中退。本人の選択肢はなかった。
18歳で、フリースクールに通うことになったが、当時は、トゲトゲしていた。進学を考える感じはなかった。バイトを決めて、周りの子が通信 制に通うのをみて、通信制があるかと思った。親も先生も知らなかった。19歳で、中央高校に入学した。
M:4年前、通信か通学か考えていた。週5日通うのは辛いと思っていたので、通信を知って行けると思った。
Q:不安はあった?
M:自分が行けるか?学校の雰囲気がわからなかった。
緊張はあったが、先生が話しかけてくれて、優しかったので、実際は不安は少なかっ た。
N:入学式で、初めに無理!と思ったが、通っていくうちに慣れたかな?
Q:今は、不安はない?
N,M:ない!
M:レーポートを期限内に提出することが、苦痛・・自分のやる気次第だけど。
Q:スクーリングは、自分で選択した科目を選んで受けることができけど、集まってやる体育は、苦手?
N:スキップができなくて、苦痛だった(笑)
M:レクレーションが、嫌。自己紹介ぽくのがあると、仲間っぽくするのは嫌。
N:話せる子、仲良くできる子もいる。
Q:2人組みでやるバトミントンなど、ペアになるときは?
M;異性とペアになることもあったり、他の人とかかわりたくない人は嫌かも。先生が、ペアになることもある。
秋、冬は、ウオーキング。学校の外周を歩いて終わり。早く終わるのがいい。
体育の必要なスクーリング時間は、10時間なので5回出席すれば終わる。
Q;先生は、どう?
N;全日制と変わらないと思う。
M;注意とか、あまりない。話しかければやさしく対応してくれる。
Q;特別活動については?
M;スクーリング以外に、卒業までに30時間出席が必要。ショートホームルームは、0.5時間。始業式は2時間、遠足は6時間。遠足は、現 地集合、現地解散。最初と最後の点呼のみで,その他は好きにしていい。最近は、のんほいぱーく、フルーツパークや科学館もあった。行事 苦手な人は、ホームルームで時間を稼ぐ。
Q;4年で卒業できそうで、ゴールが見えてきて良かった?
N;10年とかかかっている人もいる。5年の計画でも、何年かかってもいいと思う。
Q:いろいろあったと思うけど。
M:同時に入学した子がいて、フリースクールのフォローがあった。一人でやるのは、辛い。
通信制だと、同じ経験をしている人がいる。
N:Mと一緒だったことは、運が良かった。友人とも波長が合うといい。
西村テストは、自噴がテストを受けれるようになったら、自己申告をして受験票を出して受ける。得意科目は、先に受験して助け合っていた。2年目からは、選択科目が違ってくるので、共有が少なくなるので自分で管理していくことになる。
N:高卒認定試験で、単位を取った。倫理、世界史、地理。あまり、勉強しなかったけど、勉強した問題が出た。1年通してやるよりは、単位修得 は楽だった。
Q:卒業後の進路は?
M:まだ、焦っていない。卒業したら、運転免許を取って、就職を考えていこうと思っている。やりたいことを、ゆっくり探して、続けていきた い。
N;年齢的に、余裕がなく焦っている。アクトタワーの若者ハローワークに行って、適性検査を予約してきた。
Q:最後の参加者の方に、ひとこと。
先に、子どもに。
M:焦らなくていいと思う。
N:焦ってください。4歳違うと、ゆっくりと言ってられない。新卒枠がなくなってくる。
卒業して、お金があれば余裕がでてくると思う。不登校でも、働けばいい。人はそれぞれ、みんな同じとはいえない。
10代ではOKでも、20代になると余裕がなくなる。
Q:次は、親に。
M:自分の選択を、親は自由にしてくれたのが嬉しかった。一緒に考えてくれた。
N:自分は、親の関係が悪かった。親にしてほしいことはなく、イライラしていた。
西村:親の気持ちの余裕がない状況もある。できる範囲で、子どもに情報提供ができるといい。そのために、活動を続けていきます。
今年度の参加者は、60組86人(子ども12人)でした。
毎年、中学3年生の相談が一番多いのは変わりませんが、前もって情報を知りたいという中学1,2年生の相談が同じくらいになりました。高校生の不登校は留年か退学になりそう、転校が良いのかという相談、中退後の進路の相談も1割ありました。
毎年参加していますという方や2回目、3回目という方、2回目に子どもと参加される方などもありました。
学校関係者や支援に関わる方の参加もあり、不登校生を受け入れている学校情報について、お話をしていただきました。(第3回目の報告記事に掲載)学校現場のリアルな話は、私達にもとても参考になりました。
相談会を開催してから、今年で10年目となります。10年前はほとんどの方が、家族だけで不安や問題を抱えていて、誰にも相談できないという状況でした。
現在は、ほとんどの方が、学校のカウンセラーや支援室、適応指導教室、医療機関、発達支援センター、フリースクールなどに関わりを持ち、なんらかの支援を受けています。
保護者の方も多くの情報を持てるようになりましたが、親と子どもの不安や心配、苦しさや辛い状況は、いまも変わずあります。
発達障がいや精神疾患、家庭状況、社会環境など、以前からあった問題や課題がみえるようになり、複雑に絡み合うケースも少なくなく、問題の解決には、困難が伴うことから「相談者に寄り添いながら、ともに考える」子ども育ちレスキューネットの活動の必要性を感じています。
そのような中で、「保護者と子どもが、進路を決定するためには、子どもの状態に合った必要な情報を得ることが大事」ということを伝えるために、相談会を開催しています。
相談会は、来年度も開催の予定です。開催日時が決まり次第、ブログに更新します。
今回の体験談は、同じフリースクールに通う、来年3月に静岡中央高校通信制(以下、中央高校)を卒業予定のNくん(22歳)とMくん(18歳)。Mくんは、中1から不登校。Nくんは、小4から不登校。当会のメンバーの西村と質問形式で行いました。
西村:中央高校に進学した理由は?
N:中学生の時は、適応指導教室に通っていた。母に、夜間定時制を勧められて入学したが、
不登校だったので、通えるわけがなかったので中退。本人の選択肢はなかった。
18歳で、フリースクールに通うことになったが、当時は、トゲトゲしていた。進学を考える感じはなかった。バイトを決めて、周りの子が通信 制に通うのをみて、通信制があるかと思った。親も先生も知らなかった。19歳で、中央高校に入学した。
M:4年前、通信か通学か考えていた。週5日通うのは辛いと思っていたので、通信を知って行けると思った。
Q:不安はあった?
M:自分が行けるか?学校の雰囲気がわからなかった。
緊張はあったが、先生が話しかけてくれて、優しかったので、実際は不安は少なかっ た。
N:入学式で、初めに無理!と思ったが、通っていくうちに慣れたかな?
Q:今は、不安はない?
N,M:ない!
M:レーポートを期限内に提出することが、苦痛・・自分のやる気次第だけど。
Q:スクーリングは、自分で選択した科目を選んで受けることができけど、集まってやる体育は、苦手?
N:スキップができなくて、苦痛だった(笑)
M:レクレーションが、嫌。自己紹介ぽくのがあると、仲間っぽくするのは嫌。
N:話せる子、仲良くできる子もいる。
Q:2人組みでやるバトミントンなど、ペアになるときは?
M;異性とペアになることもあったり、他の人とかかわりたくない人は嫌かも。先生が、ペアになることもある。
秋、冬は、ウオーキング。学校の外周を歩いて終わり。早く終わるのがいい。
体育の必要なスクーリング時間は、10時間なので5回出席すれば終わる。
Q;先生は、どう?
N;全日制と変わらないと思う。
M;注意とか、あまりない。話しかければやさしく対応してくれる。
Q;特別活動については?
M;スクーリング以外に、卒業までに30時間出席が必要。ショートホームルームは、0.5時間。始業式は2時間、遠足は6時間。遠足は、現 地集合、現地解散。最初と最後の点呼のみで,その他は好きにしていい。最近は、のんほいぱーく、フルーツパークや科学館もあった。行事 苦手な人は、ホームルームで時間を稼ぐ。
Q;4年で卒業できそうで、ゴールが見えてきて良かった?
N;10年とかかかっている人もいる。5年の計画でも、何年かかってもいいと思う。
Q:いろいろあったと思うけど。
M:同時に入学した子がいて、フリースクールのフォローがあった。一人でやるのは、辛い。
通信制だと、同じ経験をしている人がいる。
N:Mと一緒だったことは、運が良かった。友人とも波長が合うといい。
西村テストは、自噴がテストを受けれるようになったら、自己申告をして受験票を出して受ける。得意科目は、先に受験して助け合っていた。2年目からは、選択科目が違ってくるので、共有が少なくなるので自分で管理していくことになる。
N:高卒認定試験で、単位を取った。倫理、世界史、地理。あまり、勉強しなかったけど、勉強した問題が出た。1年通してやるよりは、単位修得 は楽だった。
Q:卒業後の進路は?
M:まだ、焦っていない。卒業したら、運転免許を取って、就職を考えていこうと思っている。やりたいことを、ゆっくり探して、続けていきた い。
N;年齢的に、余裕がなく焦っている。アクトタワーの若者ハローワークに行って、適性検査を予約してきた。
Q:最後の参加者の方に、ひとこと。
先に、子どもに。
M:焦らなくていいと思う。
N:焦ってください。4歳違うと、ゆっくりと言ってられない。新卒枠がなくなってくる。
卒業して、お金があれば余裕がでてくると思う。不登校でも、働けばいい。人はそれぞれ、みんな同じとはいえない。
10代ではOKでも、20代になると余裕がなくなる。
Q:次は、親に。
M:自分の選択を、親は自由にしてくれたのが嬉しかった。一緒に考えてくれた。
N:自分は、親の関係が悪かった。親にしてほしいことはなく、イライラしていた。
西村:親の気持ちの余裕がない状況もある。できる範囲で、子どもに情報提供ができるといい。そのために、活動を続けていきます。