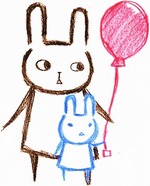2023年07月10日
第1回「2023不登校生のための進路相談会」を開催しました。
7月4日、第1回「2023不登校生のための進路相談会」を、磐田市のワークピア磐田で開催しました。
参加者は、10組15名(子ども2名)、支援者の方の参加もありました。
中2、中3の参加者が多くありましたが、小学生や中1の参加者もあり、情報を早くほしい、情報を整理したいと具体的な相談も増えてきています。
今回も、浜名高校定時制の中村先生が参加してくださいました。
説明会の後は、閉会まで中村先生と体験談を話してくださった伊藤さんと直接お話しする参加者の方がいました。
〇浜名高校の定時制の中村先生から、定時制の情報。
磐田市の磐田南高校定時制は、定員以上の応募がある。
浜名高校は30名くらい、他の夜間定時制は15から20名くらいの応募がある。
1学年の定員は40名。
定員割れをしていても、全員合格するわけではない。
高校に合格することがゴールではない。入学してからが大切。
入試では学校に通いたいという、頑張りたいという前向きの姿勢を見せることが大切。
アドミッションポリシー(入学者の受け入れ方針)がHPに載っているので確認して欲しい。
1学年30名を超えるところではクラスを2つに分けるところが多い。(磐田南は全学年、浜名は1年生のみ)
学年制の学校の場合、原級留置があるが、1科目でも単位が取れなければ原級留置の学校もあれば2科目までは仮進級ができる学校もある。(取れなかった分の科目は静岡中央高校の通信制などで単位修得しなければならない)
高校には必履修科目があり、単位制の学校でもその科目は履修しなければならない。履修する順番がある科目もあるので注意が必要。学年制の学校の履修科目は必履修科目以外は少ない。
定時制には給食がある。食堂があるところもあるが捕食(パンと牛乳程度)のところもある。
放課後は部活動や部活動以外のスポーツなどをして楽しく過ごしている生徒も多い。
定時制はやんちゃな生徒が多いイメージを持たれるが今はほとんどいない。髪型、髪色、ピアスなど一見すると派手な生徒もいるが、後輩の面倒見が良かったりやさしかったりする。
在学中のアルバイトを就職に活かすことを勧めている。働きぶりを評価してもらって就職につなげている。
各学校それぞれルールが違ったり、特徴があるので是非一度見学に来てください。
〇今回の体験談は、小4から不登校になり、小6から通ったフリースクールに通い、通信制高校を卒業して、フリースクールのスタッフとして働いている伊藤朋美さん。
質問者は、当団体代表(フリースクールドリームフィールド代表)です。
大山:伊藤萌美さん、「もみちん」と言われています。
フリースクールに入ったのは、小学校6年生のとき?
伊藤:小学校6年生のときにドリームフィールドができて、私がフリースクールに通うようになった。学校に通わなくなったのは、小学校4年生の春でした。
大山:今までは、進学を焦点に置いていたけど、不登校に関する理解とか、もっと広くみて生き方とか不登校との向き合い方を話しができたらと思う。
不登校になったときの気持ちは?
大山:
伊藤:私の中では、これが嫌だから学校に行けないという明確な理由がわからなくて。
学校に通っていたときから、クラスの中でどういう風に立ち振る舞いをして、どういう自分をやっていればということを、ずっと気にしていた。それは、のちのち気が付いたことですが、クラス替えがあって、クラスがどうなるかでその一年影響がある。小学校4年生の時にクラス替えがあり同じクラスの子をみて、そのときに「この中でやっていけない」と思ったのがきっかけとなったと思うけど、そのときは自覚してなかった。
日曜日のちびまるこちゃんが始まる時間になると、「おなかが痛い」「ご飯が食べれない」と気持ちの面より、体調の面で先に学校に行くことにブレーキがかかって、なぜかわからないけど学校に行けない、自分に何がストレスか負担がかかっているか自覚はなかったけど、じわじわと追いつめられていた感じ。
大山:お姉ちゃんも不登校だったよね。お姉ちゃんに対する親の対応は違った?
伊藤:姉が7つ年上で、私はいま31歳。姉の頃の方が不登校になるということが少なくて、周りにもいなくて、話を聞く場もなかったので、両親も祖父母も戸惑っていて、学校に行くのが当然、どうにかして学校に行かせないと動いていて、ランドセル背負わせて校門までに連れて行ってた。姉もすんなり学校に行かないという選択ができなかった。いまも、姉の方が追いつめられた感じがある。家族も戸惑う気持ちはあるけど、子どもの気持ちを置き去りにしちゃうと、のちのちあとに響くなと思う。姉はしばらくこもっていたので、私には関しては「どうして行かないの」とか行けるようにしようというのはなかった。
姉のおかげで、私は不登校になるという選択をすんなり受け入れられたかなと思う。
大山:最初はお姉ちゃんが主治医に紹介されてきたけど、不安が強くて。もみちんが一緒についてきて、明るいと思った。親の対応とか追い込み方があったと思うけど、お母さんが学校に行かないことを何か言っていた?
伊藤:あんまり、言わなかった。何が嫌だったか母もわからなかった、私自身友だち関係でも行きづらさを小学校4年生のとき感じていた。もともと集団生活が得意ではなかった。
幼稚園の頃も行きたくないという子どもだった。いろんなことを周りの子たちに合わせて動くということが苦手だっただろうなと思う。
友だち関係がうまくいってなというのは、母もわかっていたと思う。決定的なところは、わかっていなくて戸惑っていた。
大山:子どもを追い込んでしまうということは、親も悪気はなく子どものためにと思って考えてしまうけど、結果的に追いこんでしまうことがある。ほかの子ども達をみても発達の特性だったり、個性だったりとか、学校に対する苦手意識だったりとか、別に病的な症状がでたり、より多くの不安感を持ったり、後からついてくるものなので、自分たちが関わるときに一番大変だなと思うときは2次障がい的な不安や精神疾患を和らげていくことが、最初の作業になる。もみちんのように明るく通ってくれる子の方が接しやすくなるというのはある。
中学に入ったころは、コツコツ勉強してたよね。
伊藤:講師の方に勉強を教わっていた。自分の中で勉強していくのが安心というのがあった。学校の中では、学校で勉強に対しては苦しくなくて、私の場合は人間関係だった。勉強にはストレスはなく、流れで沿っていくのが安心だった。いまは、何も覚えていない (笑)
大山:静岡中央高校に入って、高校はどうだった?
伊藤:ドリームフィールドは、自分より上の人が通ってどういうところか聞いていたし、知っている人が在籍している安心感があり、ドリームフィールドに通いながら高校の卒業を目指そうと思った。
高校が好きだったかというとそうではなく、良かったことは、友だち関係を強制されないこと。人とのつながり、うわべだけでもどこかにグループに所属するとか、学校生活が苦しくクラスの中でやっていけるというのを作るのは結構しんどい。
静岡中央高校通信制は、クラスは一応あるけどクラスで何かしましょうというのはない。ホームルームはあるけど、クラスの人が誰かも正直わからないっていうくらいのクラス分けで、友だちをつくらなくていいいというのがすごく良かった。
大山:もみちんの場合は、割り切れたのは良かったと思う
学校にいかなくちゃとか勉強しなくちゃ、友だちつくらないといけないとかとではなく、私は学校苦手だし、友だちつくらなくても私の好きなことやればいいと割り切れていた。
ベースを始めたのは、いつ?
伊藤:ドリームフィールドに入って、半年以上たってから。
大山:スクールオブロックというイベントに参加して、スクエアというバンドの人に見込まれて、プロにならないかと誘われたけど、断ったのはなぜ?
伊藤:自分の中でベースを弾くのは、誰かに称賛されるものではなかった。
学校に通っているときの悩みは「みんなには得意なものがあるけど、自分にはない」と思ってしんどく感じていた。一生懸命、好きなことを探していたけどみつからなかった。
ドリームフィールドに入って、好きなことをみつけようという意識から離れたときに、ベースをやることになって、自分の好きなこと得意なことになった。
それを大きくしていきたいとかというのではなく、自分の中で好きとか得意を育てていきたいと思った。東京って怖いから行かないと思った。
大山:周りに評価されるためにでなく、自分自身がやりたいから続けているから良いね。
伊藤:いまでいうと「イイネ!」の数が多いとかリツイートが多いとかという評価でなく、自分の中であのときより上手くなっているとか、こういう風にやっていこうとか、自分がどうしていきたいかというのがあって、いまも続いていると思う。
大山:承認欲求が自分を苦しめてしまっている子が多い。割り切ってしまう、振り切ってしまうと生き方がカラフルになってくる。
ドリームフィールドで、仕事で子ども達と関わるようになったのはいつ?
伊藤:ドリームフィールドに入ってくる子に、先輩後輩という立ち位置ではなくオープンに向かい入れてあげようというのが、決まりではなく空気感。中学、高校の頃から、みんなであとからきた子だったり年下の子のサポートできるように、スタッフから自分自身もサポートしてもらっていた。19歳ころから「仕事としてやってみる?」と言われて、支援学校に通っている子が放課後にきていたので、その子たちとの関りで責任が増えた。
大山:学童保育から始めて、だんだんスキルを身につけて、いまは重要なスタッフのひとり。私は子ども達との直接的な関りをなるべく減らして、みんなに任せているが、任せられるスタッフ。もともとの感性と磨かれた経緯、みんなと関わる中で磨かれた感性ができたと思う。信頼できるスタッフ。
一般的な臨床心理士、スクールカウンセラーとか全然違う、経験を積んでいる力があると思って頼りにしている。
いま大変だなと思うことはある?
伊藤:私は不登校を経験してドリームフィールドにきている、子ども達も不登校になってドリームフィールドにきているけど、みんなが私と同じ考えではない。10人いれば10人理由が違う、似てても細かい生きづらさは、それぞれ違うので、当たり前だけど自分と違うので、自分の経験をかぶせていかないようにしようというのはある。
大山:それは、参加している親御さんの心理としても参考になると思う。「自分はこうだったから、この子もこうさせなきゃ」と考えるのは、別の人格であるわけだけだから、その辺りを理解していくことが大切。
今仕事をして、やりがいはある?
伊藤:悩むことの方が多いけど。やりがいとは別かもしれないけど、小学生の頃の自分に声をかけるとしたら「そんなに張りつめていなくてもいい」って思いがある。
今日は保護者の方だけではなくて、これから進路を考える子ども達もきている。ここにきていると時点で、自分のことに向き合っているけど向き合い過ぎると「どうなちゃうだろうか?」と不安が募ってしまうことがある。いま来ている子ども達、ドリームフィールドの子ども達、自分が10代の頃もそうだったけど、「なんとかなるさ」は無責任過ぎるけど、道を固めて固めていったら、すごい明るい未来があるっていうことではなかったりと思う。
ある意味、ちょっと楽観的部分、そんなに頑張らなくてもいいのかもとか。不登校は悪いことではないよねって、むしろ不登校を選択できている時点ですごいこと。
いい意味での遊びの部分を持てるのがいいかなっていうのは、いまの私にも通じることもある。
大山:今回の進路相談会は、「高校入学」というタイトルにしてあるけど、生き方の全体と考えてみると高校進学は、ちっぽけなこと。本当は、もっと先のこととか奥深いところを考えていって、生きることを楽しむように支えてあげたらいいと思います。
生きることを支えるために進学のこととか、勉強のことを言っていたはずなのに、いつのまにか生きることが苦しくなってしまうような追い込み方してしまうことも多いので、親御さんの進学や勉強はひとつの分岐点に過ぎないということで、広くとらえてほしいと思います。
次回は、8月27日(日)13:30~アイミティ浜松です。
※静岡新聞の取材がありました。

参加者は、10組15名(子ども2名)、支援者の方の参加もありました。
中2、中3の参加者が多くありましたが、小学生や中1の参加者もあり、情報を早くほしい、情報を整理したいと具体的な相談も増えてきています。
今回も、浜名高校定時制の中村先生が参加してくださいました。
説明会の後は、閉会まで中村先生と体験談を話してくださった伊藤さんと直接お話しする参加者の方がいました。
〇浜名高校の定時制の中村先生から、定時制の情報。
磐田市の磐田南高校定時制は、定員以上の応募がある。
浜名高校は30名くらい、他の夜間定時制は15から20名くらいの応募がある。
1学年の定員は40名。
定員割れをしていても、全員合格するわけではない。
高校に合格することがゴールではない。入学してからが大切。
入試では学校に通いたいという、頑張りたいという前向きの姿勢を見せることが大切。
アドミッションポリシー(入学者の受け入れ方針)がHPに載っているので確認して欲しい。
1学年30名を超えるところではクラスを2つに分けるところが多い。(磐田南は全学年、浜名は1年生のみ)
学年制の学校の場合、原級留置があるが、1科目でも単位が取れなければ原級留置の学校もあれば2科目までは仮進級ができる学校もある。(取れなかった分の科目は静岡中央高校の通信制などで単位修得しなければならない)
高校には必履修科目があり、単位制の学校でもその科目は履修しなければならない。履修する順番がある科目もあるので注意が必要。学年制の学校の履修科目は必履修科目以外は少ない。
定時制には給食がある。食堂があるところもあるが捕食(パンと牛乳程度)のところもある。
放課後は部活動や部活動以外のスポーツなどをして楽しく過ごしている生徒も多い。
定時制はやんちゃな生徒が多いイメージを持たれるが今はほとんどいない。髪型、髪色、ピアスなど一見すると派手な生徒もいるが、後輩の面倒見が良かったりやさしかったりする。
在学中のアルバイトを就職に活かすことを勧めている。働きぶりを評価してもらって就職につなげている。
各学校それぞれルールが違ったり、特徴があるので是非一度見学に来てください。
〇今回の体験談は、小4から不登校になり、小6から通ったフリースクールに通い、通信制高校を卒業して、フリースクールのスタッフとして働いている伊藤朋美さん。
質問者は、当団体代表(フリースクールドリームフィールド代表)です。
大山:伊藤萌美さん、「もみちん」と言われています。
フリースクールに入ったのは、小学校6年生のとき?
伊藤:小学校6年生のときにドリームフィールドができて、私がフリースクールに通うようになった。学校に通わなくなったのは、小学校4年生の春でした。
大山:今までは、進学を焦点に置いていたけど、不登校に関する理解とか、もっと広くみて生き方とか不登校との向き合い方を話しができたらと思う。
不登校になったときの気持ちは?
大山:
伊藤:私の中では、これが嫌だから学校に行けないという明確な理由がわからなくて。
学校に通っていたときから、クラスの中でどういう風に立ち振る舞いをして、どういう自分をやっていればということを、ずっと気にしていた。それは、のちのち気が付いたことですが、クラス替えがあって、クラスがどうなるかでその一年影響がある。小学校4年生の時にクラス替えがあり同じクラスの子をみて、そのときに「この中でやっていけない」と思ったのがきっかけとなったと思うけど、そのときは自覚してなかった。
日曜日のちびまるこちゃんが始まる時間になると、「おなかが痛い」「ご飯が食べれない」と気持ちの面より、体調の面で先に学校に行くことにブレーキがかかって、なぜかわからないけど学校に行けない、自分に何がストレスか負担がかかっているか自覚はなかったけど、じわじわと追いつめられていた感じ。
大山:お姉ちゃんも不登校だったよね。お姉ちゃんに対する親の対応は違った?
伊藤:姉が7つ年上で、私はいま31歳。姉の頃の方が不登校になるということが少なくて、周りにもいなくて、話を聞く場もなかったので、両親も祖父母も戸惑っていて、学校に行くのが当然、どうにかして学校に行かせないと動いていて、ランドセル背負わせて校門までに連れて行ってた。姉もすんなり学校に行かないという選択ができなかった。いまも、姉の方が追いつめられた感じがある。家族も戸惑う気持ちはあるけど、子どもの気持ちを置き去りにしちゃうと、のちのちあとに響くなと思う。姉はしばらくこもっていたので、私には関しては「どうして行かないの」とか行けるようにしようというのはなかった。
姉のおかげで、私は不登校になるという選択をすんなり受け入れられたかなと思う。
大山:最初はお姉ちゃんが主治医に紹介されてきたけど、不安が強くて。もみちんが一緒についてきて、明るいと思った。親の対応とか追い込み方があったと思うけど、お母さんが学校に行かないことを何か言っていた?
伊藤:あんまり、言わなかった。何が嫌だったか母もわからなかった、私自身友だち関係でも行きづらさを小学校4年生のとき感じていた。もともと集団生活が得意ではなかった。
幼稚園の頃も行きたくないという子どもだった。いろんなことを周りの子たちに合わせて動くということが苦手だっただろうなと思う。
友だち関係がうまくいってなというのは、母もわかっていたと思う。決定的なところは、わかっていなくて戸惑っていた。
大山:子どもを追い込んでしまうということは、親も悪気はなく子どものためにと思って考えてしまうけど、結果的に追いこんでしまうことがある。ほかの子ども達をみても発達の特性だったり、個性だったりとか、学校に対する苦手意識だったりとか、別に病的な症状がでたり、より多くの不安感を持ったり、後からついてくるものなので、自分たちが関わるときに一番大変だなと思うときは2次障がい的な不安や精神疾患を和らげていくことが、最初の作業になる。もみちんのように明るく通ってくれる子の方が接しやすくなるというのはある。
中学に入ったころは、コツコツ勉強してたよね。
伊藤:講師の方に勉強を教わっていた。自分の中で勉強していくのが安心というのがあった。学校の中では、学校で勉強に対しては苦しくなくて、私の場合は人間関係だった。勉強にはストレスはなく、流れで沿っていくのが安心だった。いまは、何も覚えていない (笑)
大山:静岡中央高校に入って、高校はどうだった?
伊藤:ドリームフィールドは、自分より上の人が通ってどういうところか聞いていたし、知っている人が在籍している安心感があり、ドリームフィールドに通いながら高校の卒業を目指そうと思った。
高校が好きだったかというとそうではなく、良かったことは、友だち関係を強制されないこと。人とのつながり、うわべだけでもどこかにグループに所属するとか、学校生活が苦しくクラスの中でやっていけるというのを作るのは結構しんどい。
静岡中央高校通信制は、クラスは一応あるけどクラスで何かしましょうというのはない。ホームルームはあるけど、クラスの人が誰かも正直わからないっていうくらいのクラス分けで、友だちをつくらなくていいいというのがすごく良かった。
大山:もみちんの場合は、割り切れたのは良かったと思う
学校にいかなくちゃとか勉強しなくちゃ、友だちつくらないといけないとかとではなく、私は学校苦手だし、友だちつくらなくても私の好きなことやればいいと割り切れていた。
ベースを始めたのは、いつ?
伊藤:ドリームフィールドに入って、半年以上たってから。
大山:スクールオブロックというイベントに参加して、スクエアというバンドの人に見込まれて、プロにならないかと誘われたけど、断ったのはなぜ?
伊藤:自分の中でベースを弾くのは、誰かに称賛されるものではなかった。
学校に通っているときの悩みは「みんなには得意なものがあるけど、自分にはない」と思ってしんどく感じていた。一生懸命、好きなことを探していたけどみつからなかった。
ドリームフィールドに入って、好きなことをみつけようという意識から離れたときに、ベースをやることになって、自分の好きなこと得意なことになった。
それを大きくしていきたいとかというのではなく、自分の中で好きとか得意を育てていきたいと思った。東京って怖いから行かないと思った。
大山:周りに評価されるためにでなく、自分自身がやりたいから続けているから良いね。
伊藤:いまでいうと「イイネ!」の数が多いとかリツイートが多いとかという評価でなく、自分の中であのときより上手くなっているとか、こういう風にやっていこうとか、自分がどうしていきたいかというのがあって、いまも続いていると思う。
大山:承認欲求が自分を苦しめてしまっている子が多い。割り切ってしまう、振り切ってしまうと生き方がカラフルになってくる。
ドリームフィールドで、仕事で子ども達と関わるようになったのはいつ?
伊藤:ドリームフィールドに入ってくる子に、先輩後輩という立ち位置ではなくオープンに向かい入れてあげようというのが、決まりではなく空気感。中学、高校の頃から、みんなであとからきた子だったり年下の子のサポートできるように、スタッフから自分自身もサポートしてもらっていた。19歳ころから「仕事としてやってみる?」と言われて、支援学校に通っている子が放課後にきていたので、その子たちとの関りで責任が増えた。
大山:学童保育から始めて、だんだんスキルを身につけて、いまは重要なスタッフのひとり。私は子ども達との直接的な関りをなるべく減らして、みんなに任せているが、任せられるスタッフ。もともとの感性と磨かれた経緯、みんなと関わる中で磨かれた感性ができたと思う。信頼できるスタッフ。
一般的な臨床心理士、スクールカウンセラーとか全然違う、経験を積んでいる力があると思って頼りにしている。
いま大変だなと思うことはある?
伊藤:私は不登校を経験してドリームフィールドにきている、子ども達も不登校になってドリームフィールドにきているけど、みんなが私と同じ考えではない。10人いれば10人理由が違う、似てても細かい生きづらさは、それぞれ違うので、当たり前だけど自分と違うので、自分の経験をかぶせていかないようにしようというのはある。
大山:それは、参加している親御さんの心理としても参考になると思う。「自分はこうだったから、この子もこうさせなきゃ」と考えるのは、別の人格であるわけだけだから、その辺りを理解していくことが大切。
今仕事をして、やりがいはある?
伊藤:悩むことの方が多いけど。やりがいとは別かもしれないけど、小学生の頃の自分に声をかけるとしたら「そんなに張りつめていなくてもいい」って思いがある。
今日は保護者の方だけではなくて、これから進路を考える子ども達もきている。ここにきていると時点で、自分のことに向き合っているけど向き合い過ぎると「どうなちゃうだろうか?」と不安が募ってしまうことがある。いま来ている子ども達、ドリームフィールドの子ども達、自分が10代の頃もそうだったけど、「なんとかなるさ」は無責任過ぎるけど、道を固めて固めていったら、すごい明るい未来があるっていうことではなかったりと思う。
ある意味、ちょっと楽観的部分、そんなに頑張らなくてもいいのかもとか。不登校は悪いことではないよねって、むしろ不登校を選択できている時点ですごいこと。
いい意味での遊びの部分を持てるのがいいかなっていうのは、いまの私にも通じることもある。
大山:今回の進路相談会は、「高校入学」というタイトルにしてあるけど、生き方の全体と考えてみると高校進学は、ちっぽけなこと。本当は、もっと先のこととか奥深いところを考えていって、生きることを楽しむように支えてあげたらいいと思います。
生きることを支えるために進学のこととか、勉強のことを言っていたはずなのに、いつのまにか生きることが苦しくなってしまうような追い込み方してしまうことも多いので、親御さんの進学や勉強はひとつの分岐点に過ぎないということで、広くとらえてほしいと思います。
次回は、8月27日(日)13:30~アイミティ浜松です。
※静岡新聞の取材がありました。